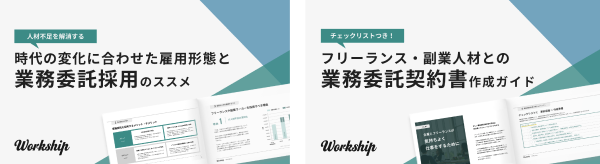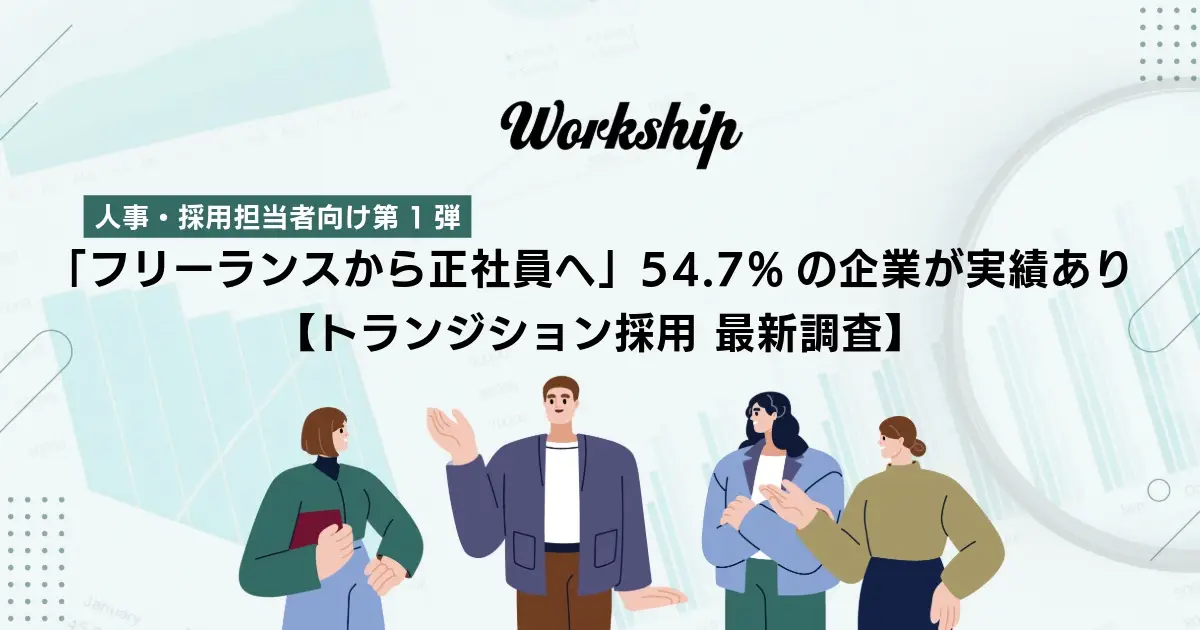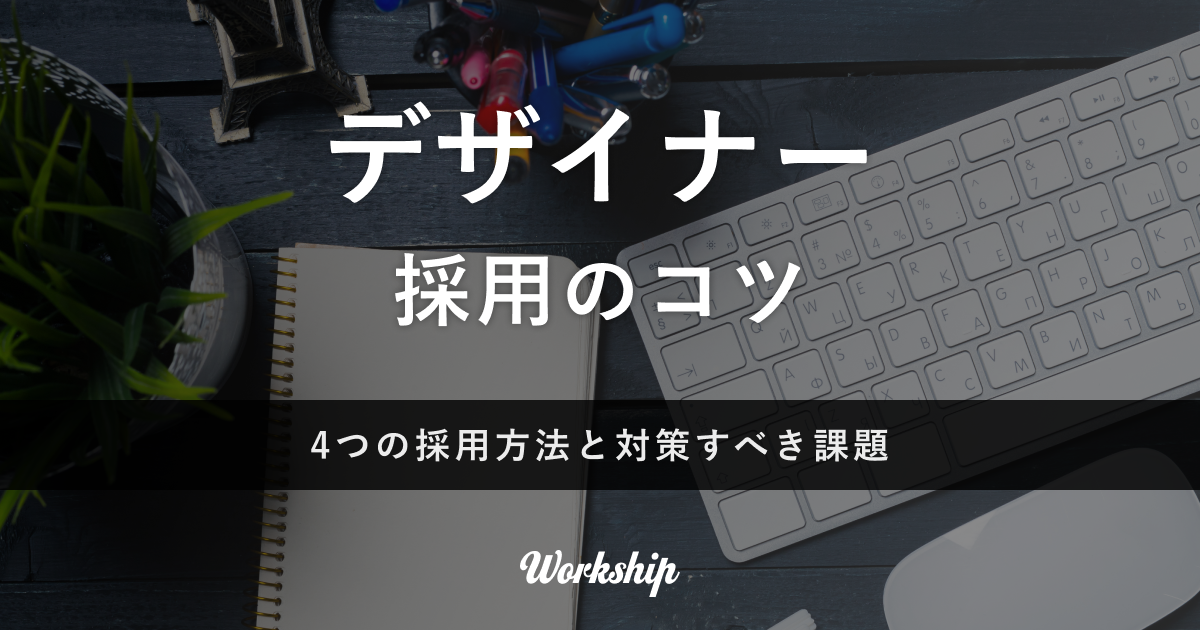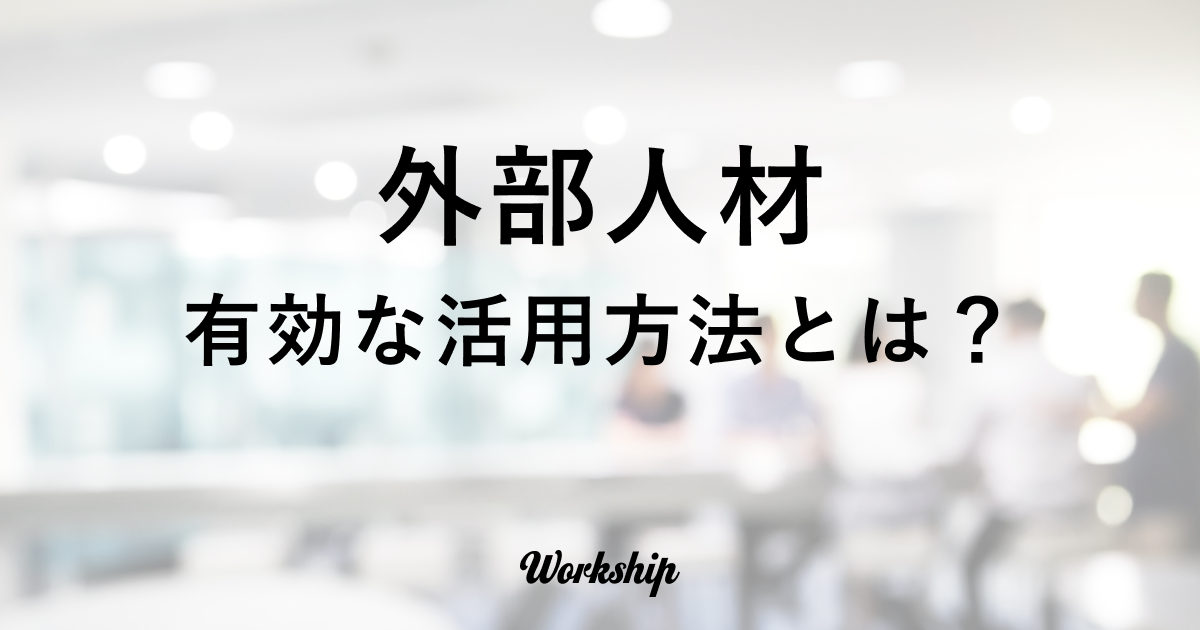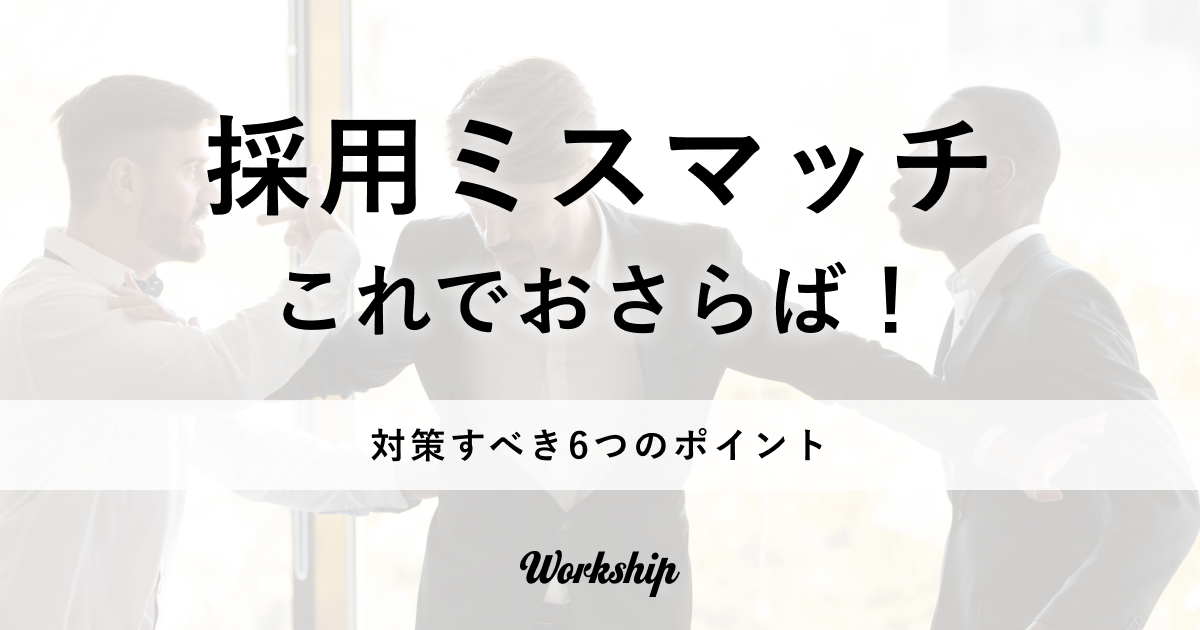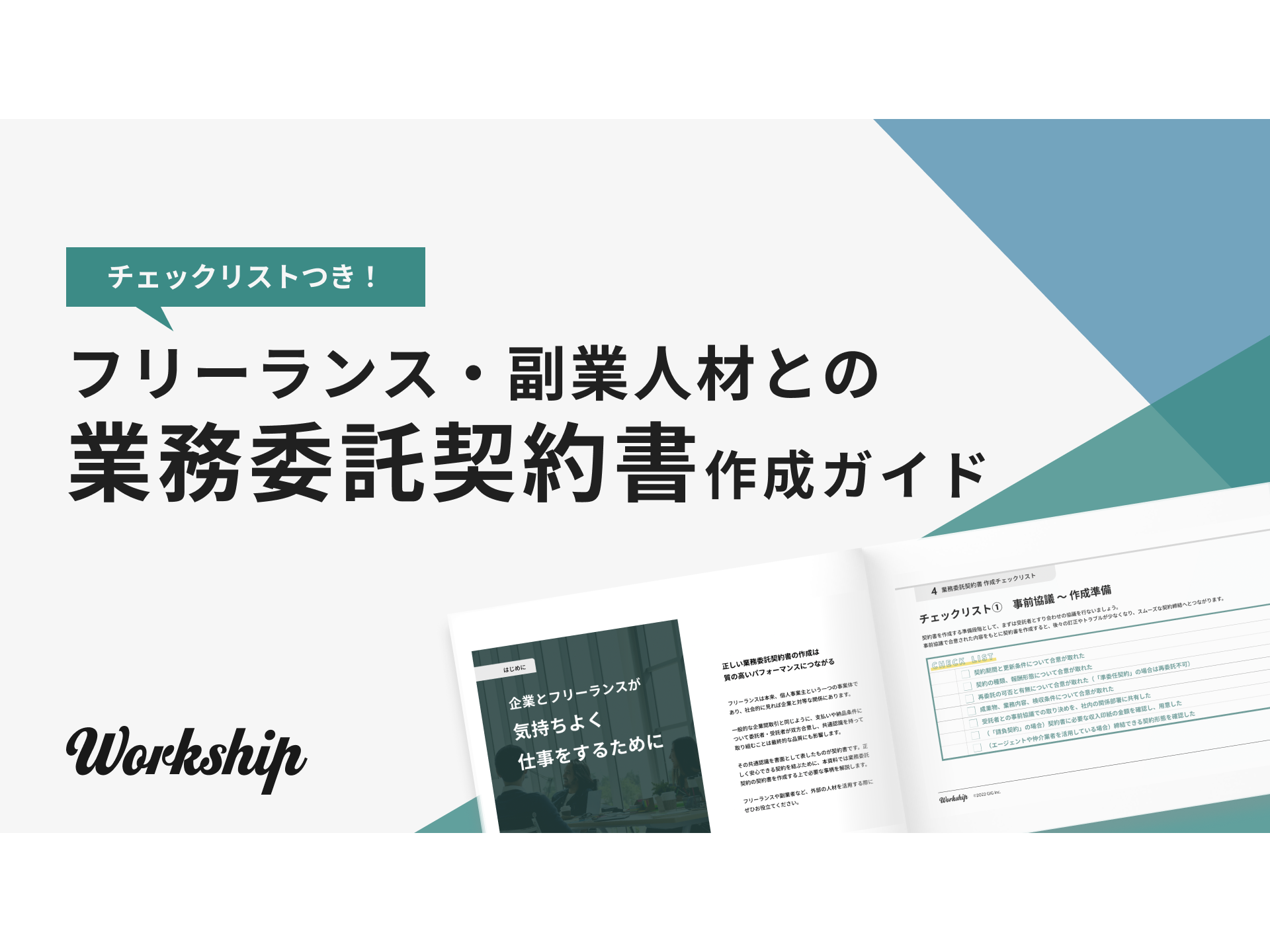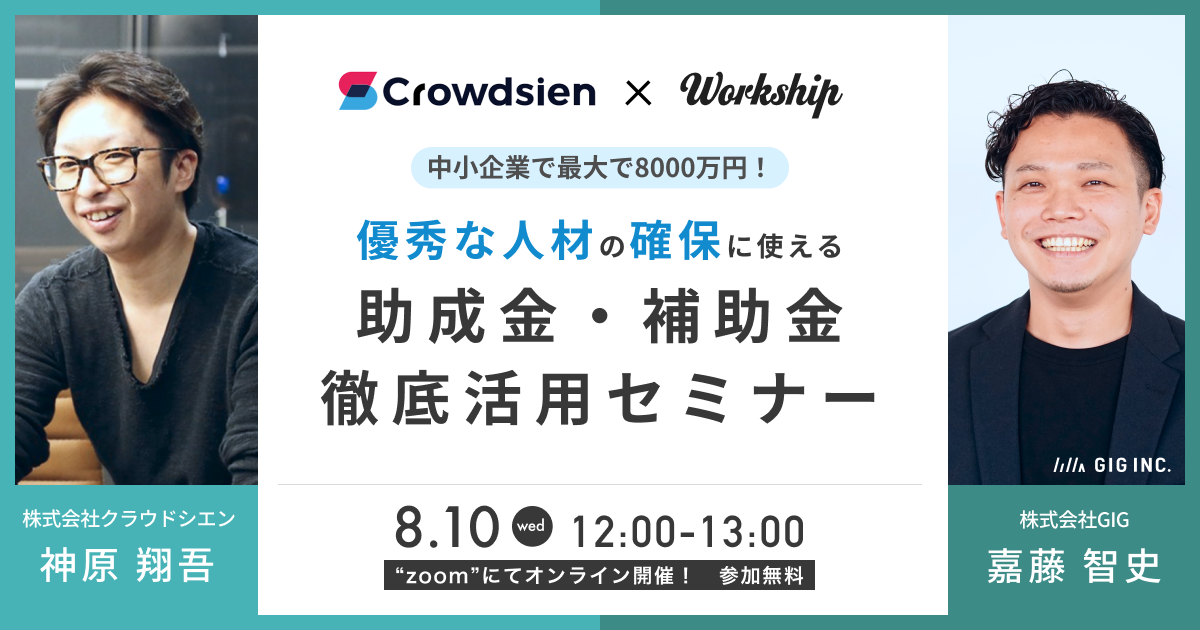フリーランス新法とは?企業がとるべき対応や罰則などわかりやすく解説
働き方の多様化に伴い、近年フリーランスとして働く人が増えています。しかしフリーランスの中には、報酬未払いや不当な契約条件の提示といった問題に直面している人もいます。こうした背景を受けて施行されたのが、「フリーランス新法」です。発注側(企業)が法令を遵守しなければ、ペナルティを受ける可能性があります。
そこで本記事では、フリーランス新法の概要や適用対象、企業が遵守すべきポイントなど、わかりやすく解説していきます。「フリーランス新法の目的や違反時の罰則など知りたい」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
※本記事ではおもに、公正取引委員会が提供するフリーランス法特設サイトとリーフレットの情報をもとに作成。
フリーランス新法はいつから施行された?
フリーランス新法、正式名称「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」は、2024年(令和6年)11月1日に施行されました。この法律は、フリーランスと発注事業者との取引を適正化しつつ、フリーランスの労働環境を整えることを目的としています。
発注事業者(企業)は、透明性のある取引や、公平な契約条件の提示が求められます。外部人材に業務を委託している企業は、早めに対応しておきましょう。
フリーランス新法が誕生した背景
フリーランス新法が誕生した背景には、フリーランス人口の増加と、それに伴う取引トラブルの深刻化があります。総務省統計局が2022年に行った調査では、フリーランスを本業にしている人は約209万人と推計。また内閣府の調査では、「フリーランスの約4割が仕事上でトラブルを経験している」と報告しています。報酬の遅延や未払い、契約内容の不明確さといった問題が浮き彫りとなり、国が法整備に乗り出しました。
発注事業者(企業)側はこれまで以上に公正な取引を心がけ、フリーランスと健全な関係を構築する必要があります。
出典:総務省統計局_基幹統計として初めて把握したフリーランスの働き方~令和4年就業構造基本調査の結果から~ / 内閣府_フリーランス実態調査結果
フリーランス新法の対象企業
フリーランス新法とは、フリーランスと取引する企業に対し、新たな義務を課す法律のことです。発注側は法律上で「業務委託事業者(特定業務委託事業者)」と定義されており、具体的には以下のような企業が該当します。
- 従業員を雇用している企業
- 代表者一名のみの企業や個人事業主
ここでの「従業員」は、「週20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」を指すため、短時間のアルバイトや家族従業員は「従業員」に含まれません。また、フリーランスとの取引頻度や契約期間にかかわらず、スポット契約であっても新法の対象となるため注意しましょう。
フリーランス新法の対象取引
フリーランス新法は、「物品の製造・販売」や「情報成果物の作成」といった取引が対象となります。たとえば、以下のような業務委託が該当します。
- Webサイトの制作
- 記事の執筆
- 動画編集
- Webデザイン
- プログラミング
- コンサルティング業務 など
ただし、一般消費者が家族写真の撮影を依頼する場合や、フリーランスが自作の作品を販売する取引は対象外です。実態として雇用関係にあるケースでは、労働関係の法令が適用されるため新法は適用されません。
契約書を交わしていなくても、実質的な業務委託であれば対象となります。形式だけで判断せず、実際の業務や関係性に基づいて対応していきましょう。
フリーランス新法で企業が対応すべき5つの項目
フリーランス新法の施行により、企業はフリーランスとの取引でいくつか重要な点に対応する必要があります。
これらの対応を怠ると法的リスクが生じるだけでなく、企業の信頼失墜にも繋がりかねません。ここでは具体的に、新法で企業が対応すべき5つの項目について解説していきます。
1.契約や取引条件を明示する
フリーランス新法では、契約や取引条件を明確にするよう発注事業者に求めています。そのため書面や電磁的記録を用いて、以下の事項を明らかにしておきましょう。
- 業務内容
- 報酬額
- 支払期日
- 発注事業者とフリーランスの名称
- 業務委託をした日
- 給付を受領/役務提供を受ける日と場所
- (検査を行う場合)検査完了日
- (現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項
これらの情報を曖昧にしたまま契約を進めると、法律違反となる可能性があります。明確な契約書の提示と双方合意の取引は、後に起こりうるトラブルを未然に防げる点でもメリットです。
2. 一方的かつ不当な行為をしない
フリーランス新法は、企業による一方的かつ不当な行為を禁止しています。たとえば6ヶ月以上続く業務委託契約を解除する場合、原則30⽇前までに解約の旨をフリーランスに報告しなければいけません。
さらに予告の⽇から解除⽇までに、フリーランスから解除理由の開⽰請求があった場合、企業(発注側)は解除理由を伝える必要があります。また新法では、次のような⾏為を禁止しています。
禁止行為 | 概要 |
一方的な契約解除や変更 |
|
不当な買い叩き・返品 |
|
不当な給付内容の変更・やり直し |
|
出典: G-Gov法令検索_特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律_第五条
契約内容を変更する必要が生じた場合は、必ず事前にフリーランスと協議し、双方合意の上で進めていきましょう。
▼関連記事:業務委託の契約解除に損害賠償や違約金は必要?書面や解除のポイントとおすすめエージェント11選
3. 適正に報酬を支払う
フリーランス新法では、企業はフリーランスに対し、期日までの報酬の支払いが義務付けられています。フリーランスへの報酬支払期日は、原則「物品等の受領日から60日以内」となっているため、報酬の支払いを先延ばししないようにしましょう。
また、発注者が元請けから業務を再委託する場合、一定の条件を満たせば30日より短い期間で支払期日を設定できる「再委託の例外」も存在します。いずれにしても支払いが遅れる場合は、フリーランスに遅延理由を伝えておきましょう。
報酬額は、業務内容や市場価格を考慮しつつ、可能な限り双方が納得のいく金額に設定します。相場よりも低い報酬は、フリーランスのモチベーション低下にも繋がるため注意が必要です。期日内での支払いを遵守し、外部人材と良好なパートナーシップを築いていきましょう。
4. 就業環境に配慮する
新法ではフリーランスが安心して業務を遂行できるよう、企業に就業環境への配慮を求めています。たとえばハラスメント対策として、ハラスメント防止研修の実施(従業員向け)や、相談窓口を設置するよう呼びかけています。
またフリーランスが育児・介護と仕事が両立できるよう、企業側はできる限り配慮しましょう。具体的には、妊婦健診日の打ち合わせ時間調整や、オンライン業務への移行などが考えられます。フリーランスの能力が最大限に発揮できるよう、企業は働く環境を積極的に整備していきましょう。
5. 募集情報を正しく表示する
WebサイトやSNSにフリーランス・業務委託の募集情報を掲載する場合、企業は虚偽または誤解を招くような表示をしてはいけません。業務内容や報酬、契約期間など、正確に記載する必要があります。
不正確な情報を載せた場合、フリーランスとの間でトラブルが生じるだけでなく、法律違反に該当します。募集を出す際は、正確かつ最新情報を提供するよう心がけましょう。
フリーランス新法を違反した場合の罰則
フリーランス新法に違反した場合、企業は法的責任を問われる可能性があります。違反行為の内容によっては、公正取引委員会による指導や勧告、さらには罰金が科されるかもしれません。
たとえば「契約内容を明確に書面で交付しなかった」「一方的な契約解除を行った」という場合、行政指導が入ることがあります。助言や勧告に従わなければ罰金の対象となり、場合によっては企業名が公表されます。そのため「対応に問題ないか」「書類に不備がないか」など、社員全員と早期に確認しておきましょう。
フリーランス新法を企業が遵守するメリット
フリーランス新法を遵守すると、企業はさまざまなメリットを享受できます。
フリーランスとの信頼関係が強化する
フリーランス新法では、報酬の支払い期限や業務内容の明確化などが義務付けられています。「納品から60日以内に報酬を支払う」「支払いは翌月の月末締め日」など、取り決めを文書で交わしておくとフリーランスも安心して働けます。
また、丁寧なやり取りや契約の遂行は、フリーランスが「またこの企業と仕事したい」と思うポイントの一つです。企業が法律を遵守すると、外部人材と良好な関係を維持したまま業務を進められます。
取引トラブルを防止できる
フリーランス新法に従うと、企業は取引におけるトラブルを未然に回避できます。たとえばWeb制作をフリーランスに依頼する場合、制作範囲や納期などを書面で事前に共有します。
委託内容の明示は、「言った・言わない」といった認識のズレを防ぎ、契約や取引の問題を防止する上で有効です。
企業の社会的信用が高まる
「法令遵守に積極的」かつ「フリーランス人材にも誠実に対応する」企業は、就職希望者や取引先からの信頼が厚くなります。逆に、違法な取引や報酬の遅延などが明るみに出ると、ネットやSNSなどを通じて悪評が広がるかもしれません。
たとえば「報酬未払いでフリーランスが泣き寝入り」といった投稿が拡散されれば、採用活動や新規顧客獲得にも悪影響です。「コンプライアンス意識の高い企業」として認知されるためにも、新法を遵守しましょう。
フリーランス新法に対応する4つのステップ
ここでは、フリーランス新法に対応する4つのステップを紹介します。
ステップ1. フリーランスとの取引実態を把握する
まず最初に、「現在フリーランスとどのような取引をしているか」を把握しましょう。たとえば、業務委託契約の「請負(成果物納品)」もしくは「委任・準委任契約(作業・業務の遂行)」のどれに該当するか確認しておきます。
もし業務委託と言いつつ、実態が「労働者」の働き方(勤務時間の拘束、常駐勤務など)であれば、労働基準法の問題にもなり得ます。具体的には、準委任契約のような時間単位の契約で勤務時間や作業内容を細かく管理する場合、偽装請負とみなされるリスクもあるため注意が必要です。
出典:厚生労働省_フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
▼関連記事:業務委託と請負は違う?請負と委任契約の違いやメリット、注意点を解説
▼関連記事:業務委託の人材にも労働基準法が適用される?契約のリスクや請負との違いを徹底解説
ステップ2. 契約書・発注書の見直しと新ルールを策定する
次に、契約書や発注書の内容を見直していきましょう。フリーランス新法では、以下のような記載事項が義務化されています。
- 報酬額と支払期限
- 納品日と業務内容
- 業務委託をした日 など
たとえば「納品後60日以内に報酬を支払う」といったルールが明記されていない場合、トラブルの原因になる可能性があります。契約書や発注書のテンプレートを見直し、法律に準拠した記載に改めましょう。
ステップ3. 社内体制を整備する
次に、社内でフリーランス新法に対応する体制を構築しておきます。たとえば「法務部門や人事部門がフリーランスとの契約チェックを担当する」「取引開始前に確認すべきチェックリストを作成する」といった対応が考えられます。
また複数部署でフリーランスと仕事している場合は、情報の一元管理も必要です。「どの部署が誰と契約しているのか」を把握できるよう、ワークフローシステムや、ビジネスチャットを活用していきます。社内全体で共通認識を持たせるためにも、必要に応じて勉強会や研修を実施しましょう。
ステップ4. 定期的に法改正をチェックする
フリーランス新法は新しい法律であり、今後も細かいガイドラインの変更や改正が行われる可能性があります。「毎月1回、法改正情報をチェックして社内に共有する」といったルールを定めておくと対応が継続しやすいです。
厚生労働省の公式サイトや業界団体からの通知を定期的に確認し、必要に応じて社内の対応フローを更新していきましょう。
フリーランス新法に関する相談窓口
ここでは、フリーランス新法を相談できる窓口について紹介します。
厚生労働省
厚生労働省では、フリーランス新法を含む、あらゆる労働に関する幅広い法律や事例を取り扱っている行政機関です。法律の解釈や制度に関する一般的な問い合わせに対応し、企業担当者からの相談も受け付けています。
たとえば、「自社の業務委託がフリーランス新法の対象なのか知りたい」「契約書に記載すべき事項を確認したい」など、業務委託に関する疑問・不明点についてアドバイスしてもらえます。
▼参考リンク:厚生労働省
労働基準監督署
労働基準監督署は厚生労働省の出先機関であり、企業が労働関連法規を遵守しているかを監視しています。
フリーランス新法に関する相談も受け付けており、「これはフリーランスへのハラスメント行為に該当するのか」「これは一方的な契約解除なのか」など、相談できます。もしフリーランスとの間でトラブルが発生し、法的な判断が必要となる場合、労働基準監督署に相談してみましょう。
「自社が所在する都道府県の労働基準監督署がどこにあるのか知りたい」という場合、以下添付のリンクから探してみてください。
▼参考リンク:厚生労働省_全国労働基準監督署の所在案内
中小企業庁の相談窓口
中小企業庁では、フリーランス新法に関する相談窓口を設けています。
特に中小企業がフリーランスを活用する上での注意点や、具体的な対応策についてのアドバイスを受けられます。「フリーランスに業務を委託したいが何から始めるべきか分からない」「契約書の作成について具体的なサポートを受けたい」といった場合、頼りになるでしょう。
▼参考リンク:中小企業庁
弁護士や専門家
フリーランス新法についてのより詳細で専門的なアドバイスを求める場合、労働法や契約法に詳しい弁護士に相談するのも一つの方法です。
契約書の作成・確認、訴訟リスクの評価、具体的なトラブル解決など、個別の状況に応じたきめ細やかなサポートが期待できます。費用はかかりますが、法的リスクを最小限に抑え、安心して事業を進めるためには専門家の知見も検討すべきです。弁護士を探したい方は、以下のリンクから探してみてください。
▼参考リンク:日本弁護士連合会
自治体や商工会議所の相談窓口
一部の自治体や商工会議所でも、企業向けの経営相談窓口を設けており、フリーランス新法に関する情報提供や相談を受け付けている場合があります。地域に根ざした情報や、地元の企業事例など、わかるかもしれません。
お近くの自治体や商工会議所のWebサイトを確認してみましょう。
フリーランスへの業務委託をスムーズにしたい企業には、登録無料の『Workship』がおすすめ!
フリーランス新法により、企業はこれまで以上に適正な取引と就業環境の整備が求められるようになりました。新法に備えるためにも、契約・取引条件の明確化や、募集情報の提示など、早急な対応が必要です。
「法令に沿った業務委託をしたい」「即戦力人材に仕事をすぐに依頼したい」という企業におすすめなのが、登録無料のフリーランス専門エージェント『Workship』です。
『Workship』では、厳選されたスキルの高いフリーランスをご紹介し、契約や取引に関するサポートも代行いたします。法令対応と人材確保を同時に進めたい企業に最適なサービスです。Workshipの特徴を、以下で簡単にお伝えします。
アカウント登録が無料!
Workshipはアカウント登録無料で、次のさまざまな機能をご利用いただけます。
- ニーズに合わせたマッチ度の高い候補者を随時提案
- スカウト機能
- フリーランス検索
- 求人掲載は無制限
- 無制限のメッセージ機能で候補者と直接交渉が可能
- オンライン面談
- 求人作成代行
- オンラインサポート
- 印紙代不要の電子契約
- 正社員転換契約
- 賠償責任保険が自動で適用
- 稼働管理
※自動で費用が発生することはありません。
※料金はユーザーとの成約が完了した時点で発生します。
また、ご利用いただく中でお困りのことがあれば、随時丁寧にサポートいたします。
三者間契約でインボイス制度の不安がない
フリーランスを活用する上で、採用担当者様の工数負担が大きいのが、契約書の取り交わしです。Workshipでは成約時に企業 ⇄ Workship ⇄ フリーランスの三者間契約を締結し、その契約手続きを代行します。クライアント企業となるお客様の契約先はWorkshipとの契約となるため、フリーランス活用でネックとなるインボイス制度への対応も問題ありません。また、毎月の請求処理も代行いたします。
Workshipで稼働と進捗管理も安心
成約後のフリーランスの稼働管理も、Workshipの管理画面でできます。管理画面ページを閲覧するだけで、稼働時間や業務の進捗などの定期チェックもしやすくなります。
Workshipでは、外部のフリーランスを活用し始めるまでは月額費用がかかりません。そのため、自社にマッチする人材をじっくりと見定められます。また、成約後であっても14日間は返金保証があり、ミスマッチを起こす可能性が低いです。
▼以下では、Workshipのサービス資料を無料でダウンロードできます。

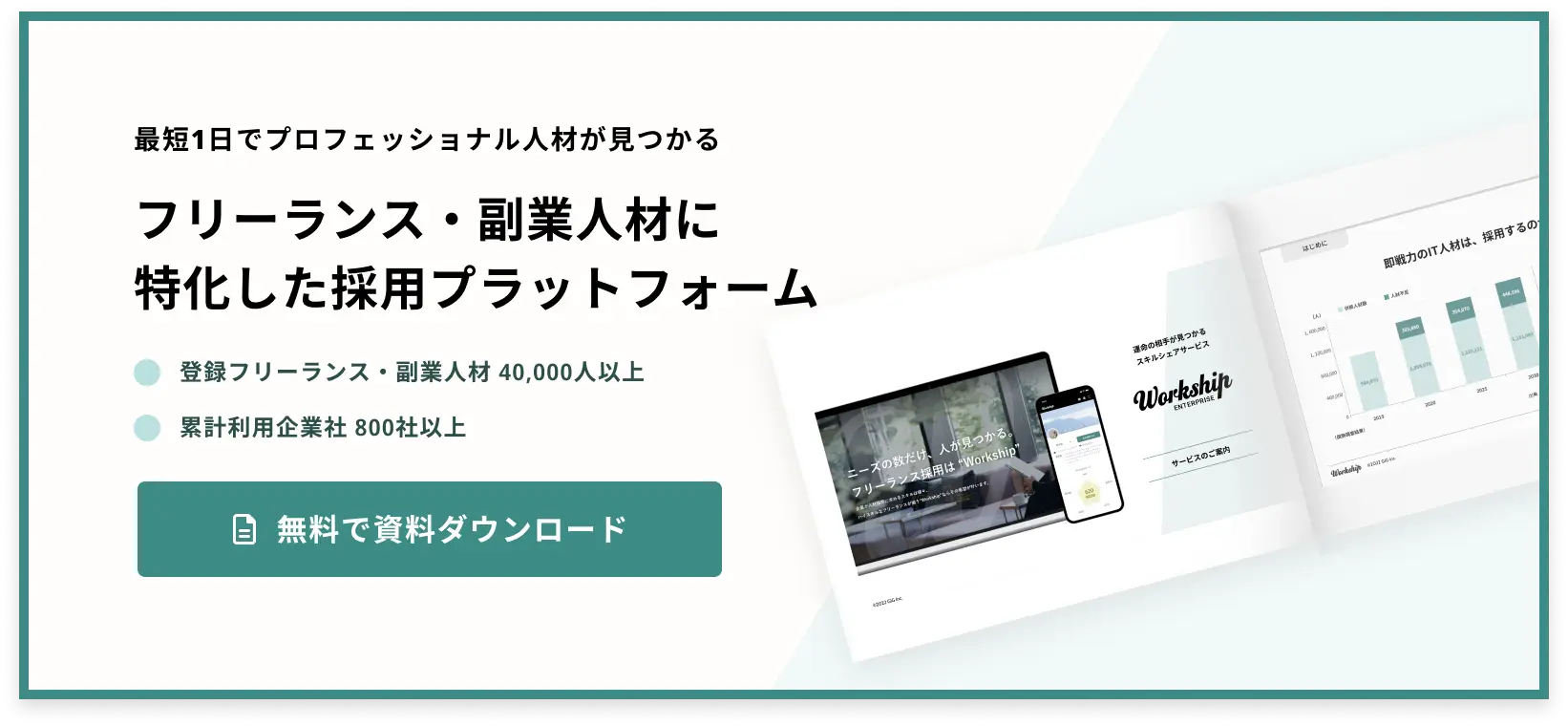 無料アカウント登録
無料アカウント登録