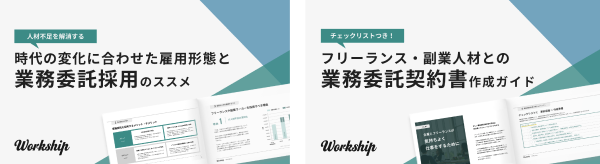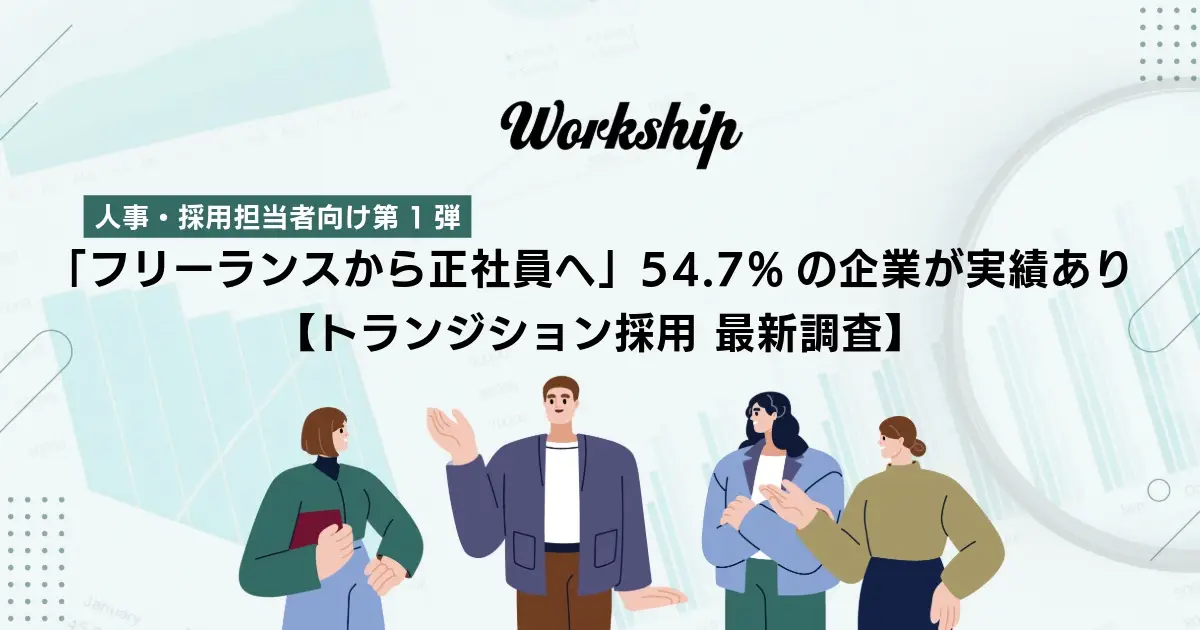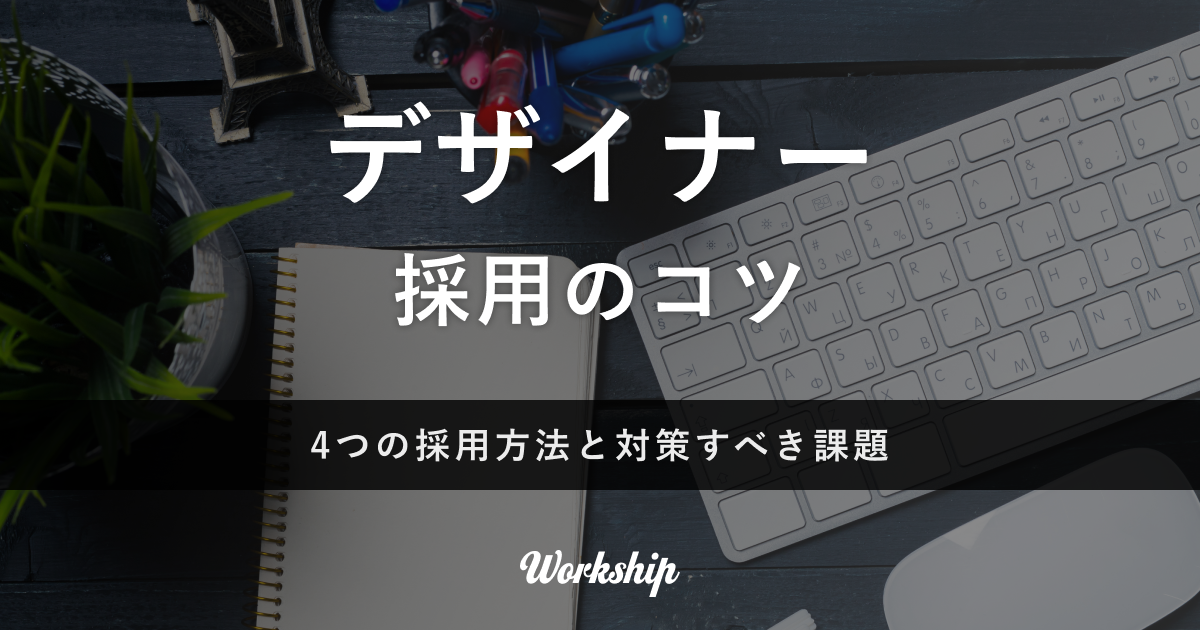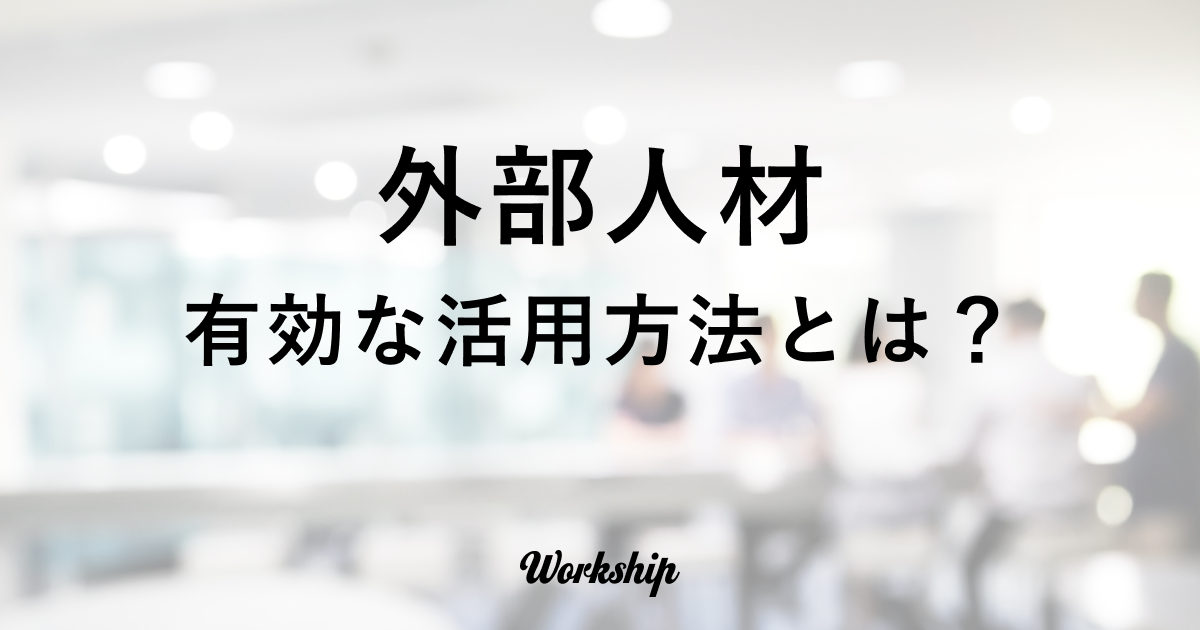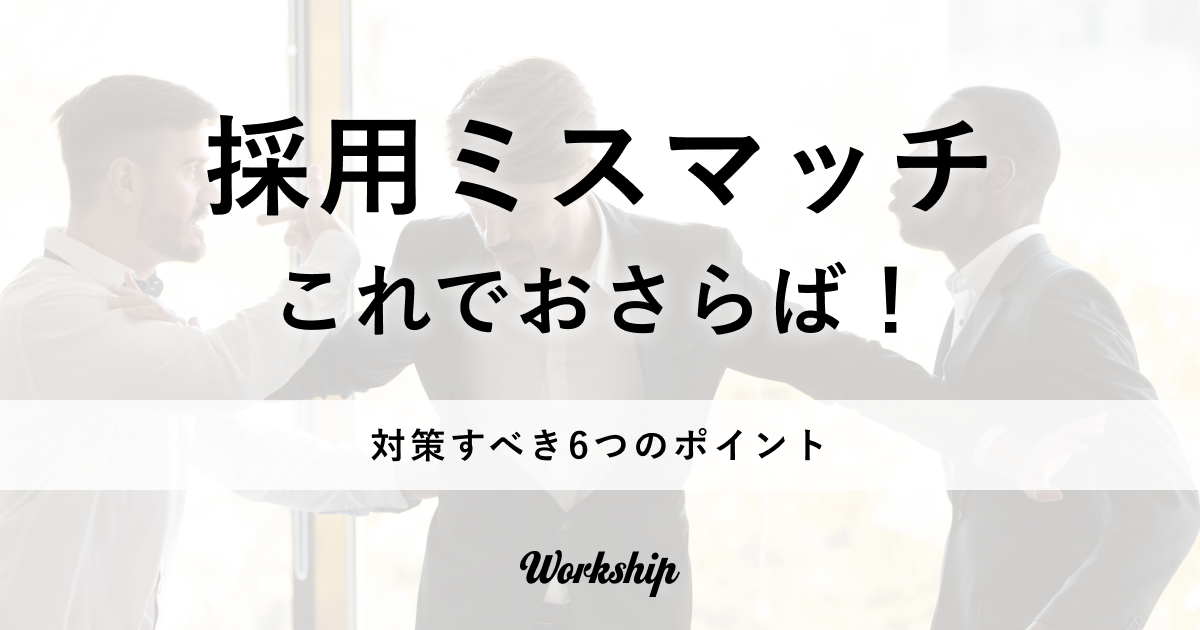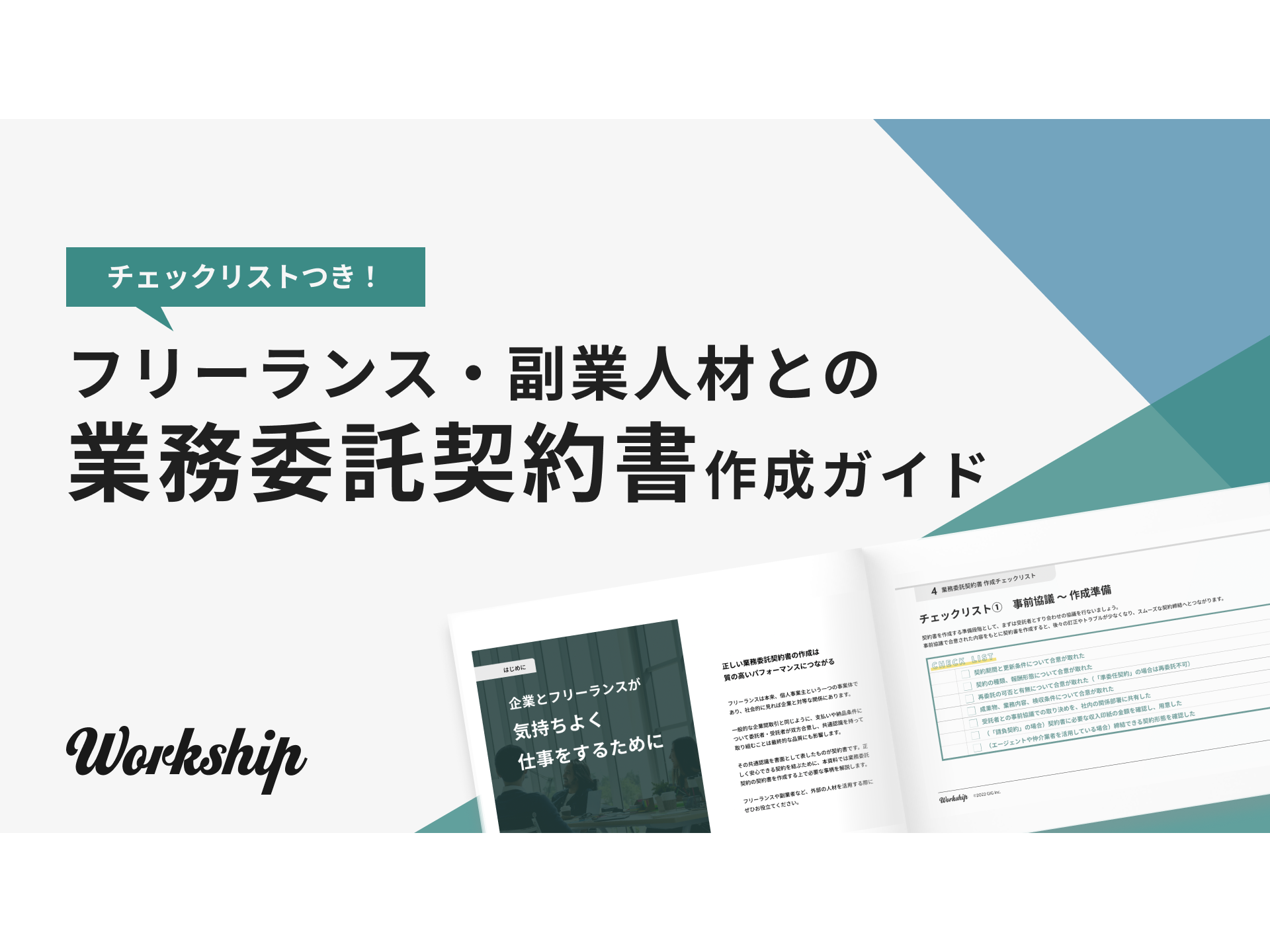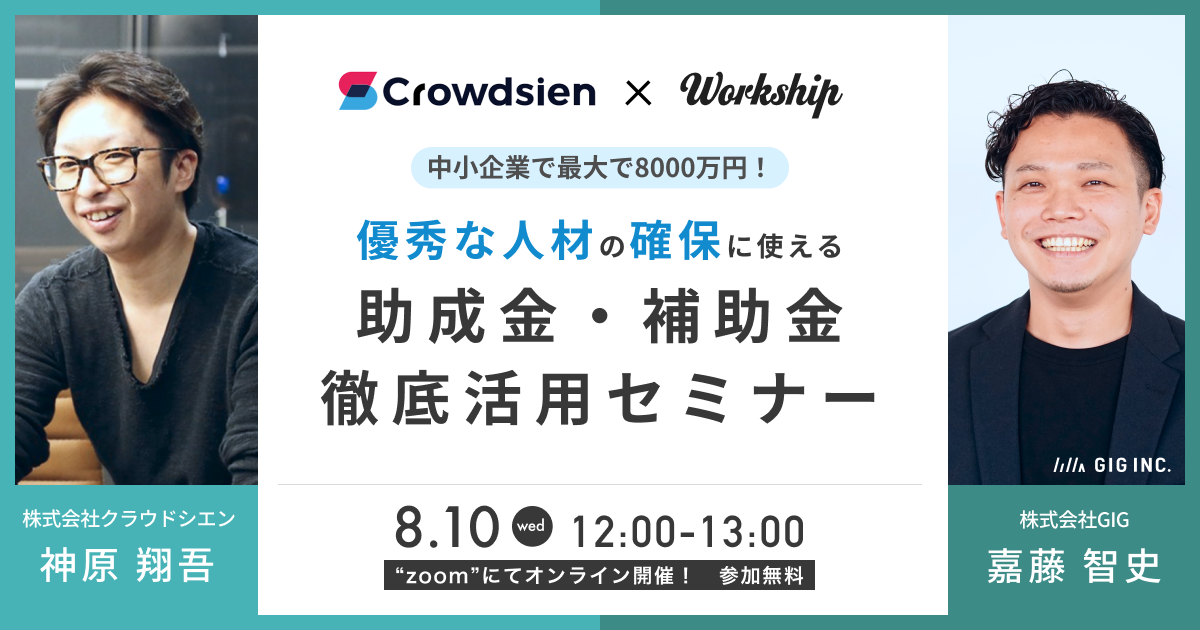フリーランスは増えすぎているのに採用が難しい?企業担当者が知るべき現実と対策
「フリーランスは年々増えているのに、なぜ採用がこんなに難しいのか」
そんな疑問を感じている企業担当者の方も多いのではないでしょうか。
確かに、フリーランス市場は拡大し、フリーランスとして活躍する人材も増えています。
しかし、実際の採用現場では「スキルの差が激しい」「信頼できる人材が見つからない」といった声が後を絶ちません。
本記事では、フリーランス採用が難しく感じられる構造的な理由を整理し、実際に信頼できる人材と出会うためのポイントをわかりやすく解説します。
フリーランスの実際の市場規模や優秀なフリーランスの見極め方を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
「フリーランスは増えすぎ」は本当?
「フリーランスは増えすぎたから、もう稼げないのでは?」などの声を聞き、独立を前に不安を感じている方もいるかもしれません。結論から言うと、フリーランスの人口が増えているのは事実です。
しかし、大切なのは数字の表面だけを見て諦めることではありません。
どのような立場の人が増えているのか、その内訳を正しく理解すれば、いたずらに不安を感じる必要がないこともわかります。
ここでは、公的なデータを基に以下の3つのポイントから「増えすぎ」の真相を解説します。
フリーランス人口の推移
本業フリーランスは209万人
副業フリーランスが急増
まずは、フリーランス全体の人口がどのように変化しているのか、具体的なデータから確認していきましょう。
フリーランス人口の推移
フリーランスとして働く人の数は、公的なデータを見ると増加傾向にあることがわかります。
実際に、総務省が実施した「令和4年就業構造基本調査」では、フリーランスに該当する人の数が具体的に示されています。
この調査ではフリーランスを「実店舗がなく、雇人もいない自営業主又は一人社長」と定義しており、その総数は2022年時点で257万人以上です。
フリーランスの働き方 | 2022年(令和4年)の人数 |
本業がフリーランス | 209万人 |
副業がフリーランス | 48万人 |
合計 | 257万人 |
257万人という数字は、日本の有業者総数6,706万人のおよそ3.8%にあたります。
確かにフリーランス人口は増えていますが、割合で見ると、まだ市場全体が飽和しているとまでは言い切れない状況です。
まずは客観的な数字として、日本には250万人を超えるフリーランスがいる事実を把握しておきましょう。
フリーランスの主な職業
フリーランスと一言でいっても、その職業は多岐にわたります。
「フリーランス」は特定の職種を指す言葉ではなく、あくまで企業に属さない働き方の一つだからです。
実際にどのような職業の人がフリーランスとして活躍しているのか、フリーランス協会の調査を見てみましょう。
2025年版の「フリーランス白書」によると、フリーランスの主な職種は以下のようになっています。
グラフを見ると、クリエイターやWeb系、出版・メディア系、エンジニア・技術開発系(13.2%)など、多様な専門職がフリーランスとして活躍していることがわかります。
「フリーランス」の大きな括りで「増えすぎ」と考えるのではなく、自分が目指す「職業」の需要を見極めることが大切です。
副業フリーランスが急増
「フリーランスが増えすぎ」と感じる理由の一つに、副業として活動する人の急増が挙げられます。
本業の傍ら、すきま時間を使ってフリーランスとして働く人が増えたことで、市場に参加する人の総数が多くなっているのです。
実際に総務省の調査では、「副業がある者」の数が2017年の245万人から2022年には305万人へと、5年間で60万人も増加したことが報告されています。
引用:副業がある者の数(非農林業従事者)の推移(2007年~2022年)-全国|総務省
「副業ブーム」はフリーランス市場も例外ではありません。先に見たように、フリーランス全体の約5人に1人にあたる48万人は、副業として活動しています。
「フリーランスが増えすぎ」などの印象は、こうした副業層の参入が大きく影響していると考えられます。
フリーランスは増えすぎといわれる背景
では、なぜこれほどフリーランスの働き方が注目され、増加しているのでしょうか。
その背景には、個人の価値観の変化だけではなく、社会全体の変化が関係しています。ここ数年で私たちの働き方を一変させた、いくつかの要因が重なり合った結果です。
ここでは、フリーランスが増えている理由を、以下の3つの社会的な背景から解説します。
リモートワークの普及による働き方の多様化
副業解禁による副業者増加
ITフリーランスの需要の高まり
これらの変化を理解すれば、フリーランス市場の今後の動向も見えてくるでしょう。
リモートワークの普及による働き方の多様化
フリーランスが増えた大きな要因として、リモートワークの普及が挙げられます。
なぜなら、働く場所の制約がなくなったことで、個人の時間活用やキャリアに対する考え方が大きく変化したからです。
会社に出社しなくても仕事が進められる経験は「会社に所属する」というこれまでの当たり前を見直すきっかけとなりました。
実際に、総務省の調査によると、2022年には有業者のうち19.1%にあたる1,265万人がテレワークを経験しています。
リモートワークの普及は、フリーランスの働き方に対して、以下のような影響を与えました。
通勤時間の削減による可処分時間の増加
居住地の自由化
企業の外部人材活用の促進
リモートワークの定着は、個人がフリーランスを目指しやすく、企業がフリーランスに仕事を依頼しやすい環境を整えました。社会的な変化が、フリーランス増加の背景の一つにつながっています。
副業解禁による副業者増加
大手企業を中心に副業を解禁する社会的な流れも、フリーランス人口の増加を後押ししています。
この背景には、かつての雇用モデルであった終身雇用制度の崩壊が大きく関係しています。一つの会社に勤め上げれば安泰という時代が終わり、企業側も個人のキャリアを最後まで保障できなくなりつつあります。
そのため、企業は従業員が社外でスキルを磨き、自律的にキャリアを築くことを容認・推奨するようになり「副業解禁」する企業が増加しました。
この変化は、個人にとっても「会社だけに依存しない働き方」を模索するきっかけとなりました。
具体的には、以下のような方向性を検討する人が増えました。
キャリアの自衛
スキルアップ機会の確保
収入源の複線化
企業と個人の双方の意識が変化したことで副業が一般化し、フリーランスの働き方がより身近な選択肢となっています。
ITフリーランスの需要の高まり
IT分野におけるフリーランスの需要が急速に高まっていることも、フリーランスが増えてる要因の一つです。
企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進が加速する一方で、それを担う専門的なIT人材が社会的に不足しています。そのため、即戦力となる外部のプロフェッショナルを求める企業が増えているのが現状です。
特に、以下のような要因がITフリーランスの需要を後押ししています。
DXやAI化の加速
高速インターネット環境の整備
ITスキルを持つ人材の不足
上記のような背景から、高いスキルを持つITフリーランスは、他の職種に比べて高単価で安定した案件を獲得しやすい状況が生まれています。
フリーランスが増えても「採用が楽にならない」3つの理由
フリーランスの数が増えても、企業にとって採用が楽になるとは限りません。
確かに、働き方の多様化や副業解禁により、個人で働く人材の選択肢は広がりました。
しかし、実際には「なかなか良い人に出会えない」「お願いしたい人ほど忙しい」といった声が後を絶ちません。
その背景には、フリーランス市場特有の課題が存在します。
主な理由は以下の3点です。
どこに良い人材がいるか分かりにくい
スキルの高い人ほどすでに仕事が埋まっている
スキルや経験に差がある
ここからは、それぞれの理由を詳しく見ていきましょう。
どこに良い人材がいるか分かりにくい
どこに優秀なフリーランス人材がいるのか分かりにくい点が、採用の難しさを生んでいます。
フリーランスの人数は増えていますが、企業側からはその所在や稼働状況が見えにくく、人材発掘に時間と労力がかかります。
なぜなら、フリーランスが活動する場所や情報の出し方がバラバラで、採用側が比較・判断しづらいからです。
正社員採用のように、求人情報が集約されているわけではありません。
特に企業が苦労するポイントは以下のとおりです。
活動場所が分散している
稼働状況が公開されていない
紹介や非公開案件で動いている
フリーランスの場合は、情報が可視化されていない場合も多く、企業が主体的に探しにいかなければ人材と出会えません。
「フリーランスは多いはずなのに、誰に声をかけたらいいか分からない」などの状況が、採用の難易度を上げていると言えるでしょう。
スキルの高い人ほどすでに仕事が埋まっている
スキルの高いフリーランス人材ほど、すでに他の案件で稼働が埋まっており、採用できる機会が限られます。
企業側が「この人にお願いしたい」と思っても、すぐに依頼できるとは限りません。
このような状況が起きる背景には、実力のあるフリーランスが既存クライアントとの継続案件に多く関わっていることが挙げられます。
スキルの高い人材ほど報酬や業務内容に対する希望も明確で、条件が合わない場合には受注につながらないこともあります。
企業側が直面しやすい具体的な課題は以下のとおりです。
- 実績のある人材は他社と契約継続中
- 条件交渉で折り合いがつきにくい
- 空いている人材=優秀とは限らない
優秀な人材ほど早期に案件が決まり、依頼できるタイミングが限られてしまいます。
フリーランスの総数が増えていても、すぐに依頼できる人材が限られている点が、採用活動を難しくする要因の一つです。
スキルや経験に差がある
フリーランスが増加する一方で、そのスキルや経験には大きな差があり、採用における見極めが難しくなっています。
「仕事を任せてみたら、思ったより経験が浅かった」といったトラブルは、フリーランス採用の現場でたびたび耳にする課題です。
背景には、近年のフリーランス人口の急増があります。
総務省の「令和4年就業構造基本調査」では、2022年時点のフリーランス該当者が257万人に達しており、そのうち副業フリーランスが48万人です。
副業者全体の数も2017年から2022年にかけて60万人増えており、フリーランス市場が広がっていることが分かります。
本業としてキャリアを築いてきた人と、近年スキル習得中の副業層が混在している状況では、どうしても能力のばらつきが生まれやすくなります。
見極めが難しい点は以下のとおりです。
実績の厚みや業界経験の差
副業か本業かのコミットメントの違い
表面上のポートフォリオでは判断困難
フリーランス人口の増加はチャンスを広げる一方で、企業にとっては「誰を選ぶか」の負荷を高める要因にもなっています。
そのため、スキルの差を前提とした評価基準の整備が必要といえるでしょう。
優秀なフリーランスを見極める4つのポイント
フリーランスを採用する際に重要なのは、数の多さではなく「誰に依頼するか」の見極めです。
スキルや経験にばらつきがあるからこそ、表面的な印象や価格だけで判断すると、期待外れの結果につながりかねません。
信頼できるフリーランスを選ぶためには、採用前のチェック項目を明確にしておく必要があります。
特に確認しておきたいのは以下の4点です。
ポートフォリオを確認する
実務スキルを試す
事業への理解度を測る
ビジネスリテラシーを確かめる
4つのポイントを押さえることで、スキルだけではなく姿勢や適性も含めて評価しやすくなります。
ここでは、それぞれのポイントを確認していきましょう。
ポートフォリオを確認する
フリーランスを見極めるうえで最初に確認すべきなのが、過去の実績がまとまったポートフォリオです。
どのような仕事をしてきたのか、どの分野を得意としているのかが一目で分かるため、スキルの水準や適性を把握しやすくなります。
経歴やスキルの説明だけでは具体的な力量を判断しやすくなるでしょう。
実際に作成された成果物を見ることで、「説明と実力に乖離がないか」「自社が求めるアウトプットに近いか」といった視点で評価できます。
案件ごとにどのような役割を担っていたかが記載されていれば、対応範囲や実務経験の深さも把握できます。
確認時に注目したいポイントは以下のとおりです。
自社業務に近い制作実績があるか
作業範囲や担当工程が明記されているか
クオリティに一貫性があるか
ポートフォリオはスキルの裏付けを得るための判断材料となります。
形式だけ整っていて中身が薄いケースもあるため、見せ方だけではなく中身の実績もしっかり確認しましょう。
実務スキルを試す
フリーランスを見極める際は、ポートフォリオだけで判断せず、実務を通してもスキルを確認しましょう。
完成された成果物を見るだけでは、実力の再現性や業務対応力までは読み取れないからです。
ポートフォリオは他者からのフィードバックを何度も受けて仕上げられているケースもあり、完成度の高さが本人の地力をそのまま反映しているとは限りません。
一方で、実務タスクを通じてやりとりの反応速度や理解力、改善力などを観察すれば、ポートフォリオには出ない実力や仕事の姿勢まで見えてきます。
確認する際のポイントは以下のとおりです。
小さなテスト業務を用意する
納期や指示対応の柔軟性を見る
修正指示への反応も含めて評価する
実務の中で相手のスキルを観察すれば、成果物だけでは見えない仕事力を判断できます。
見た目の完成度だけに頼らず、リアルなやり取りを通じて実力を見極められるように意識しましょう。
事業への理解度を測る
優秀なフリーランスを見極めるには、自社の事業やサービスへの理解度を確認しましょう。
スキルが高くても、事業の目的や背景を理解していなければ、成果物の方向性がずれる恐れがあるからです。
長期的な関係を築くうえでは「依頼されたタスクをこなす人」ではなく、「目的に沿って提案できる人材」が求められます。
そのため、応募時や面談時に自社のサイトやサービス内容に触れているか、過去の案件とどう結びつけて考えているかを確認する必要があります。
チェックすべきポイントは以下のとおりです。
事前に企業サイトを把握しているか
自社の課題に対する関心があるか
過去実績との関連性を言語化できているか
業務内容だけではなく事業背景まで意識できる人材は、単発依頼でも軸がぶれにくく、信頼性の高いパートナーになり得ます。
依頼前に理解度を測ることで、成果物の質だけでなく進行のスムーズさにもつながります。
ビジネスリテラシーを確かめる
フリーランスのスキルを評価する際には、ビジネスリテラシーが備わっているかどうかも確認すべき要素です。
高いスキルがあっても、納期や報連相に対する意識が低ければ、業務が円滑に進まなくなります。
業務委託という関係性では、相手の働き方にある程度任せる場面も多くなります。
そのため、最低限のビジネスマナーや仕事に対する責任感が備わっていないと、進行遅延や認識ズレといったトラブルが起きやすくなります。
確認するポイントは、主に以下の3つです。
メールやチャットの文面に違和感がないか
期日や納期の管理に意識が向いているか
進行状況を適切に共有できているか
ビジネスリテラシーは表に出にくいものですが、長く付き合えるかどうかを判断するうえで極めて重要です。
スキルだけで判断せず、やり取りの端々から相手の「仕事観」にも目を向ける視点を持ちましょう。
優秀なフリーランスと出会うための採用チャネル
どれだけ見極めの目を養っても、そもそも良いフリーランスに出会えなければ採用は進みません。
信頼できる人材を確保するには「どこで探すか」「どのチャネルを使うか」などの入口の設計が大切です。
フリーランスは正社員採用のように媒体に集約されておらず、それぞれ異なる場所で活動しています。
そのため、採用側が複数の手段を使い分けながら、相性の良い人材と出会う努力が求められます。
代表的なチャネルは以下の3つです。
リファラル採用(社員からの紹介)
SNSでのスカウト
フリーランス専門のマッチングサービス
それぞれの採用方法の特徴やポイントを確認していきましょう。
リファラル採用(社員からの紹介)
フリーランス採用で信頼性が高い採用方法のひとつがリファラル採用です。
社員や関係者の紹介を通じて人材とつながるため、スキルや人柄の事前情報を得やすくなるからです。
特に紹介元が一緒に働いた経験を持っている場合は、履歴書やポートフォリオではわからない「実際の仕事ぶり」まで把握できます。
採用側としても最初から信頼関係を築きやすく、ミスマッチのリスクを抑えられます。
リファラル採用以下のようなポイントに意識しましょう。
社内で「紹介歓迎」の空気をつくる
条件や求めるスキルを事前に共有する
紹介者にヒアリングして補足情報を得る
リファラルは採用の確度を高める手段ですが、制度化しすぎると紹介が出にくくなることもあります。
「信頼して紹介できる相手だけに声をかける」などの自然な形が、継続的な紹介を生みやすいポイントです。
SNSでのスカウト
フリーランスとつながる手段として、SNSを活用したスカウトも有効な方法の一つです。
X(旧Twitter)やInstagramなどでは、日頃の発信からスキルや思考、得意領域を読み取ることができます。
SNSには、ポートフォリオや実績では見えない「人となり」や「対応スタンス」が現れます。
継続的に発信している人材は、自らの仕事に自信と責任を持って取り組んでいる可能性が高く、実際のやり取りの印象もつかみやすくなるでしょう。
スカウトに活用する際のポイントは以下のとおりです。
投稿内容からスキル傾向を読み取る
コミュニケーションの姿勢を確認する
丁寧な文面でスカウトメッセージを送る
SNSは検索性と相手の人物像が見える点が大きな魅力です。
ただし、投稿頻度や内容が表面的な場合もあるため、過度な判断は避け、会話や実務を通じて丁寧に確認する姿勢が求められます。
フリーランス専門のマッチングサービス
フリーランスと効率的に出会いたい場合、マッチングサービスを活用するのもおすすめです。
専用プラットフォームには、一定のスキルや実績を持った人材が登録しており、比較的スムーズに候補者を探せるからです。
フリーランスの専門マッチングサービスには、登録者を審査する厳格型と、自由に応募できるオープン型があります。
案件のジャンルや報酬条件などを細かく設定できるため、希望に合った人材と出会える可能性が高まります。
フリーランスの専門サービスの種類は以下のとおりです。
案件単位での紹介型サービス
プロフィール公開型のスカウト型サービス
法人向けに担当者がマッチング支援するタイプ
ただし、利用の際には「価格だけで選ばない」「契約形態を確認する」といった基本を押さえておく必要があります。
サービスの特徴や掲載基準をよく確認し、自社に合ったチャネルを選びましょう。
優秀なフリーランス人材の確保なら『Workship』がおすすめ
即戦力となるプロフェッショナル人材の採用を成功させたいなら、Workshipでの人材確保をおすすめします。
なぜなら、Workshipは、一般的な求人サイトとは異なり、優秀な人材が「自ら集まり、安心して活躍できる」独自の仕組みを構築しているからです。
Workshipには、以下のような強みを持った人材が多数在籍しています。
優良企業の案件に挑戦する向上心
大手・成長企業での豊富な実務経験
営業活動よりも専門業務への集中を望むプロ意識
スキルセットが明確で高精度なマッチングが可能な信頼性
契約・請求の効率化を求めるビジネス感覚
インボイス制度にも対応したコンプライアンス意識
採用活動を「作業」から「戦略」へと変革し、事業成長を共に実現するパートナーと出会うためにも、ぜひWorkshipの力をご活用ください。
▼Workshipのサービス内容や登録されている案件の具体例を、まずは無料で確認してみませんか?独立後の働き方をイメージするために資料を確認してください。
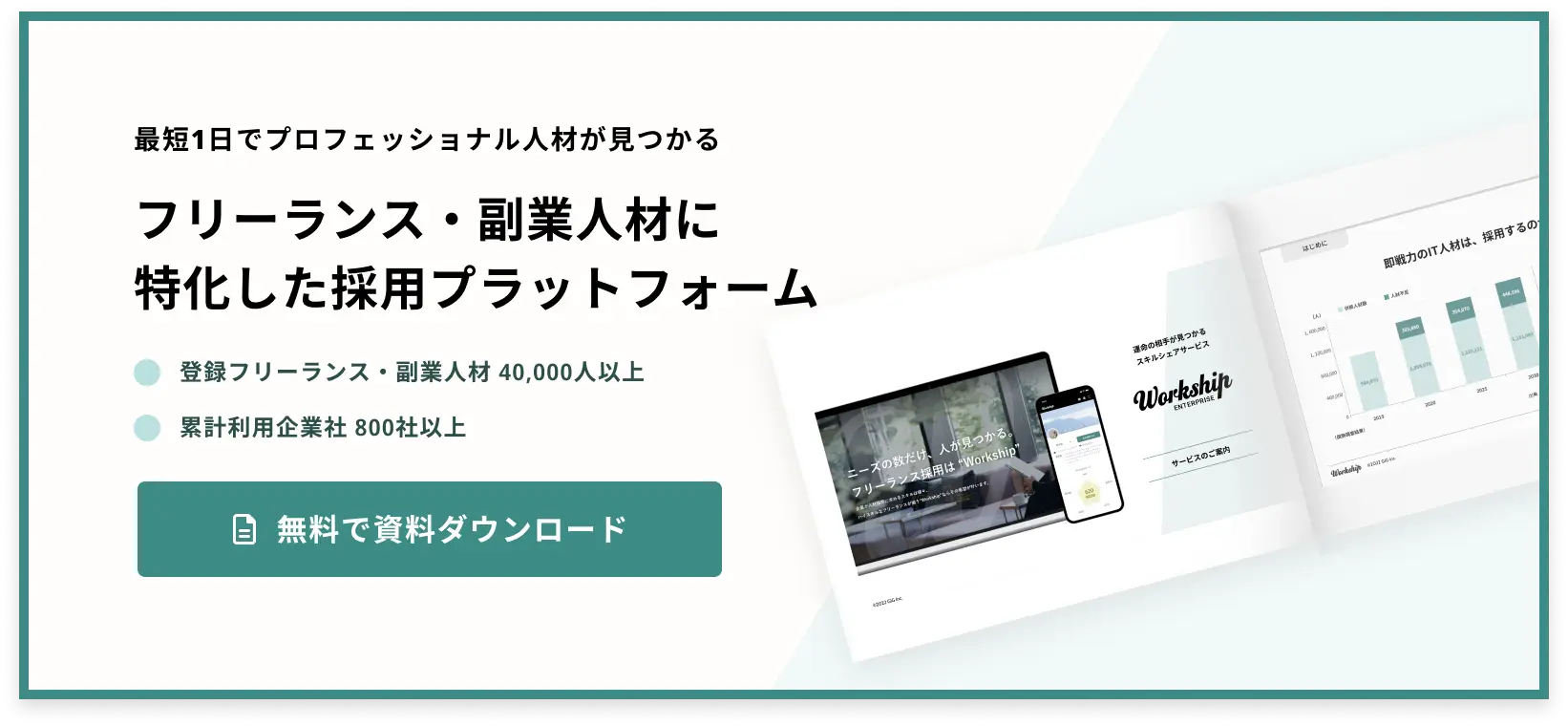 無料アカウント登録
無料アカウント登録