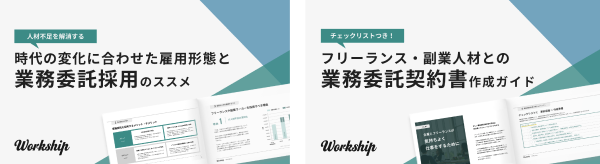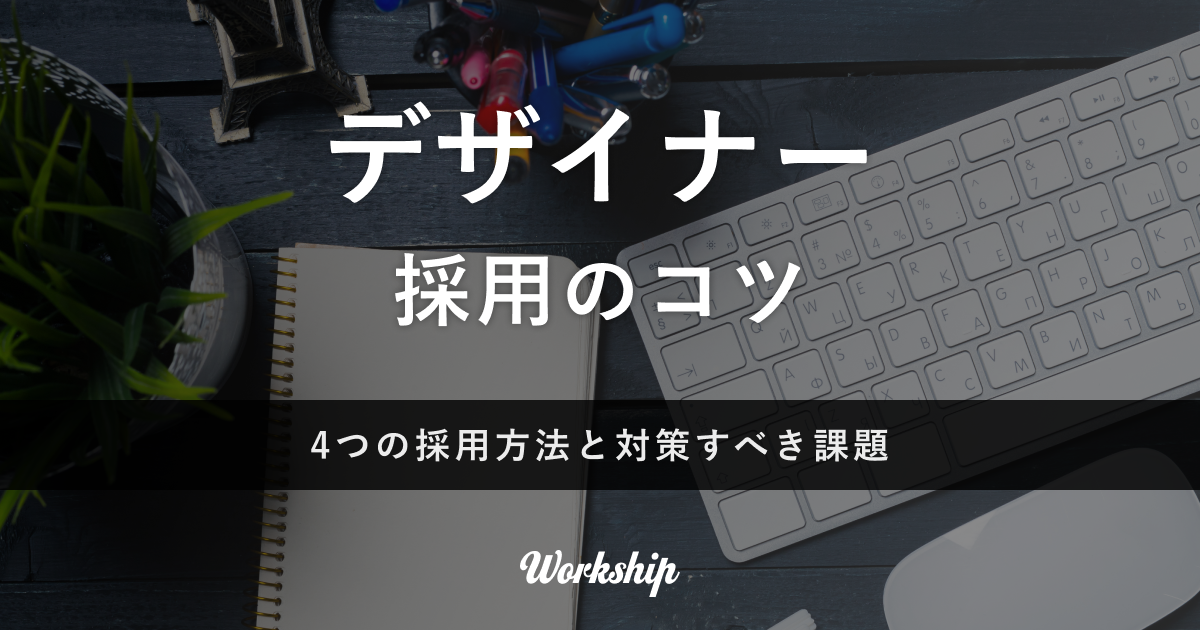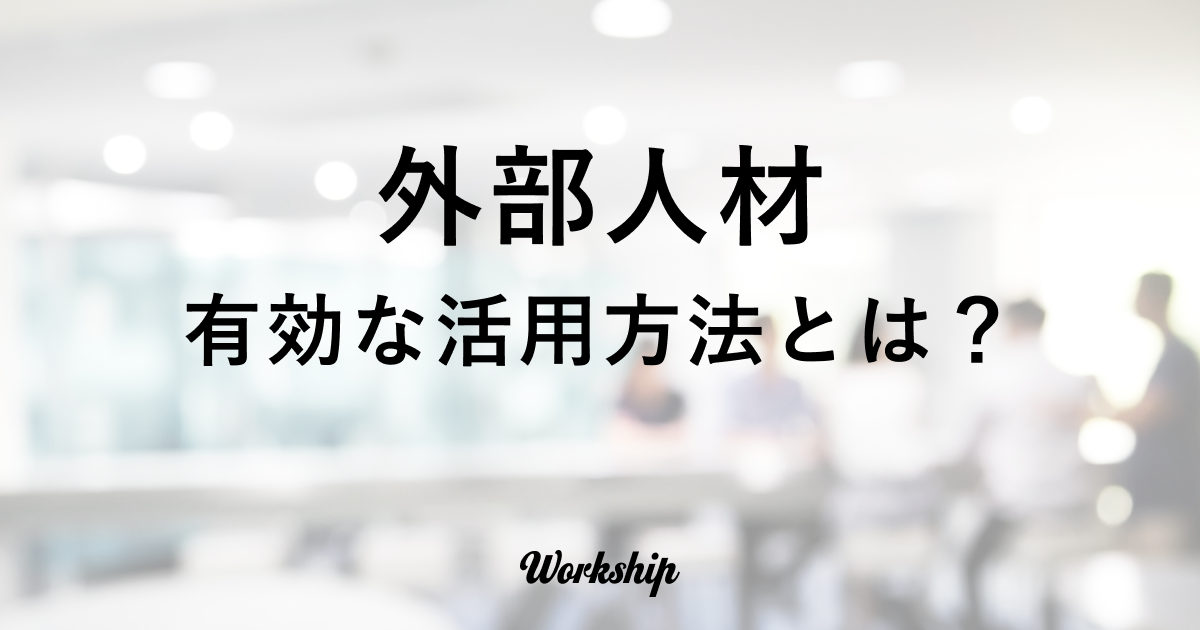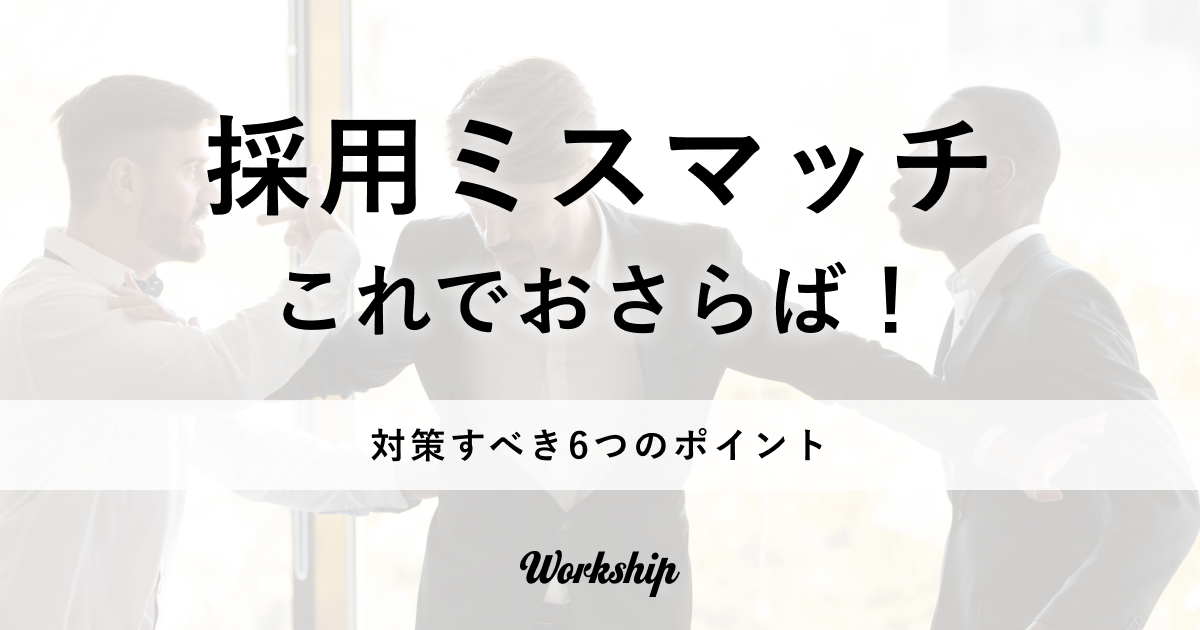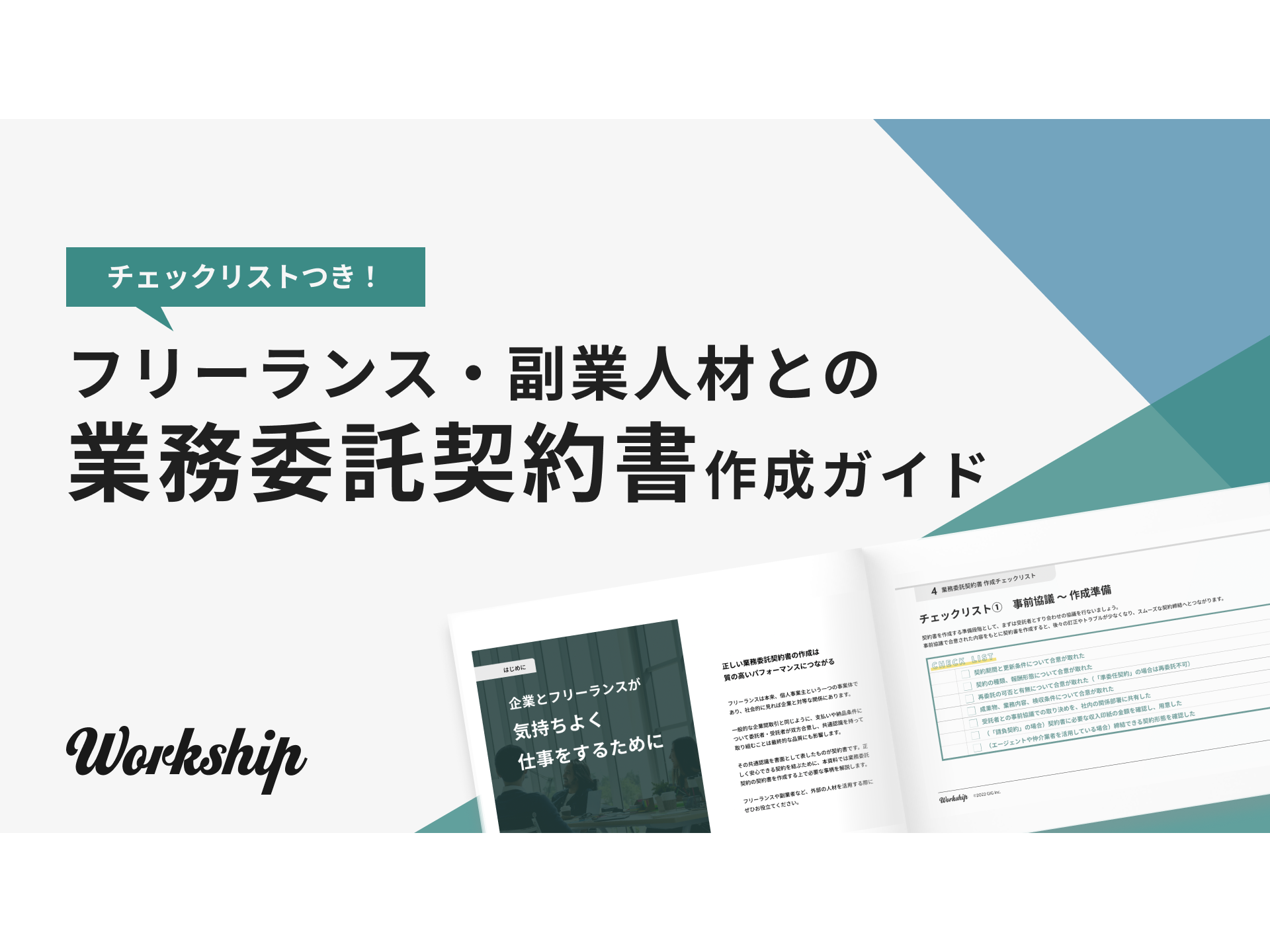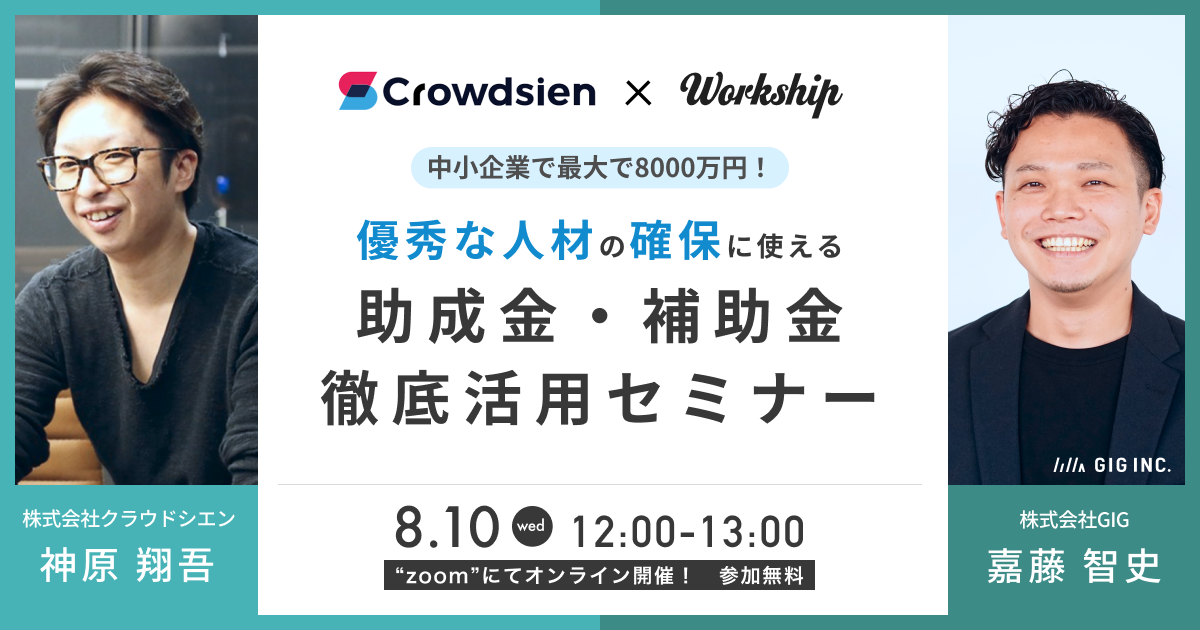エンジニア業務の外注とは?外注のメリットや費用相場、注意点など解説
「エンジニアを正社員で採用したいものの、なかなか自社にマッチする人材と出会えない」と悩んでいませんか?解決策の一つとして、「エンジニア業務の外注」がおすすめです。
外注を活用すれば、即戦力エンジニアの確保によって開発スピードが向上します。セキュリティやナレッジ共有の体制を整え、エンジニア業務の外部委託を成功させましょう。本記事では、外注のメリットや外注の費用相場など、エンジニア業務の外注について詳しく解説していきます。正社員採用に苦戦している人事担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
エンジニア業務の外注とは
エンジニア業務の外注とは、自社の開発業務や技術的な作業を、外部のエンジニアや専門チームに依頼することを指します。エンジニア業務の外注化は、以下のような企業におすすめです。
- 社内リソースが限られている
- 即戦力人材をすぐに確保したい
- 自社に正社員のエンジニアを常駐させる余裕がない
- 特定のプロジェクトや期間のみ仕事を依頼したい
近年、外注サービスを提供する企業やプラットフォームが増え、企業は多様な選択肢の中からエンジニアを採用できるようになりました。これにより、企業はスムーズな人材確保が可能となり、プロジェクトを効率よく進められます。
エンジニア業務の外注には、フリーランスエンジニアとの直接契約やエージェントを通じたマッチングなど、さまざまな方法があります。自社のニーズに応じた最適な外注方法を選び、開発スピードを向上させていきましょう。
エンジニア業務の外注・委託・請負の違い
エンジニア業務を外部に依頼する際、「外注」「請負」「委託」といった用語が使われます。これらの言葉の意味や目的は、微妙に違います。それぞれの違いについて、以下にまとめました。
用語 | 概要 |
外注 |
|
委託 |
|
請負 |
|
特に注意したいのが、業務委託契約です。業務委託契約とは特定の業務や行為を外部に依頼する契約のことで、おもに 「請負契約」「委任契約」「準委任契約」 の3種類に分類されます。
契約形態 | 概要 |
請負契約 |
|
委任契約 |
|
準委任契約 |
|
より詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:外注と委託の違い|言葉の意味や使い方の注意点まで徹底解説
エンジニア業務を外注するメリット3つ
以下では、エンジニア業務を外注するメリットを3つ紹介します。
即戦力をすぐに確保できる
エンジニア業務を外注すると、スキルを持つ即戦力を迅速に確保できるため、開発スピードを落とさずにプロジェクトを進められます。正社員のエンジニアを採用する際は選考や育成に時間が必要ですが、外注なら実績のある人材に業務を迅速に依頼できます。
外注を成功させるには、優秀なエンジニアが集まるサービスや企業、チャネルの選定が重要です。たとえばエージェント型のサービス(例:Workshipやクロスネットワーク)を活用すれば、「こんな人材が欲しい!」と要件を伝えるだけで、スクリーニングから確保までの代行を依頼できます。
リソースを柔軟に調整できる
正社員のエンジニアを雇う場合、長期契約が前提となり、自由な人員配置や契約締結が難しいでしょう。外注では、短期間のニーズに合わせたフレキシブルな人材確保が可能です。
たとえば、「プロジェクト終了時に即座にリソースを解放」といった対応がとりやすくなるでしょう。リモートワークを導入すれば、事業所にかかる設備費や事務用品代も削減できます。外注化は、予算やスケジュールに応じた効率的なリソース調整が可能となり、無駄なコストの発生を回避します。
開発スピードが向上する
外注の活用により、開発スピードの向上が期待できます。多くの外部エンジニアは特定の技術領域に詳しいため、スムーズな業務着手が可能です。たとえばAWSを使用したい場合、AWSに精通した人材に業務を依頼することでプロジェクトのスピードが加速します。
また、複数のエンジニアに作業を同時に委託すれば、分野ごとに特化した人材への仕事の分配が可能となり、並行して開発を進められます。
エンジニア業務を外注した場合の費用相場
エンジニア業務を外注する際の費用相場は、依頼する業務内容や規模、エンジニアの経験・専門性などにより大きく異なります。
エンジニアの外注費用は、人月単価によって決定することが多いです。人月単価とは、「エンジニア1人あたりにかかる1ヶ月分の仕事量」を指します。たとえばフリーランスのインフラエンジニアに業務を委託する場合、費用相場の目安は以下のようになります。
インフラエンジニアのレベル | 人月単価相場の目安(月) |
初級:実務経験1〜2年 | 約30万円〜50万円 |
中級:実務経験3〜4年 | 約50万円〜80万円 |
上級:実務経験5年 | 約80万円〜100万円 |
単純なWebサイトの保守・運用、デバッグ作業であれば、低価格で依頼できるかもしれません。しかし、特殊な技術を必要とする場合や、短期間での納品を求める場合、費用が高くなるでしょう。
外注費を抑えるには、「依頼内容の明確化」や「複数の外注先から見積もりを取る」といった対応が必要です。
エンジニア業務の外注費を抑えるコツ
ここでは、エンジニア業務の外注費を抑えるコツについて紹介します。
補助金の導入を検討する
エンジニア業務を外注する際、補助金の活用によってコストを抑えられます。政府や自治体は、技術開発や人材育成、DX支援のため、さまざまな補助金や助成金を提供しています。以下は、その一例です。
補助金 | 概要 |
IT導入補助金 |
|
ものづくり補助金 |
|
事業再構築補助金 |
|
出典:IT導入補助金_IT導入補助金2025 / ものづくり補助金 / 事業再構築補助金
補助金を上手に利用することで、外注費用の一部をカバーできます。ただし、補助金の申請には一定の要件や応募の締切があるため、手続きする際は注意が必要です。
パッケージを利用する
エンジニア業務を外注する際、ゼロからの開発ではなく、パッケージソフトウェアや既製のソリューションを利用すると費用を抑えられます。既存のツールやテンプレートをベースにカスタマイズすることで、開発にかかる時間や費用の削減が可能です。
特に一般的なニーズに適合するパッケージは、プロジェクトを効率的に進めつつ、開発期間を大幅に短縮できます。ただしカスタマイズが必要な場合、追加費用が発生する可能性がある点は気をつけましょう。そのためパッケージを選ぶ際は、業務範囲や仕様を十分に確認し、自社のニーズに適しているかを慎重に判断する必要があります。
フリーランスに仕事を依頼する
フリーランスへの依頼も、外注費を抑える手段になります。正社員採用の場合、固定の給与や福利厚生費がかかります。フリーランスであれば、プロジェクト単位での柔軟な契約が可能なため、必要な作業だけの依頼が可能です。
さらに専門分野に強みをもつフリーランスへの依頼は、高いスキルを活かした効率的な業務推進により、結果的にコストパフォーマンスが向上します。
エンジニア業務を外注化するステップ7つ
ここでは、エンジニア業務を外注化する過程について解説します。
ステップ1. 委託業務の範囲や契約内容を明確にする
エンジニア業務の外注で最初に行うべきステップは、委託業務の範囲や契約内容の明確化です。「どの業務を外注するのか」「納期や成果物の品質はどの程度か」「進捗報告の頻度は週何回か」など、詳細に決めましょう。以下では、最初に取り決めるべき項目についてまとめました。
項目 | 概要 |
業務範囲 | どの作業を外注するのか、具体的な業務内容を明記する。(例:システム開発、バグ修正、運用サポートなど) |
納期 | 各段階の納期や最終納品日を明確に設定する。 |
成果物の品質基準 | 完成品に求められる品質や仕様を具体的に記載する。 (例:コードのクオリティ、動作確認、テストの基準など) |
進捗報告の頻度 | 定期的な進捗報告のタイミング(例:週次ミーティング、月次報告)を決める。 |
予算・報酬 | 外注費用、支払い条件、分割払いの有無、報酬体系を明確にする。 |
コミュニケーション方法 | 進行中のやり取りに使用するツール(例:Slack、メール、オンラインミーティング)や対応時間帯を設定する。 |
修正対応 | 成果物に問題があった場合の修正対応方法や期間を決定する。 |
納品後のサポート | 納品後のサポートや保守に関することを決める。(例:バグ修正やアップデート) |
守秘義務 | 業務に関連する機密情報の取り扱いや守秘義務について記載する。 |
契約解除条件 | 契約解除の条件や手続きを明確にする。(例:納期遅延、品質不満足などの理由で契約解除が可能) |
これにより、スムーズな進行が可能になります。契約内容が曖昧だと後々のトラブルの原因となるため、依頼範囲を明確にしておきましょう。
ステップ2. 外注先を選定する
次に、外注先を選定します。過去の実績や専門分野、業務に対する理解度を確認し、信頼できる企業やフリーランスを選びます。
面談やオンラインミーティングでは、エンジニア業務を請け負う人材のスキルやコミュニケーション能力を評価しましょう。予算や納期を考慮しつつ、自社に適した人材・パートナーを選ぶのが重要です。
ステップ3. 契約を締結する
外注先が決まったら、正式に契約を締結します。契約書には以下のような内容を明記し、双方の合意を得ましょう。
- 業務委託の範囲
- 納期
- 報酬
- 成果物の品質基準
- 守秘義務
また万が一のトラブルに備え、契約書に解約条項や問題発生時の対応方法も盛り込みます。契約締結後に業務が円滑に進むよう、法的に必要な手続きをしておきましょう。
ステップ4. キックオフミーティングを実施する
業務開始前は、プロジェクトの目標や進行方法を再確認する、キックオフミーティングを実施します。
具体的には、業務フローや進捗管理の方法、問題が発生した場合の対応策などを共有します。キックオフミーティングはチーム間のコミュニケーションを深め、今後の連携をスムーズにする基盤作りとして有効です。
ステップ5. 業務を開始する
キックオフミーティングを終えたら、いよいよ業務開始です。事前に合意した業務内容や納期をもとに、外注先が作業を始めます。発注者は進行状況を定期的にチェックし、必要に応じてフィードバックしながら業務を進めていきます。
作業が順調に進むよう、問題が発生した際には早期に対処していきましょう。
ステップ6. 納品・検収する
業務が完了したら、外注先から成果物が納品されます。納品物を確認し、事前に決めた品質基準を満たしているかの検収を行います。
納品物が期待に応えられていない場合、修正や再提出を依頼しましょう。細部まで確認して必要な修正点を指摘した後、正式に納品完了となります。
ステップ7.運用体制を調整する
業務完了後は、運用体制を調整していきましょう。必要に応じて、コミュニケーション方法や評価方法などを見直します。
また、外注先との契約を終了したいケースに備え、自社内で引き継ぎ方法やナレッジ共有の体制も整えておきましょう。
エンジニア業務を外注する際の注意点
次に、エンジニア業務を外注する際の注意点について解説します。
セキュリティ対策を講じる
エンジニア業務を外注する際は、セキュリティ対策を万全にしましょう。外注先が扱うデータやシステムには機密情報が多いため、情報漏洩や不正アクセスへの防止が欠かせません。
契約書には守秘義務を明記し、外注先が遵守すべきセキュリティ基準を設定します。たとえばアクセス権限の管理やデータの暗号化、定期的なセキュリティ監査の実施によって、リスクを最小限に抑えられます。
エンジニアとの相性を確認する
コミュニケーションの取りやすさや、業務に対する考え方の一致など、エンジニアとの相性は業務効率に大きく影響します。そのため、面談やテストプロジェクトの実施が重要です。
また、進捗報告の方法や問題解決のアプローチにおいても、認識のズレがないかを確認し、円滑な協力関係を築くことが求められます。
ナレッジ共有の体制を整える
エンジニア業務を外注する際は、ナレッジ共有の体制整備が不可欠です。仮に契約が終了しても、外注先が担当した業務やプロジェクトの知識を自社でも活用できるよう、情報共有の仕組みを作っておきます。
外注先の作業内容を把握するために、コードのレビューや仕様書の管理を徹底し、社内でのスムーズな引継ぎや運用体制を整えましょう。他にも、ドキュメント管理システムの活用や、定期的なミーティングでの情報共有も効果的です。
エンジニア業務の外注先の種類
エンジニア業務の外注先は、以下の通りです。
小規模システム開発会社
小規模システム開発会社は、密なコミュニケーション体制が特徴です。機能のカスタマイズや変更依頼など、細かなニーズに応える傾向があります。
また、コンサルティングやパッケージ販売、Webマーケティング支援など、企業によっては提供するサービスの幅が広いです。そのため発注側は、開発企業の実績や得意分野を確認し、予算内で業務が依頼できるかをチェックしていきましょう。
大手システム開発会社
大手のシステム開発会社は、豊富なリソースと高い技術力を持っており、規模の大きいプロジェクトや複雑なシステム開発に対応する傾向があります。信頼性やサポート体制の充実により、納期の保証が期待できます。
また、業界標準の技術やプラクティスを遵守するケースが多く、セキュリティや法規制にも対応。ただし、その分コストは高めであり、柔軟性に欠ける場合があるでしょう。
派遣会社
エンジニア業務の外注先に、派遣会社もあります。派遣会社は、専門知識や専門技術を持つエンジニアが集まっており、発注側はプロジェクトに合った即戦力を投入できます。
たとえば、システム開発やインフラ構築、運用サポートなど、特定の工程に特化した業務の依頼が可能です。派遣会社は労働契約や給与の管理も行うため、企業側は雇用関連の負担を軽減できる点もメリット。業務終了後に応じて契約を解除することも可能なため、柔軟にリソースを調整できます。
ただし、派遣社員は自社の社員ではありません。そのため、チームとのコミュニケーションやカルチャーフィットの確認は必要となります。
オフショア開発
オフショア開発とは、海外の開発チームに業務を委託する方法のことです。コストを削減しつつ、海外の優秀なエンジニアと仕事できるとあって、昨今、注目が集まっています。
ただし、言語や文化の違い、タイムゾーンの問題には注意しましょう。プロジェクト管理ツールを導入し、進捗報告を徹底していきます。
フリーランス
フリーランスは、企業や組織に属さず、仕事を受注する働き方のことです。企業は、専門スキルを持ったフリーランスエンジニアに業務を委託できます。契約条件や納期に合わせて、必要な作業を必要な期間依頼できる柔軟性が魅力です。
また、個人のエンジニアとのやり取りになるため単価交渉がしやすく、開発企業への依頼と比較してコスト調整がしやすいです。「高い専門性が必要」「特定のプロジェクトのみ、すぐにアサインしてほしい」といった場合、フリーランスへの業務委託が活躍します。
フリーランスエンジニアは「やめとけ」と言われる理由と対策
「エンジニア 外注」と検索すると、「フリーランスエンジニア やめとけ」とあり、フリーランスエンジニアへの依頼をためらう人もいるのではないでしょうか。
ここでは、「フリーランスエンジニア やめとけ」と言われている理由と、その対策について解説していきます。
プロジェクトを離脱するリスクがある
フリーランスエンジニアは個人で活動しているため、急な契約終了や離脱のリスクがあります。特に、体調不良や他の案件への優先などによって、業務が突然中断する可能性も否めません。
そのため、契約期間や途中解約時に関するルールの明確化が重要です。たとえば、「◯ヶ月前に通知する」「未納品分の◯日以内に対応する」といった内容を契約書に盛り込むと、リスクを軽減できます。
また一人のフリーランスに依存するのではなく、複数人と契約してバックアップ体制を構築すると業務の安定性を確保できます。さらに、業務のドキュメント化を徹底し、仕様や設計書を残しておくと、別のエンジニアへの引き継ぎもスムーズになります。
責任範囲があいまい
フリーランスは企業の社員ではないため、トラブル発生時に責任の所在が不明確になることがあります。特にシステムに問題が発生した際、対応範囲が不明確だと、トラブルに発展しかねません。
そうした事態を防ぐために、契約書には責任範囲を明記しておきます。たとえば、「バグ発生時の対応は◯日間」といった条件を載せておくと、双方の認識が一致しやすくなります。
また事前に、トラブル対応のフローを決めておくことも有効です。「連絡方法・対応可能な時間」「緊急時の対応方針」など、確認しておきましょう。
コミュニケーションの齟齬が発生しやすい
リモートワークでやり取りする場合、プロジェクト全体の進捗状況が把握しにくくなり、認識のズレが発生しやすいです。そのため、以下のような対策をとるといいでしょう。
- 週1回の進捗報告会やミーティングを実施する
- タスク管理ツールを活用して業務を見える化する
- SlackやChatworkといったツールを活用し、即レスを促す
- TrelloやNotionなどを使用し、進捗状況をリアルタイムに把握する
作業の進捗やルールの共有によって認識の齟齬を防ぎ、やり取りをスムーズにしていきましょう。
品質にバラつきがある
フリーランスエンジニアのスキルや経験は、個人によって異なります。そのため実際に契約すると、「期待していたスキルが不足している」と感じるケースも少なくありません。
対策として、事前にエンジニアの実績やポートフォリオを確認します。たとえば、GitHubの公開リポジトリや過去の開発案件、クライアントからのレビュー評価などをチェックすると、技術力を見極めやすいです。
また、いきなり本契約を結ぶのではなく、最初に小規模なテストプロジェクトを実施し、実力の確認後に本格的な契約を結ぶと安心です。信頼できる人からの紹介や、評判の良いフリーランスエージェントを活用することで、一定の品質が確保されたエンジニアと契約しやすくなります。
コストが高くなる場合がある
フリーランスエンジニアは企業の社員とは異なり、社会保険や福利厚生の負担がない代わりに、追加料金や単価設定が高い場合があります。結果、想定以上のコストが発生するケースもあるでしょう。
そのため業務内容を細分化し、追加コストを防止していきます。たとえば、「〜の範囲外は追加費用」「修正は◯回まで無料」などの条件を確認しておくと、不要なコストを抑えられます。
また単発契約ではなく、できれば6ヶ月や12ヶ月といった長期契約がおすすめです。信頼関係が構築されることで単価交渉がしやすくなり、将来的なコスト削減につながる可能性があります。他にも、費用対効果を考慮し、外注と内製をバランスよく活用してみましょう。たとえば、事業の核となる部分は自社のエンジニアが担当し、補助的な業務や短期プロジェクトはフリーランスに任せることで、コストと品質の最適化が図れます。
エンジニア業務を請け負うフリーランスの探し方
以下では、エンジニア業務を請け負うフリーランスの探し方について解説します。
SNSやコミュニティで探す
フリーランスのエンジニアを探す方法の一つとして、SNSやコミュニティの活用が挙げられます。LinkedInやX(旧Twitter)、GitHubなどのSNSは、エンジニアの実績や活動内容を直接確認でき、スキルや専門分野に合ったフリーランスを見つけやすいです。
また、技術系のオンラインコミュニティや勉強会に参加すると、フリーランスエンジニアと直接やり取りでき、信頼関係を築けます。ネットワーキングを通じてリファレンスをゲットできる点でもメリットです。
クラウドソーシング・マッチングプラットフォームを使う
クラウドソーシングサイトやマッチングプラットフォームは、フリーランスのエンジニアを効率よく見つけられる有力なツールです。
これらのプラットフォームでは、フリーランスが自身のスキルセットを公開しています。過去の実績や経歴を簡単に確認できるため、自社が求めるスキル・経験を保有した人材を探せます。必要に応じて、募集をかけることも可能です。また、契約後の進捗管理や決済も、サービス提供会社によるサポートがあるため、安心して利用できます。
フリーランスエージェントを活用する
フリーランスエージェントでは、経験豊富なエージェントスタッフを通じて、即戦力のフリーランスエンジニアを紹介してもらえます。求める条件に合った迅速なマッチングと、契約までのスムーズな進行が魅力です。
適切な報酬や契約条件の交渉をサポートしてもらえるため、トラブルを避けやすく、安心して依頼できます。またエージェントによっては、プロジェクトの進捗管理やサポートを提供するところもあります。
エンジニア業務を外注したいなら『Workship』がおすすめ
エンジニア業務の外注を考えている企業には、登録無料の『Workship』がおすすめです。『Workship』では、フリーランスと企業を迅速にマッチングさせるサービスを提供しております。
Workshipのサービスの特徴を簡単にお伝えします。
アカウント登録が無料!
Workshipはアカウント登録料無料で、次のさまざまな機能をご利用いただけます。
- ニーズに合わせたマッチ度の高い候補者を随時提案
- スカウト機能
- フリーランス検索
- 求人掲載は無制限
- 無制限のメッセージ機能で候補者と直接交渉が可能
- オンライン面談
- 求人作成代行
- オンラインサポート
- 印紙代不要の電子契約
- 正社員転換契約
- 賠償責任保険が自動で適用
- 稼働管理
※自動で費用が発生することはありません。
※料金はユーザーとの成約が完了した時点で発生します。
また、ご利用いただく中でお困りのことがあれば、随時丁寧にサポートいたします。
三者間契約でインボイス制度の不安がない
フリーランスを活用する上で、採用担当者様の工数負担が大きいのが、契約書の取り交わしです。Workshipでは成約時に、「企業 ⇄ Workship ⇄ フリーランス」の三者間契約を締結し、契約手続きも代行いたします。クライアント企業となるお客様の契約先はWorkshipとの契約となるため、フリーランス活用でネックとなるインボイス制度への対応も問題ありません。
Workshipで稼働と進捗管理も安心
成約後、Workshipの管理画面内でフリーランスの稼働を管理することも可能。管理画面ページを閲覧するだけで、稼働時間や業務の進捗といった定期チェックもしやすくなります。
成約まで費用は発生しません!成約後も14日間の返金保証アリ!
Workshipでは、外部のフリーランスを活用し始めるまで、月額費用がかかりません。そのため、自社にマッチする人材をじっくりと見定められます。また、成約後であっても14日間は返金保証があり、ミスマッチを起こす可能性が低くなります。
▼以下では、Workshipのサービス資料を無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。

また、企業とフリーランスエンジニアとのマッチング支援に特化した『クロスネットワーク(X Network)』もおすすめです。


『クロスネットワーク(X Network)』では、エンジニアのプロフェッショナルネットワークを活用しつつ、企業はより専門的なエンジニアを見つけられます。どちらのサービスも、即戦力人材の迅速な確保を支援いたします。
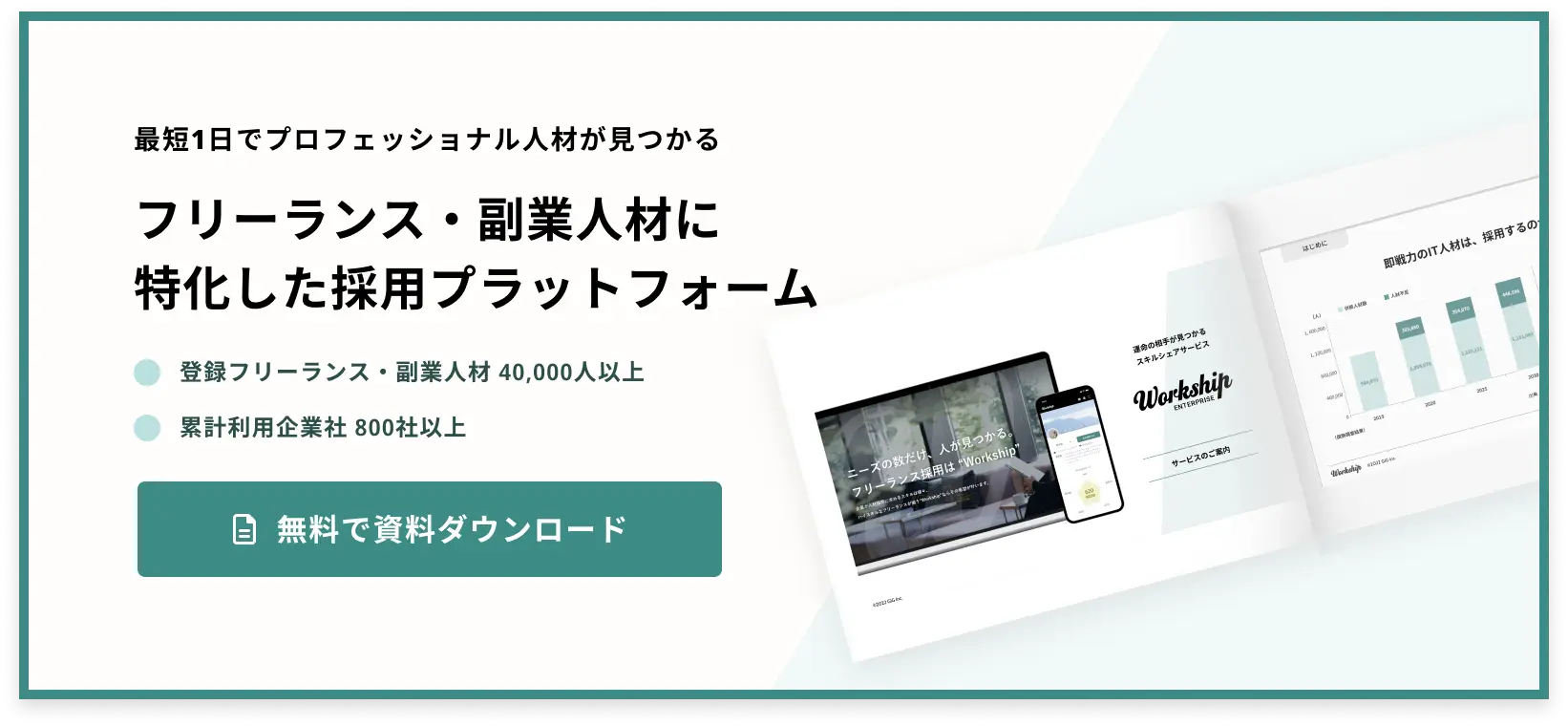 無料アカウント登録
無料アカウント登録