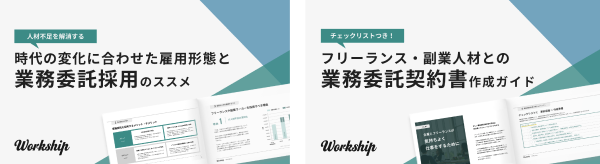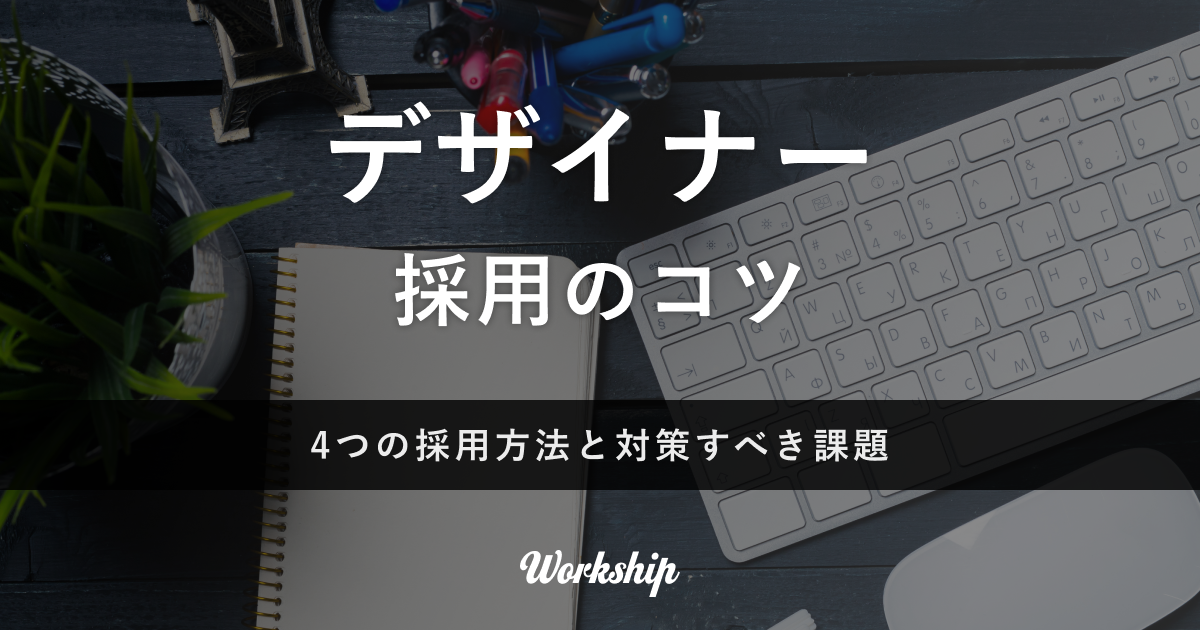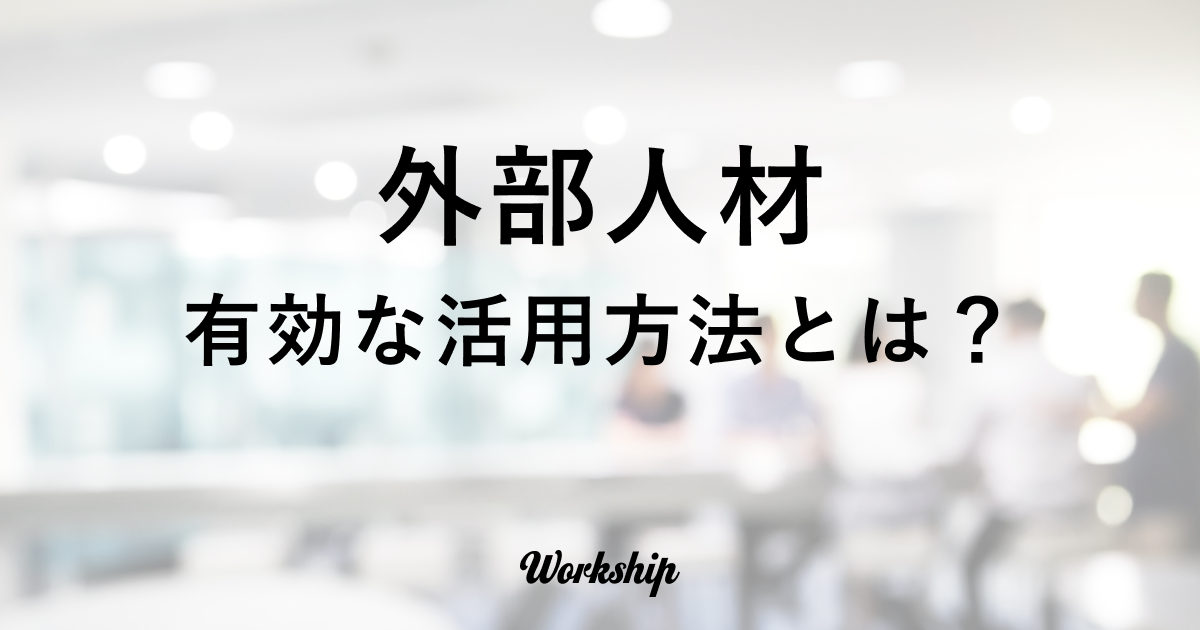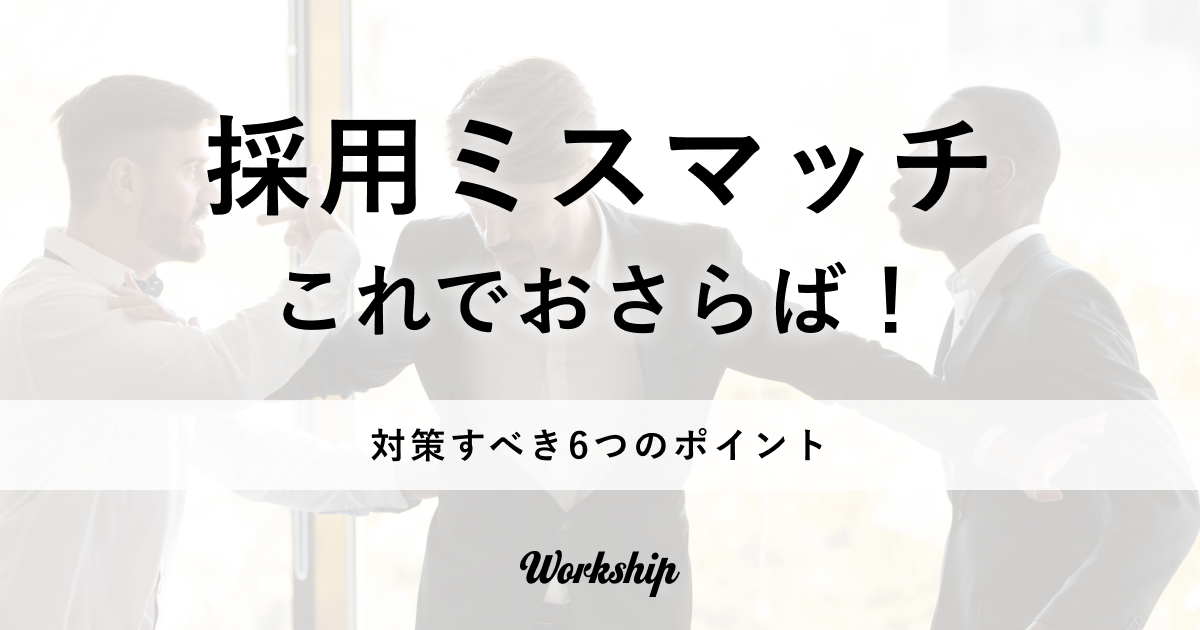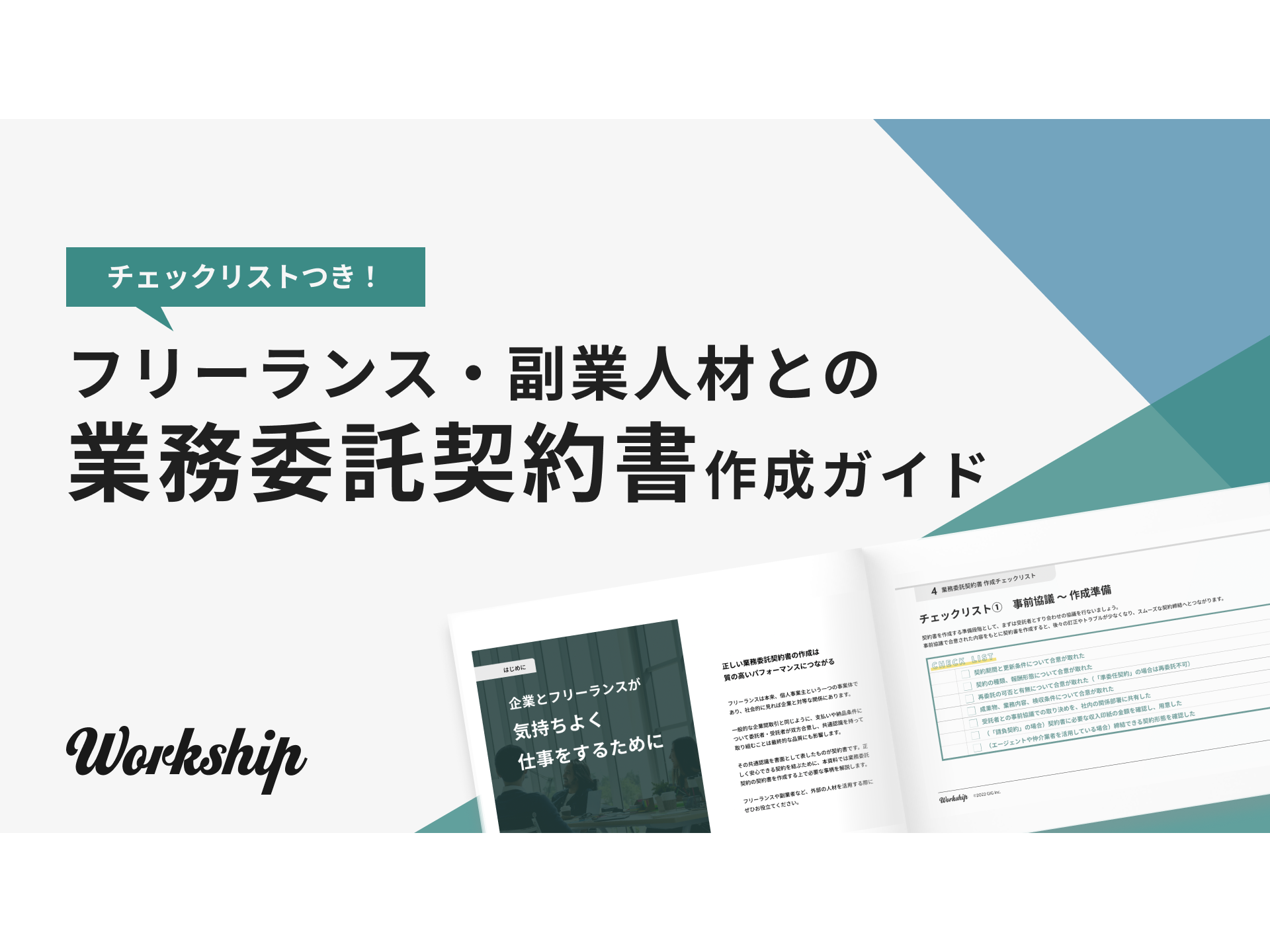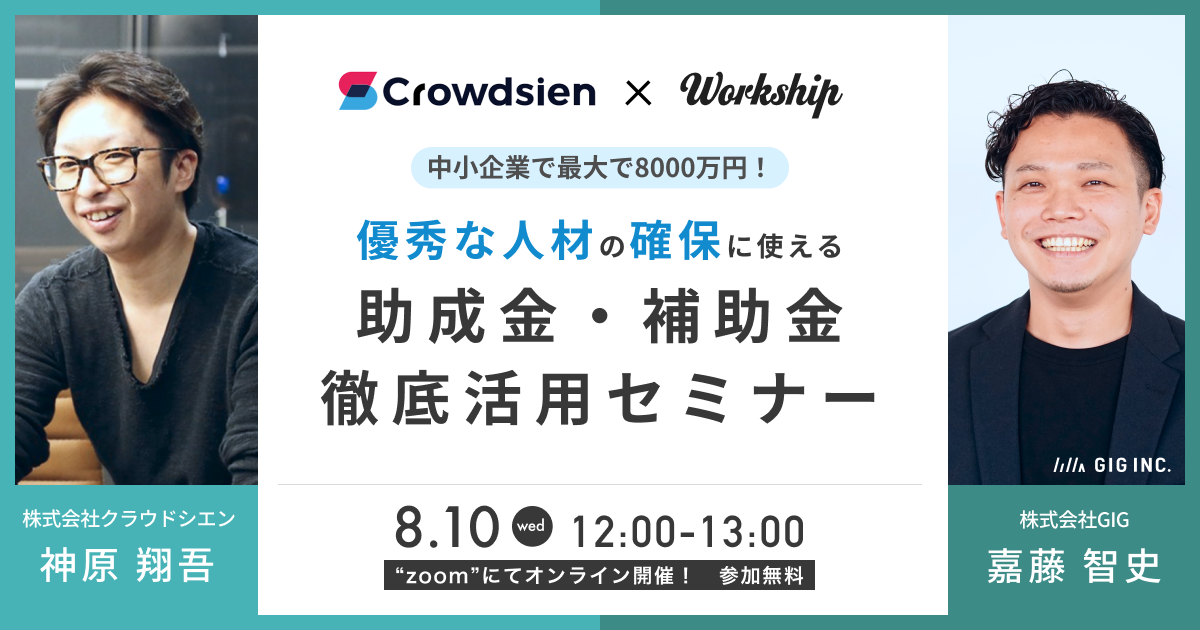AIによる業務の効率化とは?おすすめのAIツール15選や活用事例を紹介
繰り返し作業の自動化や高度なデータ分析など、AI(人工知能)は急速に進化し続けています。業務の効率化やDX推進の手段として、AIを積極的に活用する企業や、AI導入を検討する企業が増加している状況です。
一方で、「AIツールを登録したものの活用方法がわからない」「どんなAIツールがあるのか知りたい」という疑問を抱いている人も多いでしょう。そこで本記事では、AIの基本知識からAI導入のメリット、導入の手順までわかりやすく解説。さらに、最新のAIツールや、業界・部門別の成功事例についてもまとめました。
「これからAIの導入を進めたい」もしくは「既にAIツールを活用している」企業にとって、実践的かつ役立つ情報が満載です。
そもそもAIとは?AI導入が企業に求められている背景
AI(人工知能)とは、学習・推論・判断といった、人間の知能を模倣するコンピュータシステムやソフトウェアのことです。大量のルール・データの学習で、企業は業務の自動化や効率化を図れます。日本政策金融公庫では、企業がAIの導入を検討する背景と具体的な活用事例として、以下の3つを挙げています。
企業がAIの導入を検討する背景 | 具体的な活用事例 |
1.人手不足の改善 |
|
2.業務の可視化 |
|
3.新たなビジネスの創出 |
|
▼出典:日本政策金融公庫-中小企業における AI 活用の現状と求められる支援
特にベンチャー企業を中心にAIの使用が活発化する中、人口減少と高齢化の影響により、今後さまざまな企業でAIが導入されると予想されています。他社に先んじた業務改革の一つとしてAIの活用を進め、市場での競争力を高めていきましょう。
AIで社内業務を効率化させるメリット
AIは、単なる業務の「自動化」にとどまりません。「業務品質の安定」「コスト削減」など、経営全体にプラスの効果をもたらします。
ここでは、企業がAIを導入することで得られる具体的なメリットについて解説していきます。
人的リソースを戦略業務に回せる
AIが定型的・反復的な業務を代替すると、社員の時間や労力に余裕が生まれ、本来注力すべき高度な業務に集中できます。たとえば、データ入力やレポート作成、問い合わせ対応など、毎日発生するルーティン業務は、AIやRPAを使えば自動化が可能です。
そのため担当者は、マーケティング戦略の立案や業務改善の提案、新規事業の企画といった、企業の価値を高める創造的なタスクに時間を使えるようになります。AIの活用は単なる業務効率に止まらず、企業全体のパフォーマンス向上やイノベーションの加速にも貢献します。
作業時間が大幅に減る
AIを導入すると、これまで数時間〜数日かかっていた業務が、わずか数分〜数秒で完了するようになります。たとえば請求書の内容を手入力していた業務では、AI-OCRによるスキャンで自動的にデータ化・システム登録まで実行可能です。
AIチャットボットを活用すれば、「よくある問い合わせ」への回答を即時的に自動で送信できるため、担当者の対応が不要になります。24時間休むことなく稼働するAIは、今後、作業効率を飛躍的に向上させるツールとして企業になくてはならないものになっていくでしょう。
業務品質が安定する
AIは常に一定のルールやアルゴリズムに従って処理を行うため、人による作業のばらつきやミスを防ぎます。たとえば、手作業によるデータ入力や目視による検品では、疲労や集中力の低下でミスが発生することがあります。AIであれば、いつでも同じ精度で処理を進めるため、人的ミスを大幅に減らせるでしょう。
また、AIによる画像認識を使った製品検査では、人では見逃してしまうような微細なキズや異常を高精度に検出できます。AIチャットボットによる顧客対応も、常に定型化された回答を返すため、オペレーターごとの対応品質の差をなくせるでしょう。AIの活用で作業プロセスの標準化と再現性が高まるため、業務品質が安定します。
人件費を削減できる
これまで人が対応していた業務の一部をAIが代替することで、必要な人員数や稼働時間を減らせます。たとえば、毎日発生するデータ入力や書類チェックといった定型業務は、AIツールによって自動化が可能です。こうした業務にかかっていた時間や人手が削減されることで、パート・アルバイト・派遣社員などの人件費を抑えられるでしょう。
さらに、AIは24時間稼働できるため、深夜対応や休日対応に人を配置する必要がなくなり、シフト管理や残業代といったコストも削減可能です。限られた予算内でも、企業はより生産性の高い業務に人的リソースを集中できるようになります。
データの蓄積と分析が可能になる
AIが日々の業務データを自動で収集・整理しつつ傾向や課題を可視化できるため、より精度の高い意思決定や業務改善につなげられます。
これまで人手で管理していたデータは、入力ミスや記録漏れが起こりやすく、集計や分析にも手間と時間がかかっていました。AIを導入すれば、顧客対応履歴や売上データといった情報を自動で蓄積し、リアルタイムに整理・分析できます。
さらに、AIは大量のデータから関連性や予測を立てることも得意なため、サービスの将来性や需要の予測といった戦略立案にも役立ちます。
AIは、得たデータを資産として活用できるようにするツールです。感覚や経験に頼る判断から、データに基づいた正確な意思決定へと企業を導いてくれるでしょう。
▼関連記事:AIで仕事はなくなる?AI活用と人的資源を両立させた人員再配置の流れを解説
AIで社内業務を効率化させる5つのステップ
AIを社内業務に取り入れて効率化するには、いきなりツールを導入するのではなく、計画的なステップを踏むことが重要です。場当たり的に進めると「うまく活用できなかった」「現場で定着しなかった」といった失敗につながりかねません。
ここでは、AI導入をスムーズに進め、業務改善の効果を最大化する5つのステップを紹介します。
1.AIで代替可能な作業を洗い出す
AI導入の第一歩は、現在の社内業務の中から、AIで代替できる作業を明確にすることから始まります。すべての業務がAIに置き換えられるわけではないため、最初に「どの業務が自動化に適しているか」を見極めていきましょう。具体的には、次のような業務がAI化に向いています。
AI化しやすい業務の一例 | 具体例 |
定型的でルールが明確な業務 |
|
繰り返し頻度が高く、工数がかかる業務 |
|
大量の情報処理が必要な業務 |
|
まずは部署ごとに業務内容を棚卸しし、「誰が・いつ・何を・どのくらいの頻度で」実行しているのかを可視化しましょう。その上で、「人でなくても対応できそうな作業」や「ミスが起こりやすい単純作業」をリストアップします。この工程を丁寧に行うと、AI導入の方向性が明確になり、無駄な投資や失敗のリスクを避けられます。
2.業務課題に応じたAIツールを選定する
AI導入で成果を出すには、自社の業務課題に適したAIツールの選定が重要です。目的に合わないツールを導入すると、十分な効果が得られず、かえって運用コストがかかる可能性があります。
「AIで代替したい作業」を元に、課題解決したい内容を整理しましょう。たとえば、「問い合わせ対応の負担が大きい」という課題なら「AIチャットボット」、「請求書処理に時間がかかる」という課題なら「AI-OCRや経費精算システム」が有効です。
また、無料トライアルやデモの実施から、「使いやすさ・他システムとの連携」といった運用面も確認します。自社の課題と目的にフィットしたAIツールを選び、効果的かつ継続的な業務効率化を実現しましょう。
3.小さく導入して効果検証を実施する
AI導入の初期段階では、特定の部署や業務フローなど「スモールスタート」で導入し、AIの効果を見極めましょう。作業時間や対応件数、エラー率などの変化を比較すると、AIの有用性が定量的に判断できます。たとえば、以下のような業務からAIを使ってみるといいでしょう。
- 営業部門の定型レポート作成
- 総務部の請求書処理
- 社内文書の作成 など
また、現場目線での課題の洗い出しも重要です。フィードバックをもとに、AIツールの改善や社内ルールの見直しを図ると、全社展開に向けやすくなります。小さな成功体験で社内全体の理解を進めると、AI活用推進の動きが活発化していくでしょう。
4.社内のセキュリティ体制を整える
AIを社内業務に活用する際は、セキュリティ体制の整備が欠かせません。AIツールの多くは、社内データや顧客情報などの重要な情報を扱うため、情報漏洩や不正アクセスなどのリスクに備える必要があります。
特にクラウド型のAIサービスを利用する場合、社外にデータを預けるため、暗号化・アクセス制限・ログ管理などのセキュリティ対策の事前確認が重要です。また、従業員が誤って機密情報を外部ツールに入力しないよう、運用ルールや教育体制も整えておきましょう。たとえば、以下のような対策が有効です。
- 利用するAIツールのセキュリティ規格を確認する
- 社員に対してAIの使用ルールといったガイドラインを明確にする
- 社内ネットワークやクラウドのアクセス権限を最小限に設定する
また、AIの出力結果を鵜呑みにせず、人の目による確認体制を残すことも管理の一環として欠かせません。特に顧客対応や契約書類など、誤った内容が大きな損失につながる業務では慎重な運用が求められます。情報セキュリティを確保しつつ、AIを社内に根づかせていきましょう。
5.定期的にAIツールの見直しを図る
AIは導入して終わりではなく、定期的な効果の調査や運用状況の見直しが肝心です。AI技術は日々進化しており、「数カ月前の最適解が今では通用しない」というケースもあります。
仮に導入当初は期待通りの成果だったとしても、業務フローの変更や事業規模の拡大により、AIツールの機能が合致しないこともあるでしょう。
そこで重要なのが、定期的な効果測定とフィードバックの収集です。たとえば、以下のような観点で見直しを行いましょう。
- 当初の業務改善目標(作業時間の削減、エラー率の低下など)を今も達成しているか?
- 社内の運用ルールや業務内容の変化に、AIツールが対応しているか?
- より高機能かつコストパフォーマンスの高いツールが登場していないか?
また、現場の社員から定期的にヒアリングを行い、新たなニーズについて把握することも重要です。継続的な改善活動によって、AIによる効果を最大限引き出し続けられるでしょう。
AI業務効率化ツール・アプリの種類
AIは、使用目的や機能によってさまざまな種類に分かれています。どのツールを選ぶかによって、改善できる業務領域や成果が大きく異なるため、自社の課題に合った種類を把握しておくことが重要です。以下に、主なAI業務効率化ツールの種類とその特徴を表でまとめました。
ツール種別 | 主な用途・機能 | 活用例 |
AIチャットボット |
|
|
AI-OCR |
|
|
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション) |
|
|
画像認識AI | 写真や映像から物体・文字・異常を自動で認識 |
|
音声認識AI |
|
|
予測・分析AI |
|
|
生成AI (Generative AI) | テキスト・画像・コードなどの自動生成 |
|
AIツールは、それぞれの得意分野で業務を効率化し、人的リソースを戦略業務に集中させる強力なサポーターとなります。複数のツールを組み合わせて使用することで、さらなる業務改善が期待できるでしょう。
【最新】AI業務効率化ツールおすすめ15選!一覧で紹介
AIツールは、今や企業活動のさまざまな場面で活躍しています。定型作業の自動化や問い合わせ対応、文章作成など、その用途は多岐にわたります。正しく選べば、作業時間の短縮や人件費の削減、意思決定の精度向上など、さまざまな業務改善効果が得られるでしょう。
ここでは、最新のAI業務効率化ツールを15個厳選し、用途や特徴とともに一覧でご紹介します。自社の課題に合ったツールを選ぶための比較材料として、ぜひご活用ください。
ツール名 | 主な機能・特徴 | 活用例 |
1.ChatGPT |
|
|
2.Gemini(旧Bard) |
|
|
3.Notion AI |
|
|
4.Microsoft Copilot |
|
|
5.Claude |
|
|
6.Notta |
| ・オンライン会議の議事録作成 |
7.Canva |
|
|
8.Adobe Firefly |
|
|
9.Vrew |
|
|
10.ChatPlus |
|
|
11.Zendesk |
|
|
12.hitobo |
|
|
13.Coopel |
|
|
14.RoboTANGO |
|
|
15.Robo-Pat |
|
|
【多用途に使える】AI業務効率化ツールおすすめ6選
AIの中でも幅広い用途に対応する「多用途型」のツールは、社内のあらゆる業務に活用しやすく、導入効果も大きいです。文章作成や情報検索、プレゼン資料の作成補助など、部門横断で使えるのが強みです。以下では代表的なツールをまとめました。
ツール名 | 主な機能・特徴 | 活用例 |
1.ChatGPT |
| メール作成、社内文書の草案、FAQ対応 |
2.Gemini(旧Bard) |
| 調査、コンテンツ作成、戦略案の下書き |
3.Notion AI |
| 会議メモの整理、プロジェクト共有 |
4.Microsoft Copilot |
| レポート作成、スライド作成、数式分析 |
5.Claude |
| 複雑な文書の構成、コーディング支援 |
6.Notta |
| オンライン会議の議事録作成、要点抽出 |
1.ChatGPT
出典:ChatGPT
ChatGPTは、自然な文章の生成や要約、翻訳、アイデア出しなど、さまざまな業務に活用できます。質問に対して人間のように応答する能力を持っており、ビジネス文書の草案作成や議事録の要約、プログラミング支援などにも対応可能です。
指示の仕方次第で幅広い業務に適応できるため、部署を問わず多用途に使えるAIとして、多くの企業で導入が進んでいます。ツール選びに迷ったら、まずはChatGPTから試してみるのもおすすめです。
2.Gemini
出典:Gemini
Gemini(旧Bard)は、Googleが提供する生成AIで、検索機能と連携しながら情報収集や文章作成をサポートしてくれるツールです。Google Workspace(GmailやGoogleドキュメントなど)と連携できる点が特徴で、日々の業務に自然と組み込みやすいのが強みです。
提案書のたたき台やメール文案の作成、アイデア出しなどにも活用されており、操作性も高くなっています。既存のGoogle環境と親和性が高いため、導入のハードルも低く、すぐに活用できるでしょう。
3.Notion AI
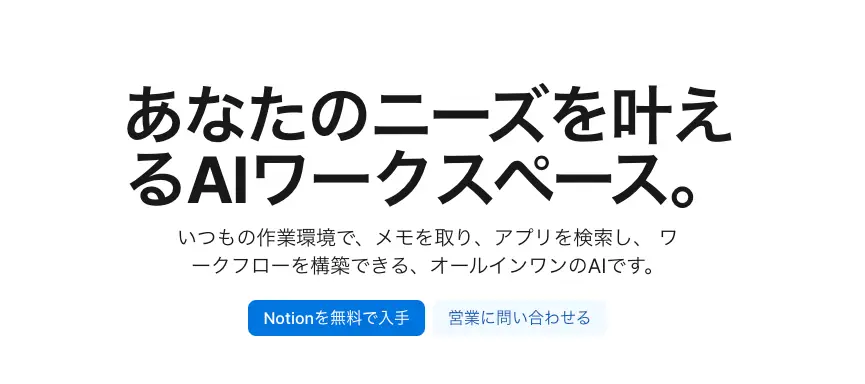 出典:Notion AI
出典:Notion AI
Notion AIは、ドキュメント管理ツール「Notion」に搭載された生成AI機能です。議事録の要約や文章のリライト、タスク整理、企画書の草案作成など、日常業務をサポートする多彩な機能が揃っています。
操作はシンプルで、Notion上で手軽にAIの活用が可能。特に情報整理やチームでのナレッジ共有に強く、ドキュメント作成のスピードと品質を同時に高めてくれます。すでにNotionを使っている企業には、導入しやすいでしょう。
4.Microsoft Copilot
Microsoft Copilotは、WordやExcelなどのMicrosoft 365アプリと連携できる生成AIツールです。文章作成の自動化や、表計算の分析、スライド資料の作成支援など、日々の業務を効率よく進められます。
たとえばExcelでは、複雑な数式列の候補やグラフ作成も、指示を入力するだけで実行可能。普段使っているOffice製品にAIを組み込むことで、学習コストを抑えながら社内の生産性をアップできます。
5.Claude
出典:Claude
Anthropic社が開発したClaudeは、自然な会話力に優れた対話型のAIです。長文の要約や構成作成、企画書のドラフト作成、議事録整理など、あらゆる業務で活躍します。
特にセキュリティや透明性を重視した設計で、企業利用にも適した安心感があります。丁寧かつ慎重な応答が得意なため、内容の精度や安全性が求められる業務にも対応しやすいです。多様な業務に柔軟に対応する、高品質な生成AIとして注目されています。
6.Notta
出典:Notta
Nottaは、会議やインタビュー、打ち合わせの音声をリアルタイムで文字起こしできるAI音声認識ツールです。ZoomやGoogle Meetなどのオンライン会議と連携し、自動で録音・書き起こし・要約までを一括で行えるのが特徴です。
対応言語も豊富で、グローバルなビジネスシーンにも対応可能。議事録作成にかかる時間を大幅に短縮し、手作業によるミスも防げます。会議の記録を効率化したい企業にとって、Nottaは強力なサポート役となるでしょう。
【画像生成・動画編集】AI業務効率化ツールおすすめ3選
画像や動画を扱う部門では、AIによるコンテンツ生成・編集ツールが活躍します。直感的な操作で高品質な素材を作成でき、クリエイティブ業務の時短につながります。
ここでは、以下3つのツールをご紹介します。
ツール名 | 主な機能・特徴 | 活用例 |
1.Canva |
|
|
2.Adobe Firefly |
|
|
3.Vrew |
|
|
1.Canva
出典:Canva
Canvaは、デザインの専門知識がなくても、誰でも簡単に高品質な資料や画像を作成できるデザインツールです。AI機能では、「マジックデザイン」や「文章から画像生成」など、わずかな操作でプロ並みのビジュアルを作れるのが魅力です。
プレゼン資料、SNS投稿画像、バナー広告など、ビジネスのあらゆるシーンに対応でき、チームでの共同編集も可能。デザイン業務の工数を削減しつつ、見栄えのするアウトプットを効率よく生み出せます。
2.Adobe Firefly
Adobe Fireflyは、Adobeが提供する生成AIツールで、テキスト入力から画像やグラフィックを自動生成できるのが特徴です。
PhotoshopやIllustratorとの連携によって、デザイン作業を直感的かつスピーディーに進められます。
商用利用にも対応しており、企業の広告バナーや商品画像の作成に最適です。クリエイティブ業務の効率化と表現力の向上を両立したい方におすすめのツールです。
3.Vrew
出典:Vrew
Vrewは、動画編集に特化したAIツールです。音声認識で字幕を自動生成するため、スムーズな編集が可能。テキスト編集だけで動画編集ができる手軽さは、初心者でも簡単に扱えると好評です。
YouTube動画の制作やインタビューの文字起こし、ショート動画など、ビジネスシーンで活用の幅が広がっています。手間のかかる動画編集を効率化し、伝わる動画コンテンツを短時間で仕上げたい企業におすすめです。
【チャットボット】AI業務効率化ツールおすすめ3選
顧客対応や社内問い合わせ対応に使えるチャットボットは、人的工数の削減に大きく貢献します。特に、24時間対応や即時回答が求められる業務に効果的です。以下では、代表的な3つのツールについて紹介します。
ツール名 | 主な機能・特徴 | 活用例 |
1.ChatPlus |
|
|
2.Zendesk |
|
|
3.hitobo |
|
|
1.ChatPlus
出典:ChatPlus
ChatPlusは、問い合わせ対応の自動化や、顧客対応の効率化に強いチャットボットツールです。あらかじめ設定したシナリオに沿って自動応答が可能で、必要に応じて有人対応への切り替えもスムーズに行えます。
ECサイトやサービスサイトに導入すると、24時間体制の問い合わせ対応が可能になり、顧客満足度の向上と対応コストの削減を両立できます。操作画面も日本語で直感的に扱えるため、導入や運用のハードルが低いのも魅力です。
2.Zendesk
出典:Zendesk
Zendeskは、世界中で利用されているカスタマーサポート向けのAIチャットボットツールです。Webサイト・メール・電話など、複数のチャネルを統合して顧客対応を効率化できます。
AIによる自動応答に加えて、問い合わせ管理やFAQの構築によって、迅速かつ一貫した対応が可能になります。SalesforceやSlackなど他の業務ツールとの連携性も高く、サポート業務を包括的に改善できます。サポート体制の強化と業務の効率化を同時に実現したい企業に最適なソリューションです。
3.hitobo
出典:hitobo
hitoboは、社内ヘルプデスクや顧客対応を自動化するチャットボットツールです。ノーコードで設定でき、FAQを登録するだけで自動応答がスタートできる手軽さが魅力です。
また履歴の分析機能も充実しており、質問内容を可視化することで、業務改善にも役立ちます。サポート体制の強化や業務の属人化防止を目指す中小企業にとって、導入・運用しやすいAIチャットボットのひとつです。
【RPA】AI業務効率化ツールおすすめ3選
ルールベースの定型業務を自動化するRPAツールは、バックオフィス業務の効率化に適しています。人の手による繰り返し作業をAIが代行することで、ヒューマンエラーも減らせます。
ツール名 | 主な機能・特徴 | 活用例 |
1.Coopel |
|
|
2.RoboTANGO |
|
|
3.Robo-Pat |
|
|
1.Coopel
出典: Coopel
Coopelは、プログラミング不要で自動化フローを作成できるノーコードRPAツールです。経費精算や請求書処理、定期レポート作成などを直感的に設計できます。管理画面も分かりやすく、トレーニングコンテンツも豊富なため、IT専門知識がない現場担当者でも使いやすいです。
さらに、Excelやファイル上での操作や、SNSでの情報収集も可能。1ヶ月の無料トライアルで実際に操作性を確認できる点も魅力です。
2.RoboTANGO
出典: RoboTANGO
RoboTANGOは、パソコン操作を「録画」するだけで簡単にRPAを作成・運用できる、国産RPAツールです。IT知識がなくても、経理の請求処理や定型レポートの作成など、日常的な定型業務を簡単に自動化できます 。
また、フローティングライセンスにより、1ライセンスで複数台のPCに導入できるため、拠点や部署を超えた共有利用にも優れています 。
無料トライアルもあるため中小企業でもスモールスタートしやすく、業務効率化・工数削減にすぐに取り組めるツールとして高く評価されています。
3.Robo-Pat
出典:Robo-Pat
Robo‑Pat(ロボパットDX)は、プログラミングや専門知識がなくても簡単に業務を自動化できる国産のRPAツールです。専任の担当者とカスタマーサクセスチームによるサポートがあるため、ITスキルを保有していない現場スタッフでも導入しやすい点が特徴です。
月単位の契約やフローティングライセンスに対応しており、繁忙期だけ一時的に導入したい企業にもマッチします。無料トライアル制度が整っており、特に定型作業の効率化や業務標準化を目指す組織におすすめのツールです。
【業界別】AIで業務を効率化させた事例
以下では、業界別にAIで業務を効率化させた事例について解説していきます。
製造・物流業界
製造・物流業界では、AIを活用した在庫管理や倉庫内オペレーションの効率化が進んでいます。たとえば、以下のような事例があります。
活用事例 | AI導入後の成果 |
AI搭載型の在庫管理システムを導入 |
|
倉庫内でAIと連携した車や画像認識技術を活用 |
|
こうした取り組みは、需要変動に柔軟に対応するスマートロジスティクスへの転換を促しており、業界内での競争力強化に直結しています。
小売業
小売業では、AIやRPAの導入により、ECモールとのデータ連携業務が大幅に効率化されています。たとえば、以下のような事例があります。
活用事例 | AI導入後の成果 |
ファッション通販サイトのデータを、RPAツールで自動ダウンロードする仕組みを構築 |
|
このように、小売業では「人的ミスを防ぎながら確実に繰り返す業務」に、RPAの活用が進んでいます。自動化によって、「業務の安定性向上・コスト削減・精度の高い在庫管理」という三拍子そろった効果を得られるでしょう。
不動産業
不動産業においては、AIを活用したコミュニケーションクラウドが、業務効率化と顧客満足度向上に効果を発揮しています。具体的には、以下のような活用事例と成果があります。
活用事例 | AI導入後の成果 |
クラウド型のAIシステムを導入 |
|
AIによるバックエンド業務のデジタル化が、不動産仲介の生産性と顧客体験を共に向上させるでしょう。
【部門別】AIで業務を効率化させた事例
次に、部門別でAIで業務を効率化させた事例について解説していきます。
経理部門
経理部門では、大幅な業務効率と業務品質の向上を目的に導入するケースが多く見られます。以下では、具体的な活用事例とAI導入後の成果をまとめました。
活用事例 | AI導入後の成果 |
AI-OCRとRPAを組み合わせたAIシステムを導入 |
|
承認プロセスや証跡の記録も一元管理するAIシステムを活用すれば、内部統制の強化にも寄与します。これにより、複数拠点展開でも迅速かつ安定した運用が可能となり、経理担当者が本来注力すべき分析や戦略業務へシフトできる余裕が生まれています。
営業部門
多くの営業部門では、AIツールで営業効率と質の両立を図っています。たとえば、以下のような事例があります。
活用事例 | AI導入後の成果 |
営業担当者が、市場動向や競合状況をリアルタイムで把握できるAIツールを導入 |
|
このように、AIによる情報分析基盤の整備は、営業における「属人化の防止」「スピード感ある対応」「チーム力の強化」への実現が期待できます。
人事部門
人事部門では、AIチャットボットを導入して社内問い合わせ対応の効率化を実現した、以下のような事例があります。
活用事例 | AI導入後の成果 |
社内からの「よくある質問」を自動応答にすべく、AIチャットボットツールを導入 |
|
上記のように、問い合わせ対応の自動化や、サポート体制の強化によって担当者の負担が大幅に軽減されるでしょう。人事部門が注力すべき採用業務や制度設計などに集中できる環境が整備される点は、企業にとって大きなメリットとなりそうです。
AIで社内業務を効率化させる際の注意点
AIで社内業務を効率化させる際は、以下の点に注意しましょう。
ファクトチェックを行う
AIは膨大なデータをもとに情報生成や提案を実行しますが、その内容が必ずしも正確とは限りません。特に生成AIは、存在しない事実をもっともらしく記述する「ハルシネーション(幻覚)」という現象を起こすことがあります。
たとえば、AIに商品説明文や業界の統計情報を作成させた際、実際には存在しないデータや誤った数値が含まれている可能性もあります。そのため、AIが出力した情報は必ず人間の目でファクトチェックを行うことが重要です。
社外向けの資料やWebコンテンツ、意思決定に関わる資料であれば、なおさら出典元の明記や一次情報へのあたり直しを徹底する必要があります。AIのアウトプットを盲信せず、事実確認を前提とした活用を心がけましょう。
社員のAIリテラシーを高める
AIを効果的に業務へ取り入れるには、社員一人ひとりがAIの仕組みや特性、注意点を正しく理解していることが不可欠です。AIリテラシーが低いままでは、誤った使い方による情報漏洩や、AIへの過信による誤判断が起きかねません。
たとえば、ChatGPTのような生成AIを業務で使う際、社外秘情報をうっかり入力してしまうと情報漏洩リスクが生じます。また、AIの提案を鵜呑みにすると、誤情報に基づいた意思決定となる可能性が高まります。
そのため、AIの基本的な仕組みやリスク、活用時のルールなどを学べる研修の実施やガイドラインの整備が重要です。社員全体のAIリテラシーを底上げすることで、安全かつ効果的にAIを業務へ取り入れられるようになります。
社内の運用体制を整える
AIを業務に導入する際は、AIを活用・管理する社内運用体制の整備が欠かせません。体制が不十分なままでは、効果測定や改善が行われず、期待した成果を得られないこともあります。他にも効果的に活用できていたものの、担当者の異動でノウハウが引き継がれず、形骸化するケースも少なくありません。そのため、以下のような対策をとっておきましょう。
- AI活用の責任者や推進チームの設置する
- 運用マニュアルやナレッジの蓄積する仕組みを作る
- 定期的な見直しフローを策定する
また、利用ルールやセキュリティポリシーを全社で共有し、従業員が安心して使える環境を整備することも重要です。安全な仕組みづくりで、AIを継続的かつ全社的に活用できる基盤を作っておきましょう。
AI領域の仕事はフリーランスへの業務委託をおすすめしたい3つの理由
AIの活用が進む中で、「社内に専門人材がいない」「正社員採用には時間もコストもかかる」といった悩みを抱えていませんか?
特にAI開発やデータ分析のような高度専門領域では、専門分野に詳しい即戦力人材が必要です。有効な選択肢の一つに、フリーランスへの業務委託があります。ここでは、AI領域の仕事こそフリーランスへの業務委託をおすすめしたい3つの理由について解説していきます。
1.フリーランスには最新技術に精通した即戦力が多いから
AI領域は技術の進化が非常に速く、企業内だけで常に最新情報をキャッチアップするのは困難です。一方、フリーランスとして活動するAIエンジニアやデータサイエンティストの多くは、業界トレンドに敏感で、新しい技術やツールを積極的に学び続ける姿勢を持っています。
そういった人材を業務委託で活用すれば、自社内にノウハウがなくても、スピーディにAI活用を進められます。さらに、複数の企業プロジェクトを経験しているため、実践的なスキルや現場対応力にも長けており、短期間で成果が出やすいでしょう。限られた期間でAIプロジェクトを加速させたい企業にとって、フリーランスは心強い即戦力として期待できます。
2.外部委託は必要な期間・業務だけ依頼できるから
フリーランスへの業務委託であれば、「必要なスキルを持つ人材に・必要な業務だけ」を依頼できます。
特に短期的かつ限定的となりやすいAI関連のプロジェクトでは、外部人材への業務委託と相性がいいでしょう。「3カ月だけ自然言語処理モデルの構築を任せたい」「社内用のAIチャットボットを立ち上げるフェーズだけ関わってほしい」といった依頼も可能です。
柔軟な体制で即戦力人材に仕事を依頼できる柔軟性が業務委託の魅力となります。
3.コストの調整がしやすいから
AI人材を正社員として採用する場合、採用コスト・給与・社会保険料などが継続的に発生し、固定費として企業の負担になります。特に、AIエンジニアやデータサイエンティストは希少価値が高く、高年収での採用が一般的なため、コストが膨らみやすいのが実情です。
フリーランスへの業務委託であれば、プロジェクト単位での契約が可能なため、コストの変動に柔軟に対応できます。固定費化しがちな人件費を変動費として扱えるため、AI領域における無理のない投資判断が可能になります。
リスクを抑えながらAI活用をスモールスタートできる点は、企業にとって大きなメリットとなるでしょう。
AIに強い人材に業務を委託したいときは、Workshipにおまかせ!
AIを活用した業務効率は、人的リソースの最適化やコスト削減、業務品質の安定など、多くのメリットをもたらします。しかし、自社にノウハウがない状態で導入を進めるのは簡単ではありません。そこでおすすめなのが、外部の専門人材に業務を委託することです。
とはいえ、「どこで信頼できる人材を探せばいいかわからない」「即戦力人材に効率よく出会いたい」といった悩みもあるでしょう。そんなときに活用したいのが、ハイスキルなフリーランスと企業をつなぐマッチングサービス「Workship」です。
Workshipでは、AIエンジニアやデータサイエンティストなど、最新テクノロジーに精通したプロフェッショナル人材が多数登録しています。必要な期間・スキルに応じて最適な人材を探せるため、プロジェクトの立ち上げから運用までがスピーディです。
以下では、Workshipの特徴を簡単にお伝えします。
独自AIのスコアリング技術で人材のスキルを可視化
プロフィール・スキル・過去に携わった仕事など、フリーランスの評価を数値化し、自社との適合性を確認できます。
成果報酬型で月額費用は必要なし
成約時に企業 ⇄ Workship ⇄ フリーランスの三者間契約をオンライン上で締結。稼働開始から14日以内の返金保証があり、直接契約によるトラブルを防止します。
検索から契約までワンストップで進められる
フリーランス検索や、無制限の求人掲載が可能。無制限のメッセージやスカウト、オンライン面談も可能。求人作成代行や稼働管理といったサポートもいたします。
AIの活用を進めたい企業は、Workshipの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
▼Workshipの詳細は、以下の動画よりご覧いただけます。
▼Workshipのサービス概要資料は、以下より無料でダウンロードできます。

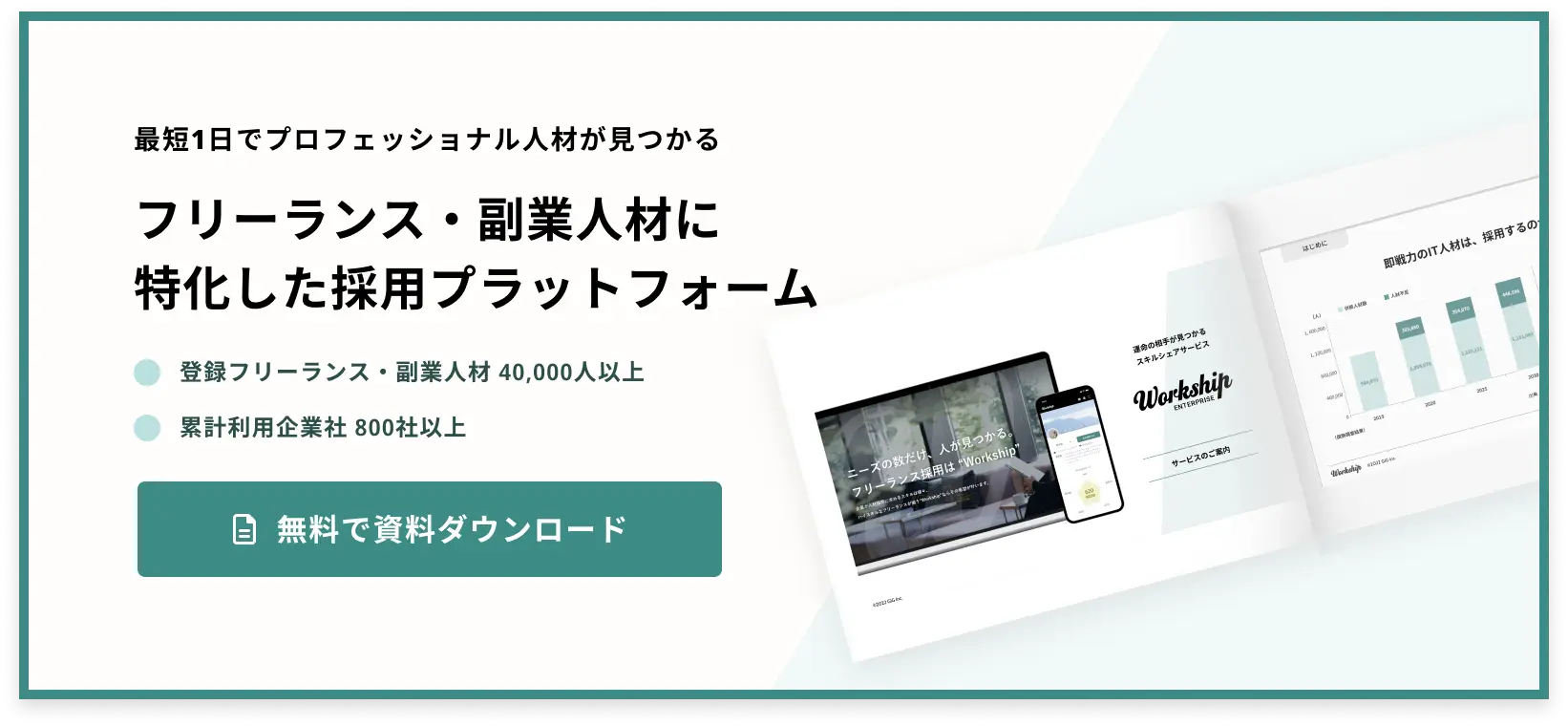 無料アカウント登録
無料アカウント登録