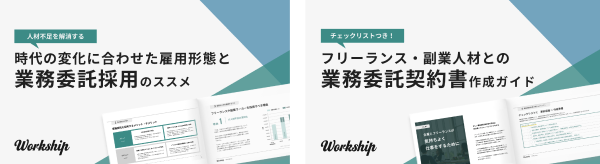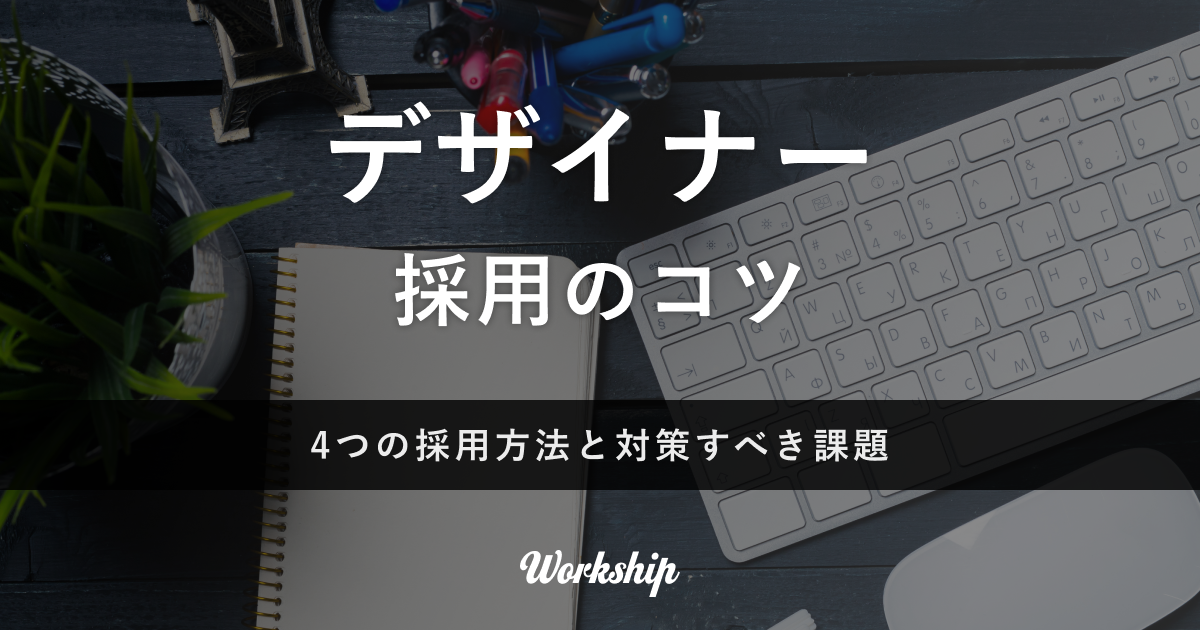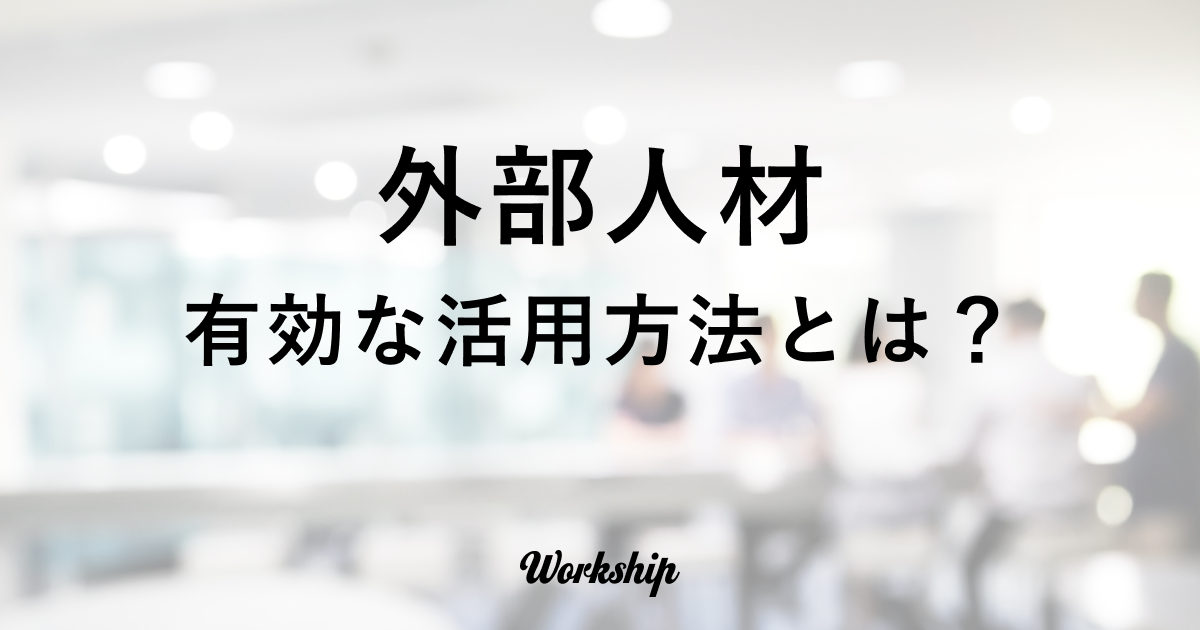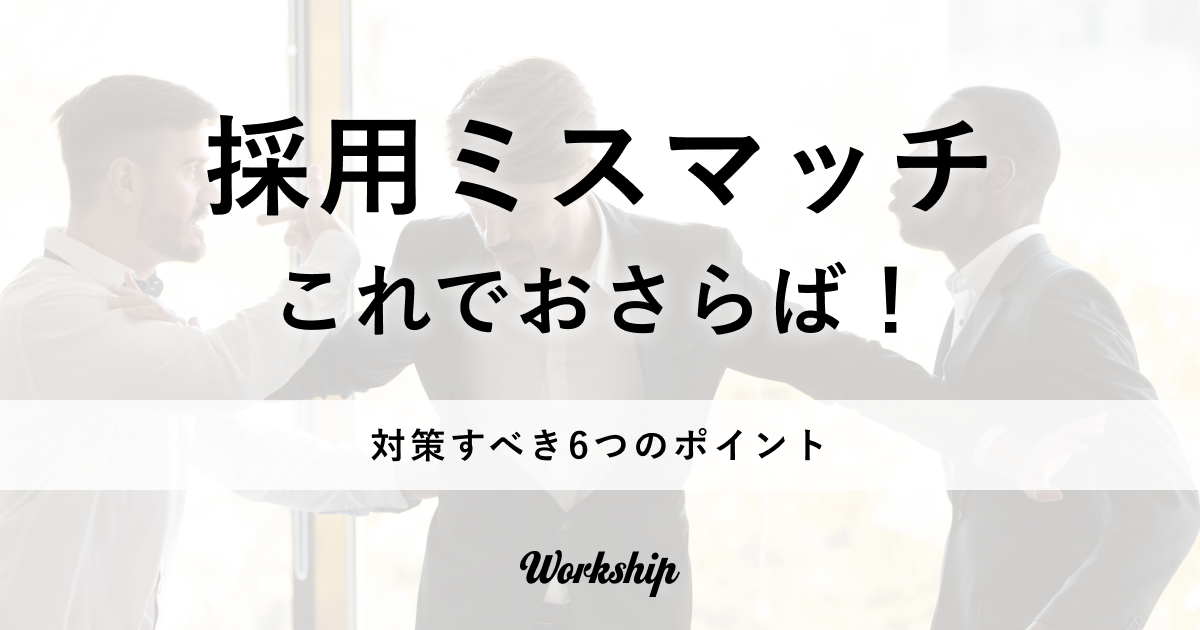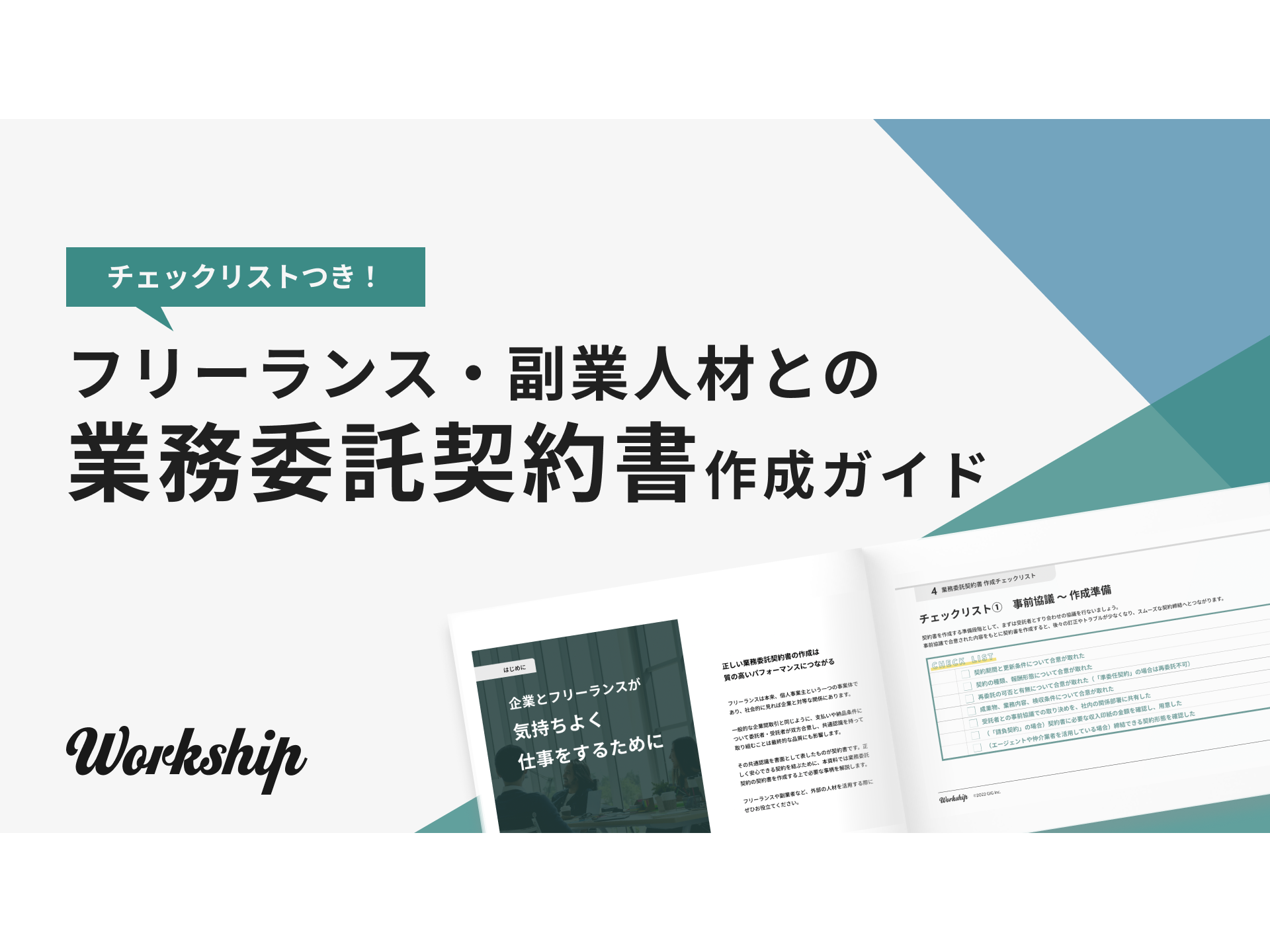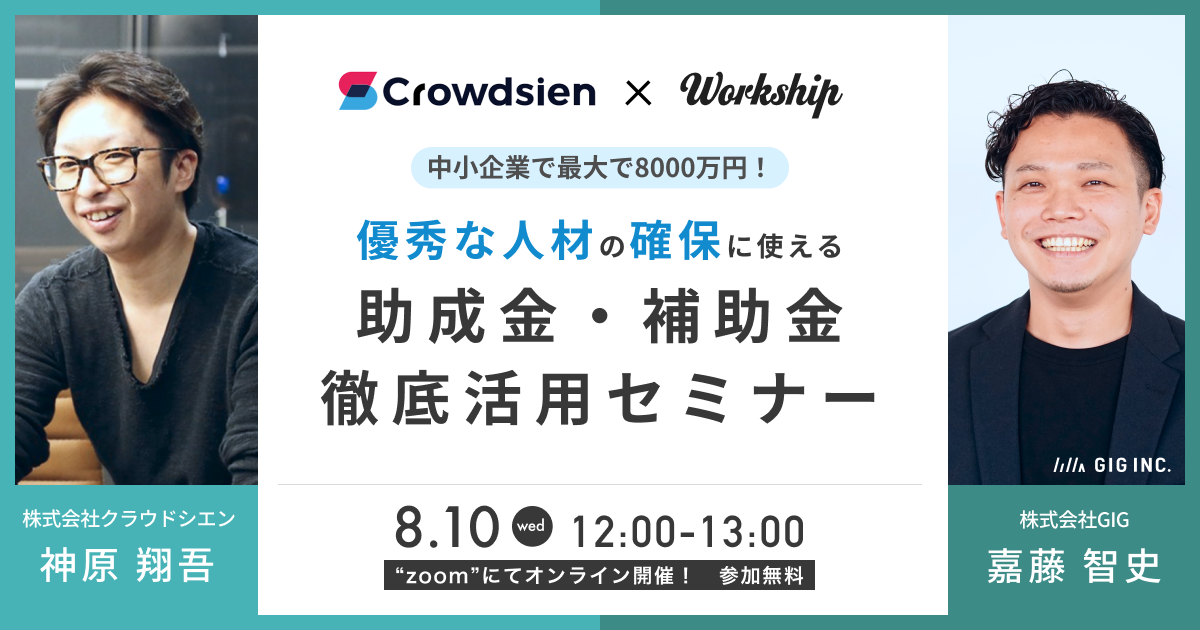「優秀すぎる人材」の中途採用は注意が必要?失敗しないためのポイント、優秀すぎる人材を採用するには
中途採用で優秀すぎる人材を得られることは、企業にとって大きなメリットです。しかし、あまりにも優秀だと周囲との摩擦が生じたり、既存社員のモチベーションを下げてしまったりと、悪影響を及ぼしてしまうケースもあります。
本記事では、優秀すぎる人材を中途採用した際の注意点をふまえ、失敗しないためのポイントをご紹介します。あわせて、中途採用で優秀な人材を獲得する方法や優秀すぎる人材にする方法についてもお伝えします。
優秀すぎる人材を中途採用した際の注意点
「即戦力の採用は無理」「即戦力なんているわけない」と感じ、中途採用に大きく期待していない企業も少なくないでしょう。しかし、ときには「優秀すぎる人材」を採用できる場合があります。
しかし、優秀すぎる人材を中途採用した際には、いくつか注意点もあります。まずは、どういった点に注意が必要かをみていきましょう。
過度に期待しない
華やかな経歴や高度なスキルを持っている優秀すぎる人材を採用できた場合、過度に期待しないよう注意が必要です。
いきなり高すぎる目標を設定したり、「すぐに成果を出せるよね」とプレッシャーをかけたりすることは、かえってパフォーマンスを低下させてしまいます。また、優秀だからと十分な研修やフォローをせず、いきなり実務を任せても、期待する実力は発揮できません。
過度な期待からプレッシャーを与えてしまったり、放置したりしては、不安や悩みを抱えてしまい、最悪のケースでは早期離職につながってしまうおそれがあります。
前職のやり方に固執する人もいる
優秀すぎる人材は、前職での成功体験から自分の仕事のやり方に強い自信を持っている場合があります。悪いことではありませんが、新しいやり方やルールに従わず、自らのやり方を頑なに貫こうとする場合は注意が必要です。
「郷に入ったら郷に従え」という言葉があるように、企業それぞれのやり方やルールがあり、既存社員はそれを守って仕事を進めています。
そうした中で郷に従わず、むしろそのやり方に不満をぶつけたり、周りの人を無視して自分勝手に仕事を進めたりする場合、周囲との摩擦が生じやすくなります。そのせいで職場やチームの雰囲気が悪くなってしまっては、全体のエンゲージメントやパフォーマンスが低下してしまうでしょう。
他の従業員のプレッシャーになる
優秀すぎる人材が入ったことで、成果を出せるようになったり、生産性が上がったりするのは良いことです。しかし、既存社員が劣等感やプレッシャーを感じ、自信を失ってしまう可能性があります。
そうならないためには、既存社員と中途社員を比較しない、既存社員の仕事や役割を奪うような采配にしないことが大切です。
中途社員の存在によって自分の存在価値がなくなったと思わせないよう、お互いのコミュニケーションを促進させ、個々の強みを補完し合える関係を構築する必要があります。
中途採用で優秀すぎる人材を採用して失敗しないためには
優秀すぎる人材は企業の戦力となってくれる一方で、前述したような注意点に気をつける必要があります。では、失敗しないためには具体的に何が必要なのでしょうか。
中途採用で優秀すぎる人材を採用した際に、失敗しないために必要なポイントをお伝えします。
理念やビジョン、会社が期待することを明確に伝える
求めるパフォーマンスを発揮してもらうには、理念やビジョン、そして会社が中途社員に期待することを明確に伝える必要があります。
経営活動の目標は、企業理念やビジョンの実現です。日々の業務を理念やビジョンの実現につなげるためには、まずそれらを伝え、理解してもらわなければなりません。理念やビジョンは考え方・行動の指針となるものであるため、そこをベースに日々アクションが取れるようになれば、おのずと理念やビジョンを体現していくことにつながります。
また、具体的な行動に落とし込むには、会社が期待していることを伝えることも大切です。中途社員も自分に求められていることが理解できれば、会社の方針とズレることなく、主体的に行動できるようになるでしょう。
優秀さだけに固執せず人間性も評価する
華やかな経歴や実績、高度なスキルや資格を有しているなど、条件面での優秀さだけをみて採用しないよう注意しましょう。
いくら優秀でも周囲の人とうまくやれなかったり、実力はあるが仕事を最後までやり切らなかったりと、どこかで問題が発生してしまう可能性があります。
もちろん条件面も大切ですが、責任感の強さや誠実さなど、人間性も見落としてはならない重要なポイントです。
自社のやり方やルールを遵守してもらう
中途社員が自己流のやり方を押し切ろうとすると、周囲との摩擦が生じてしまい、チームワークを乱してしまうおそれがあります。そのため、中途社員にはまず社内ルールや自社の仕事の進め方を伝え、遵守してもらうことが大切です。
しかし、中途社員が自らのやり方を捨てる必要はありません。その経験や知識を自社の業務に反映させることで、業務効率や生産性が高まる場合もあるでしょう。
中途社員を抑圧するのではなく、良い部分は組織に取り入れられるよう、組織側が受け入れる体制をつくることも大切です。
社風や価値観がマッチするかも確認する
人間性とあわせて、社風や価値観がマッチするかも重要なポイントです。社風や価値観がマッチする人材は理念やビジョンへの共感度も高く、職場にも馴染みやすいでしょう。能力の高さも相まって、早期にパフォーマンスを発揮し、期待以上の成果を出してくれる可能性も高まります。
社風や価値観がマッチしないと、いくら能力が高くてもなかなかパフォーマンスを発揮できなかったり、居心地の悪さから早期離職するリスクもあります。
適性検査や面接では、候補者の価値観や考え方も把握し、カルチャーフィットするかもしっかりとチェックしてみてください。
中途採用で優秀すぎる人材を採用するには「採用基準」が大切
優秀すぎる人材がそれゆえに組織やチームに悪く作用してしまう部分もありますが、それらは対策が可能です。であれば、企業はできるだけ「優秀すぎる人材」を採用したいはずです。
優秀すぎる人材を採用するには、採用基準が大切となります。採用基準は採用のミスマッチが防げ、統一した評価が可能になることで採用活動の効率化にも有効です。
ここでは、採用基準を構成する要素や設定方法を解説します。
採用基準を構成する3要素
採用基準を設定する上で、下記3つの構成要素を把握しておくことがポイントです。3つの要素から必要な項目を洗い出していくことで、求める人材を採用するための効果的な採用基準が設定できます。
①人格
人格は動機や価値観、信念、先天的な資質や才能といった要素です。その人の考え方や価値観を形成する素であり、社風や価値観とのマッチ度を見極めるために重要なポイントです。
人格は潜在的なものであるためその人も自覚していない場合が多く、第三者からしても捉えにくいものです。そのため、人格を把握するには選考時に下記のような内容を質問をしてみましょう。
・仕事を通じてどうなりたいか、どう成長していきたいか ・どのようなことにやりがいを感じるか ・今後のビジョン ・仕事観 |
②行動特性
行動特性はコンピテンシーとも呼ばれるもので、その人の行動パターンを示すものです。行動そのものではなく、行動の動機や性格といった要素に着目するため、可視化しにくいポイントですが、適性検査などからある程度は把握できます。
自社で活躍できる優秀な人材であるかを判断する手法として、コンピテンシー評価があります。実際に活躍している人材の行動特性と類似しているかを評価基準とする方法です。実例に基づく基準となるため、採用基準も精度も高まります。
③知識・スキル
知識やスキルは、優秀であるかをもっとも判断しやすい要素です。学習や経験によって習得できるものであり、今後さらに高めることもできます。
中途採用では特に重視されることが多く、即戦力となるかを判断しやすいポイントです。採用基準を設定する上では、入社後活躍してもらうために必要なスキルや経験、その程度を明らかにしておく必要があります。
採用基準の設定方法
では、採用基準の具体的な方法についてみていきいます。
①求める人材像を明確にする
まずは求める人材像を明確にします。優秀すぎる人材の獲得を目指すのであれば、「優秀すぎる」に求めるスキルや経験のレベル、人格や行動特性の具体的な要素を洗い出しましょう。
「優秀」や「即戦力」の度合いや定義は企業によって異なるため、自社の状況をふまえてしっかりと明確にしていきます。
②評価項目を設定する
求める人材像であるかを判断するための具体的な評価項目を設定します。評価項目は少なすぎても多すぎても、評価が難しくなってしまいます。
求める人材像の条件に優先順位をつけ、「必ず満たしてほしい条件」と「あると良い条件」に分類することがポイントです。
中途採用を優秀すぎる人材にする方法
中途採用で得た人材を活かせるか、優秀な人材にできるかは、企業に委ねられています。中途社員を優秀すぎる人材にするには、以下のような方法で育成していくことが有効です。
オンボーディングを実施する
オンボーディングとは、新しく組織に加わった人材に職場環境に慣れてもらい、定着を図るためのさまざまな取り組みです。
オンボーディングの取り組み例 | |
入社前 | 入社後 |
・内定者交流会 ・既存社員との懇親会 ・社内見学 ・社内報の送付 など | ・ランチ会 ・OJT ・研修 ・歓迎会 ・1on1ミーティング など |
オンボーディングでは業務面のサポートも行いますが、具体的なスキルの習得に焦点を当てるOJTとは異なり、企業文化や職場環境に早く馴染むことを目的としています。
オンボーディングの実施にあたって具体的な目標と活動計画を策定し、継続的なサポートを提供していきましょう。
研修をおこなう
オンボーディングの取り組み例にもあるように、研修の実施も有効な方法です。中途社員向けに実施する研修のカリキュラム例には、下記のようなものがあります。
・企業理念、ミッション ・社内ルール ・仕事の進め方 ・業務に必要な専門知識 ・キャリアデザイン ・コンプライアンス など |
研修は企業文化や社内ルールを理解するために必要です。入社後いきなり業務を任せるのではなく、まずは研修を実施しましょう。
継続的にフォローする
継続的なフォローは、中途社員の早期戦力化のために不可欠です。中途社員ならとくにフォローせずに良いだろうと放置しては、思うようなパフォーマンスを発揮できません。新しい環境になれば、当然わからないことはたくさん出てきます。
早期に業務を覚え、効率的に進めるためにも、周囲がしっかりとフォローすることが大切です。
誰に聞けば良いかわからないという場合もあるため、バディをつくることもおすすめです。バディはメンター役としても機能してくれます。業務面のサポートだけでなく、悩みや不安に対するサポートも提供し、中途社員の精神的ストレスの軽減や定着化に役立ちます。
まとめ
中途採用で期待以上の仕事ぶりを発揮してくれる優秀すぎる人材を獲得できる場合もあります。しかし、採用時に能力以外の面を見極めなかったり、入社後の研修やフォローが十分でないと、組織に悪い方向で影響してしまう場合があります。
優秀すぎる人材を採用できることは、企業にとって大きなメリットです。優秀すぎる人材と既存社員が互いに補完し合える関係を構築することで、生産性や企業力の向上につながります。
また、採用時に優秀すぎなくとも、採用後の適切な育成とフォローにより期待以上の人材へと成長してくれる可能性も十分にあります。中途採用のポテンシャルをしっかりと活かすためにも、適切なサポートを提供しましょう。
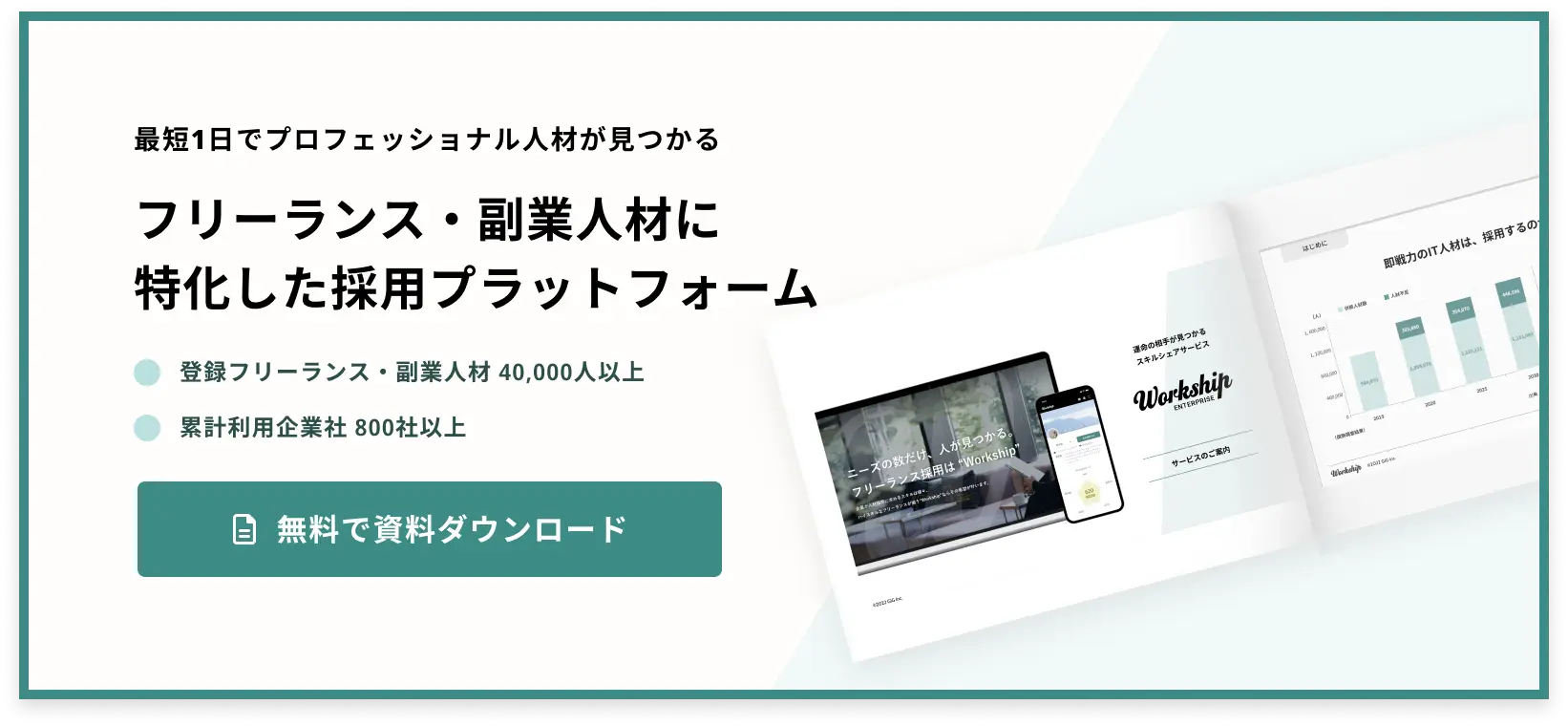 無料アカウント登録
無料アカウント登録