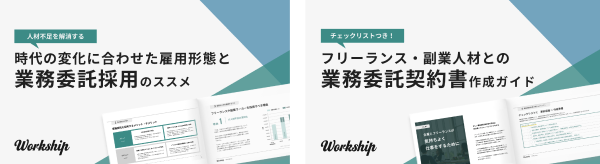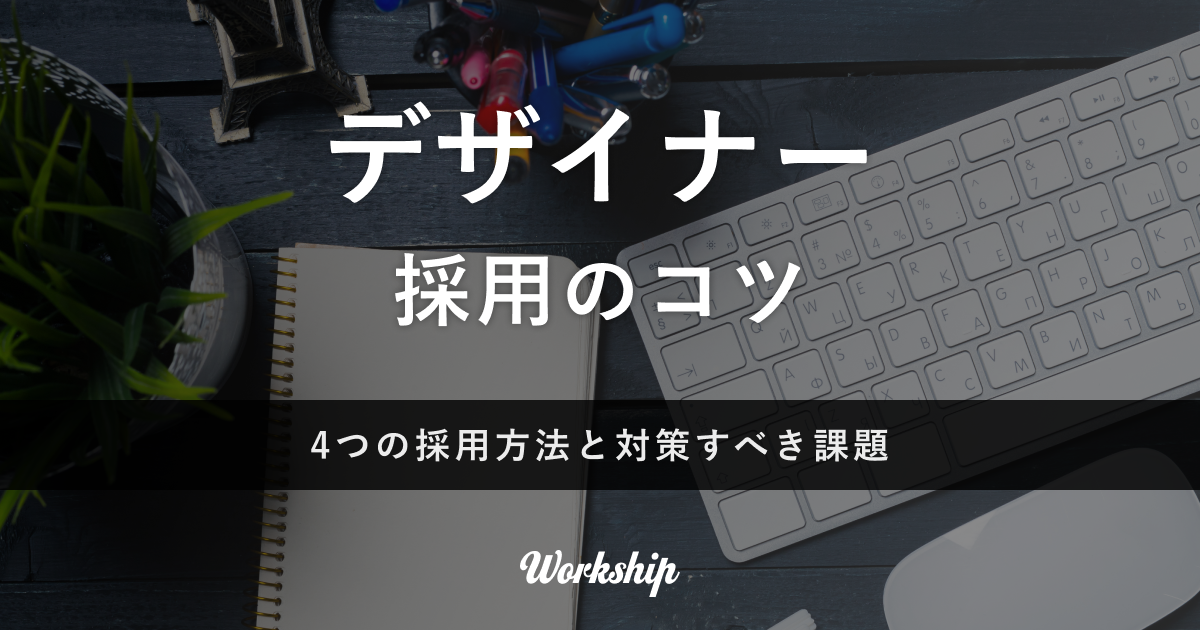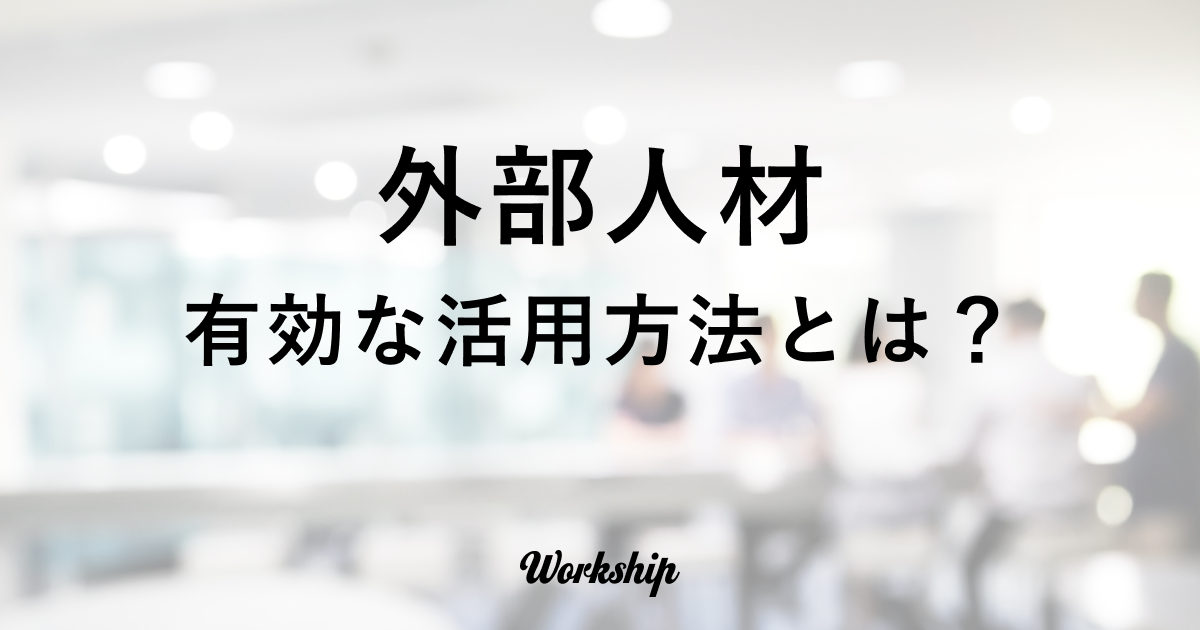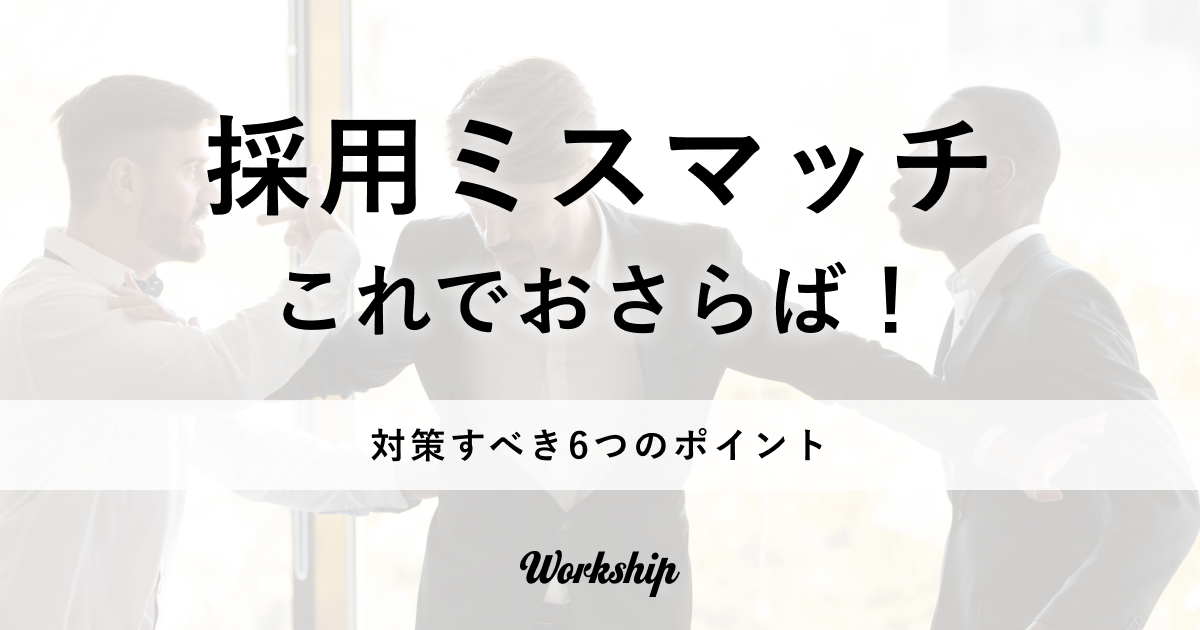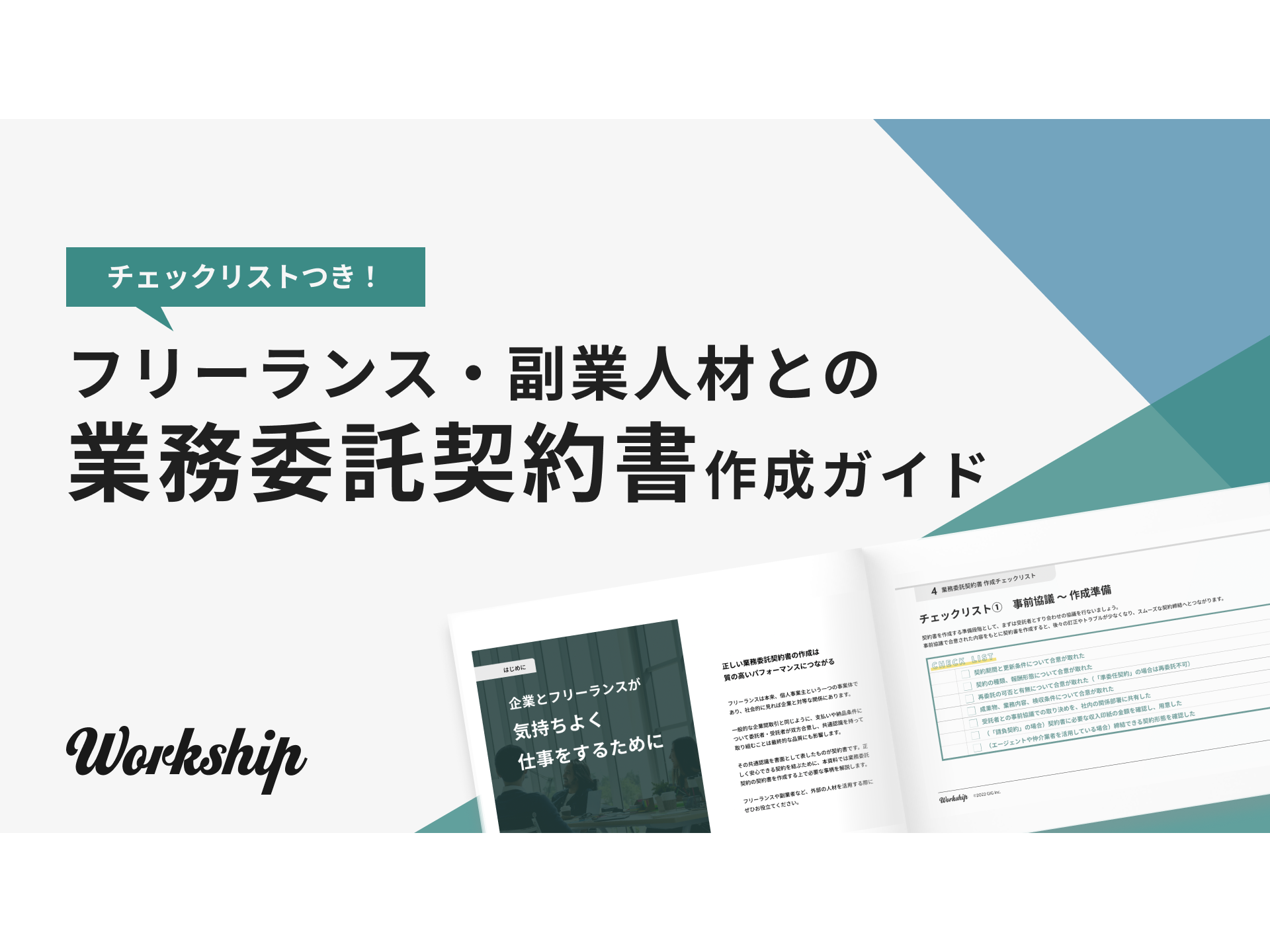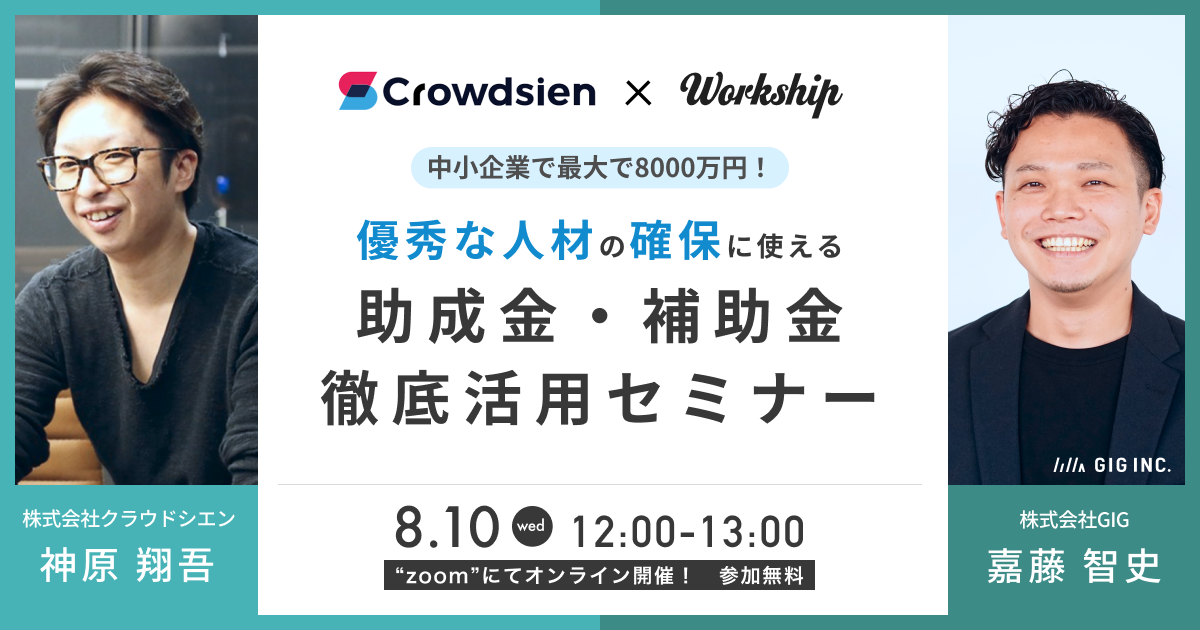中途採用は研修なしでいい?ダメな理由と研修実施の目的・メリット、研修の内容や実施方法を紹介
「中途採用=即戦力」と考え、入社後に研修を実施しない企業もあるでしょう。しかし、中途採用でも研修やフォローは必要です。適切な育成やフォローをせず放置しては、早期退職に発展し、せっかく採用した人材を失ってしまいます。
本記事では、中途採用の研修について、研修なしがダメな理由や研修を実施する目的・メリット、研修の内容や実施方法などを詳しく紹介します。
中途採用の研修なしがダメな理由
中途採用はビジネスパーソンとしての社会経験があり、同業種・職種からの転職であれば、実務経験もあります。そのため、入社後すぐに即戦力として活躍してくれると考えている企業は多いでしょう。
しかし、中途採用でも入社後は研修が必要です。中途採用への研修の重要性を理解するため、まずはその理由についてみていきます。
中途採用でも教育は必要だから
「中途採用=即戦力」という考えは間違いではありませんが、「即戦力になり得る人材」と認識する方が正確でしょう。なぜなら、同業種・職種からの転職であっても、企業によって任されていた仕事内容やその範囲、教育レベルや業務の進め方は全く異なるからです。
社会人としてのマナーや常識、職種に関係なく必要とされるポータブルスキルに関しては教育の必要はありませんが、業務の進め方や企業理念のようなカルチャー面に関する教育は必要です。
中途採用の放置が退職につながるから
実務経験やスキルがあるからと、研修やフォローをせず放置している状態では、早期退職に発展するリスクが高まります。
同じ業務でもやり方が違うことでスムーズに進められなかったり、疑問点があっても誰に確認すればいいかわからなかったりする状態では、仕事への意欲も徐々に失われてしまいます。また、組織の一員としての自覚が持ちにくく、孤立感・疎外感が高まるおそれもあります。
中途採用に研修を実施する目的
では、中途採用にはどういった目的で研修を実施するのでしょうか。その目的を詳しくみていきます。
理念やビジョンを理解してもらうため
中途人材に期待する活躍をしてもらうためには、企業理念を理解してもらうことが重要です。なぜなら、企業理念は考えたり行動したりする際の指針となるものであるからです。企業理念を実現するための行動ができないと、企業のビジョンの体現にはつながりません。
この点については新入社員と同程度の理解度となるため、業務に取り組む前に理念やビジョンについて共有する機会を研修として設けるようにしましょう。
業務内容や役割を理解してもらうため
同じ業種・職種であっても、企業にはそれぞれのやり方や考え方があります。その点を理解してこそ、中途人材がもつ実力や経験を発揮できるようになります。
また、自分が配属される部署が社内でどういった立ち位置にあるのか、その業務はどう事業に関連しているのかという点から、自分のポジション・役割を理解することも必要です。
この点を理解するには、業務前に組織の全体像について理解する機会を設けることが有効であり、研修として実施できると良いでしょう。
新しい環境に馴染んでもらうため
中途採用は新入社員のように同期がおらず、孤独感を感じやすいものです。新しい環境で新しい人たちと仕事していくことは、少なからず精神的な負担やストレスになることもあります。
研修は同時期に入社した人たちや既存社員との交流の場にもなります。ともに研修を受けることでつながりができ、組織への帰属意識が醸成されるきっかけとなるでしょう。
中途採用に研修を実施するメリット
中途採用に研修を実施することは、下記のようなメリットがあります。
・中途人材の早期退職を防げる ・早期に戦力化できる ・中途人材の孤独感を解消できる |
目的とあわせて、メリットも押さえましょう。
中途人材の早期退職を防げる
中途人材が退職を検討する原因の一つに、不十分な教育体制が挙げられます。
実務経験やスキルがある人なら教育がなくてもある程度のことはこなせるかもしれませんが、仕事の進め方やルールがわからないと効率的に業務は進められません。研修も行われず、現場でのフォローもない状態ではなかなか本領を発揮できず、このまま働き続けることに不安を覚えてしまうでしょう。
そうした不安を解消し早期退職を防ぐには、教育体制を整え、その一環として研修を行うことが重要です。
早期に戦力化できる
研修によって理念やビジョン、業務の進め方を理解できれば、企業が期待する行動を取れるようになります。これらが不十分な状態では、本来ある実力や経験を発揮するのが難しく、パフォーマンスが出せないことで中途人材のモチベーションも下がってしまうでしょう。
理念やビジョン、業務の進め方や自身の役割を理解してもらうこと、そして環境に慣れてもらうことは、人材が活躍するためのベースとなるものです。研修はこのベースを整えるために役立ちます。
中途人材の孤独感を解消できる
「同期」という存在がいない中途人材は、入社して初めの頃はどうしても孤独感や疎外感があります。また、組織の一員という自覚も持ちにくく、帰属意識やエンゲージメントも醸成されにくいでしょう。
研修は同時期に入社した人や既存社員との交流の場ともなり、社内とのつながりをつくる場としても活用できます。早くに職場環境に慣れられれば、パフォーマンスも発揮しやすく、定着率も高まります。
中途採用研修のカリキュラムの具体例と実施方法
では、中途採用の研修はどういった内容をどのような方法で実施すればよいのでしょうか。ここでは、実際に研修を企画する際に参考にできる、カリキュラムの具体例や実施方法をご紹介します。
カリキュラムの具体例
中途採用研修で実施すべきカリキュラムの具体例として、下記が挙げられます。
・企業理念、ミッション ・社内ルール ・仕事の進め方 ・業務に必要な専門知識 ・キャリアデザイン ・コンプライアンス など |
理念やビジョン、社内ルールや仕事の進め方に関する研修は、業務に入る前に実施することがおすすめです。どのタイミングで実施するかは企業が自由に決めて問題ありませんが、入社前あるいは入社後の早い段階で実施できると良いでしょう。
実施方法
研修の主な実施方法には、講習形式の集合研修やオンラインで受講できるeラーニングがあります。
企業理念や社内ルール、仕事の進め方といった独自の内容は、集合研修となる場合が多いでしょう。企業によっては研修を動画化し、eラーニングとして提供しているケースもみられます。
eラーニングは時間や場所の制限なく研修が実施できる点でメリットがあります。しかし、研修は交流の場としても機能するため、eラーニングだけで完結させないことがポイントです。
研修期間はどれくらい?
必要な研修期間は人によってさまざまですが、一週間ほどで実施する企業が多いでしょう。ただし、一度研修を受けたからと、その内容がすぐに定着するわけではありません。実務を通して理解していくことを考えると、研修が必要な期間は数ヶ月〜1年ほどとなるでしょう。
個人の習得速度や元のスキルレベルによっても異なるため、個々のレベルやペースに合わせてカリキュラムを組んでみてください。
中途採用の育成・フォローのポイント
中途採用の研修は、育成・フォローの手段の一つです。中途採用の研修の効果を高め、早期に活躍する人材へと育成するには、どういったポイントを意識すれば良いのでしょうか。
ここでは、研修を含む育成・フォローのポイントについてお伝えします。
バディをつくる
業務に入る前の研修期間が終了したら、その後は現場でOJTを受けながら継続的な育成やフォローを受けることになります。この時、OJTを担当する人以外にもバディをつくっておくことがおすすめです。
バディには業務に関する相談だけでなく、悩みや不安なども密なコミュニケーションが取れる存在です。仕事以外のことも気軽に話せる存在がいることで精神的な負担や不安が軽減され、新しい環境にも馴染みやすくなります。
バディには、比較的年の近い先輩社員を選ぶと良いでしょう。
研修以外でも定期的なフォローを行う
入社後一週間ほどの研修ですべての育成やフォローが終わりと認識しないよう注意が必要です。研修をしたからとその後を放置しては、結局業務のやり方が十分に身に付かなかったり、職場に慣れなかったりして、退職を検討してしまうおそれがあります。
OJTにより実務のフォローを行いつつ、定期的な面談を実施し、現状を把握することが重要です。入社後のフォロー体制が充実していることで、中途人材も早期に実力を発揮できるようになります。
情報やナレッジを共有する
研修で情報を得るだけでは不十分です。実際に現場でアウトプットしていく中で、新たな疑問がたくさん出てきます。この時、人事や教育担当者、チーム内の人に質問してばかりになると、双方にとって負担となり、業務効率が低下してしまう場合があります。
そのため、すべてを質問する必要がなくなるよう、情報やナレッジを一元化し、共有することもポイントです。知りたい情報を自分でスムーズに引き出せる環境があれば、質問したり、回答したりする手間が省け、生産性の向上にも有効です。
まとめ
中途採用の人材にも研修は必要です。研修を実施し、その後のフォローもしっかりと行うことで、早期にパフォーマンスを発揮できるようになります。
中途採用だからと研修やフォローをせず、放置していては、新しい環境に慣れられず、業務への理解度も高められないことで、早期に退職してしまうリスクも高まります。中途採用は即戦力となり得る貴重な人材であり、その実力を活かせるかは企業の対応次第です。
本記事を参考に中途採用への研修の必要性し、適切な研修を企画してみましょう。
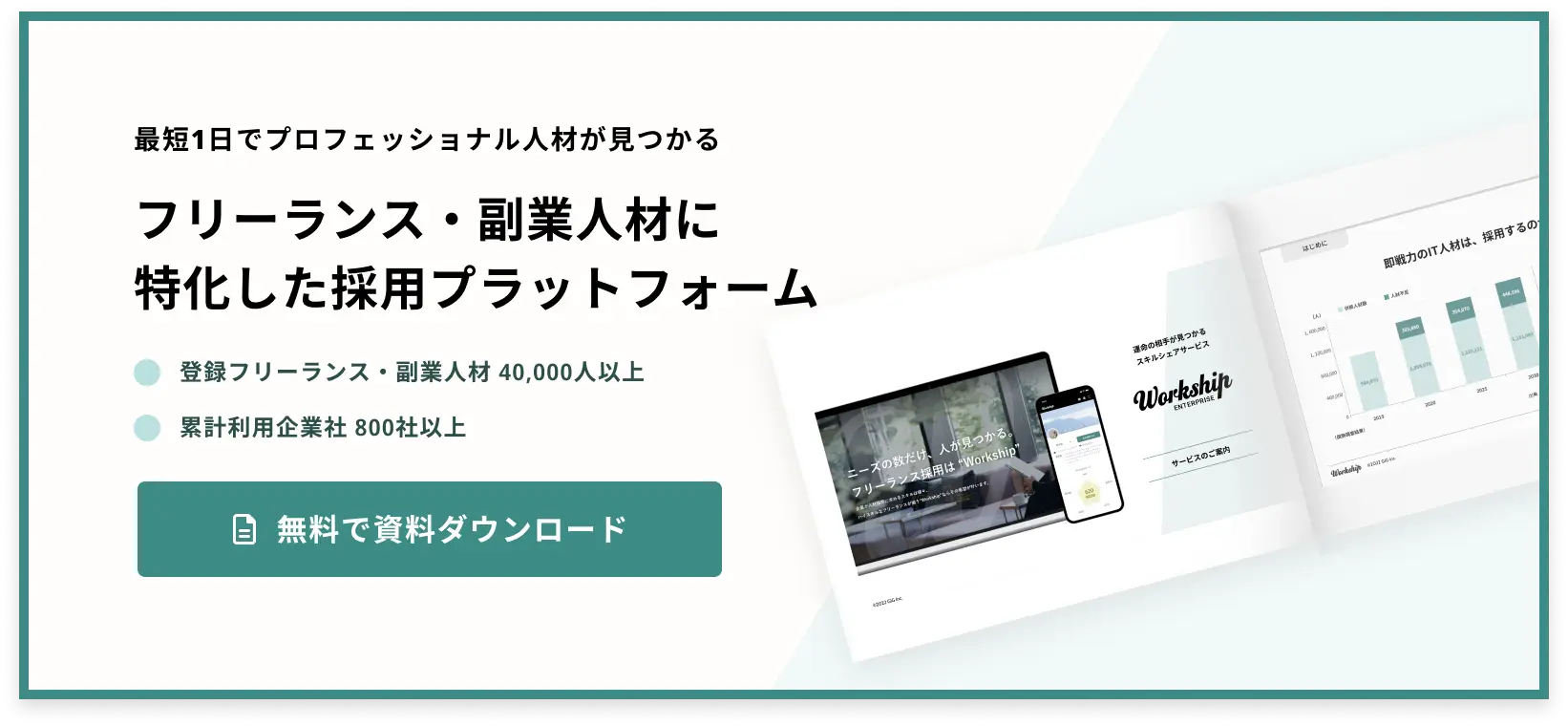 無料アカウント登録
無料アカウント登録