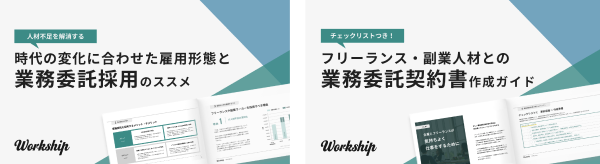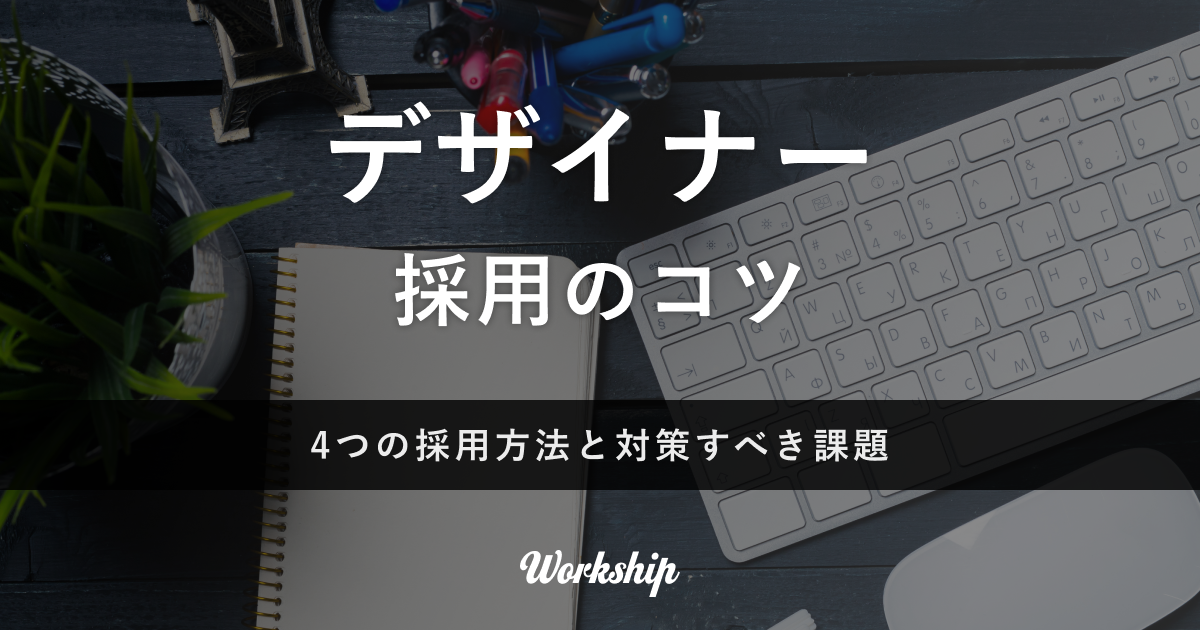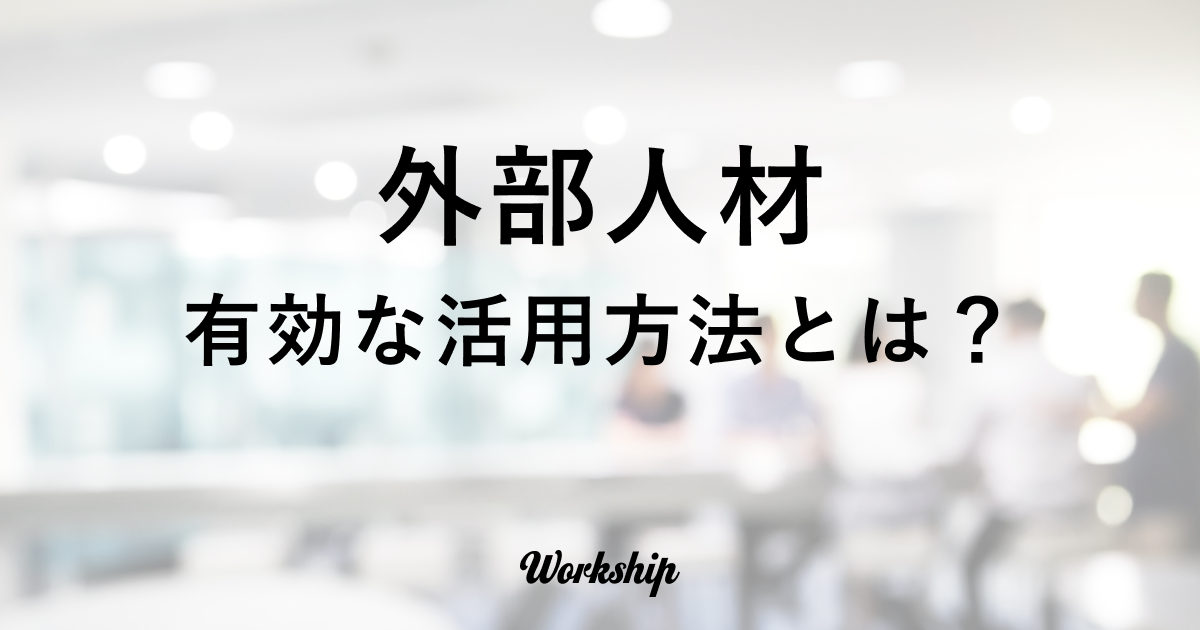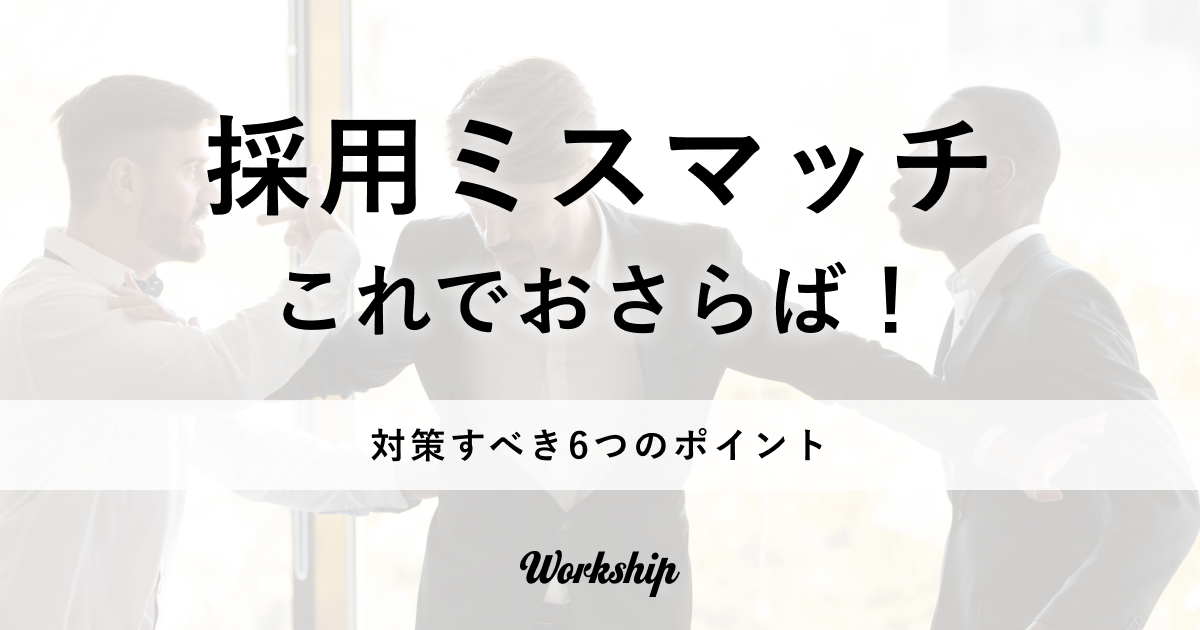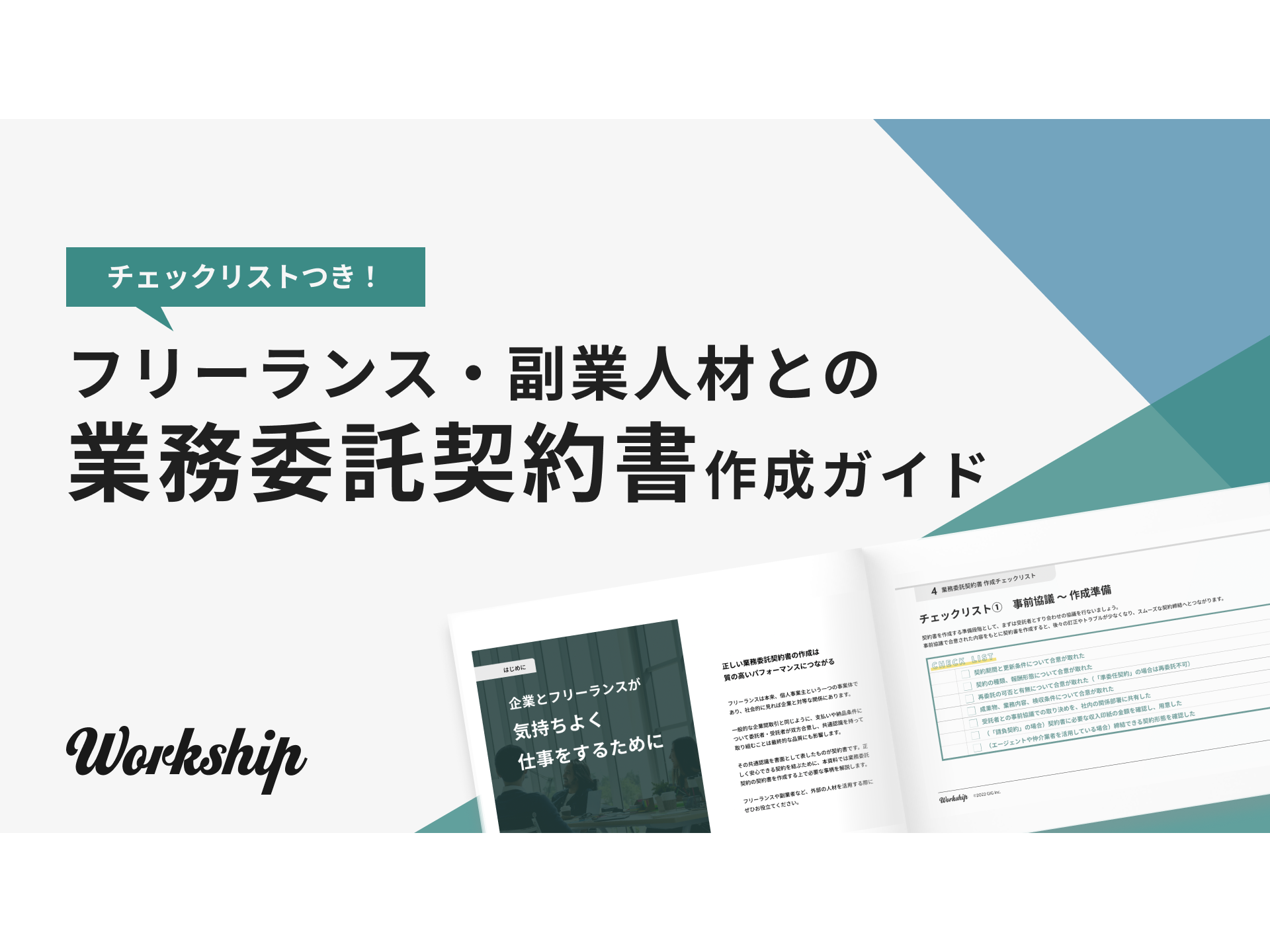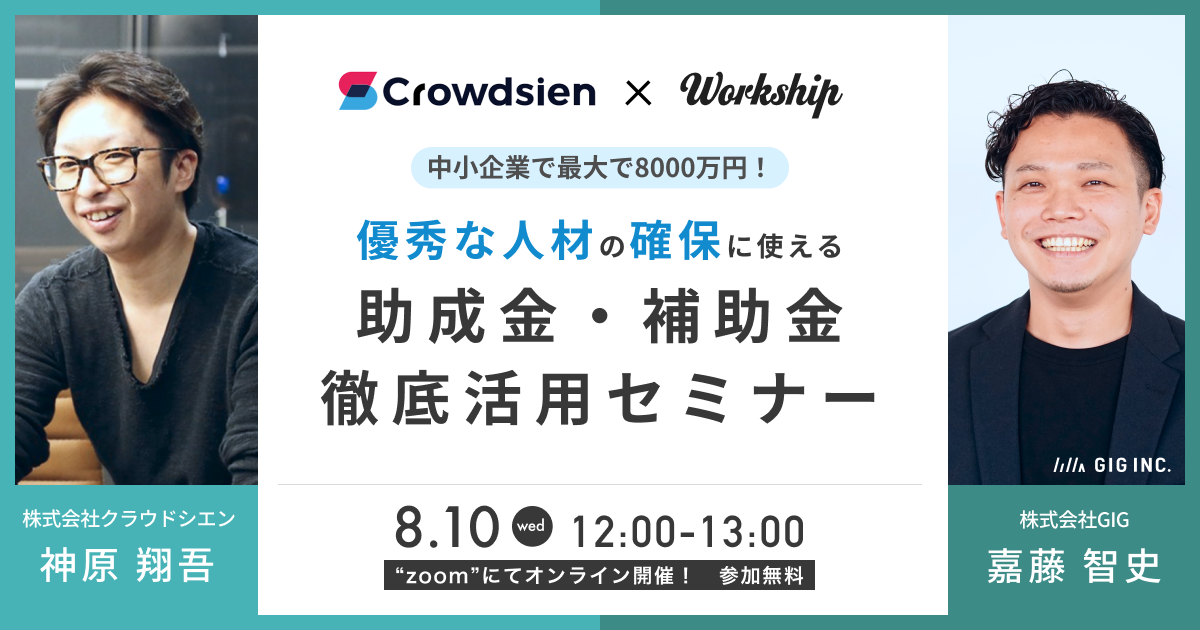契約社員とフリーランスの違いとは?メリット・デメリットや採用の判断基準を詳しく解説
企業が正社員以外の人材を採用する際、契約社員とフリーランスのどちらを選ぶべきか悩むことはありませんか?
両者はそれぞれ、雇用形態や契約条件、期間やコストなどに大きな違いがあります。
本記事では、契約社員とフリーランスの違いやそれぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。
人材確保のために人を雇いたいけれど、契約社員かフリーランスで悩んでいるという採用担当者の方はぜひ参考にしてください。
フリーランスと契約社員の違いとは?
ここからは、フリーランスと契約社員の違いを4つに分けて解説します。
契約の種類
社会保険
福利厚生
勤務する時間・場所
それぞれ詳しく見ていきましょう。
契約の種類
フリーランスと契約社員は、契約の種類が異なります。
それぞれの契約の種類は以下のとおりです。
契約社員:雇用契約
フリーランス:業務委託契約
契約社員は雇用契約を結ぶことで会社の従業員として雇用され、一定の雇用期間が設定されるのが一般的です。
一方フリーランスは、業務やプロジェクトごとに業務委託契約を結ぶため、会社との直接的な雇用関係はありません。
さらにフリーランスの業務委託契約には、成果物や責任範囲などによって以下の3種類に分かれます。
契約の種類 | 目的 | 成果物の有無 | 具体例 |
請負契約 | 仕事の成果物を納品すること | 有 | Webサイト制作 建築工事 |
委任契約 | 依頼された業務を遂行すること | 無 | 弁護士業務 税理士業務 |
準委任契約 | 専門的な業務や作業を行うこと | 無 | ITコンサルティング システム運用 |
フリーランスと契約社員は、契約によってできる業務の範囲も異なりますので、事前にどんな業務を任せたいのかなど、目的を決めておくとよいでしょう。
社会保険
契約社員とフリーランスは、契約の種類が異なることから、保険の有無も変わります。
そもそも社会保険とは、企業に勤める正社員や、一定条件を満たした非正規社員が加入する公的な強制保険制度です。
契約社員の場合であれば、企業に雇用されている非正規社員として以下の条件が満たされていれば社会保険に加入することができます。
週の勤務時間が20時間以上
給与が月額88,000円以上
2ヶ月を超えて働く予定がある
学生ではない
引用:[厚生労働省]
契約社員は社会保険として厚生年金や健康保険、雇用保険に加入できるため、老後の保障や病気・失業時のサポートがある点が魅力です。
一方でフリーランスは、企業と雇用契約を結んでいないため社会保険の対象外です。
社会保険に加入できない代わりに、国民健康保険に自力で加入が求められます。
契約社員のように厚生年金や雇用保険の加入もできないため、もしもに備えて自分に必要な保険を用意する必要があり、保険料などのコストがかかります。
企業側が契約社員とフリーランスを比較する際、社会保険の面ではフリーランス人材の方がコストを押さえることができるでしょう。
福利厚生
福利厚生は、企業と雇用契約がある人材に与えられる制度です。
つまり契約社員は企業の福利厚生を利用できますが、フリーランスには基本的に福利厚生がありません。
契約社員が受けられる福利厚生には、法律で定められている法定福利厚生と会社独自の法定外福利厚生の2種類があり、それぞれの例は以下のとおりです。
種類 | 内容の事例 |
法定福利厚生 | 健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 介護保険 子ども・子育て拠出金 |
法定外福利厚生 | 通勤・住宅手当 人間ドックの費用 サークル活動・交流会 結婚祝い金・出産祝い金 ベビーシッター料金の補助 リフレッシュ休暇 |
しかし、フリーランスは企業の従業員ではないため、福利厚生の対象外となります。
福利厚生が充実している企業であれば、契約社員の採用にもメリットに働くでしょう。
勤務する時間・場所
契約社員は企業の勤務時間や勤務地に従いますが、フリーランスは企業との調整次第では好きな場所や時間で働くことが可能です。
なぜならフリーランスは企業とプロジェクト単位で仕事をするため。
たとえば、契約社員の勤務時間は「9時〜18時」など、企業によって決められていることが多く、残業が発生することもあります。
一方でフリーランスであれば、成果物の提出が目的の場合には納期までに成果物を完成させればよいため、日中に休んで夜に作業することも可能です。
もちろん、フリーランスだから常に自由な時間に働けるというわけではありませんが、勤務地や時間の自由度は契約社員よりは高いといえるでしょう。
契約社員を雇うメリット・デメリット
企業が人材を採用する際、契約社員という雇用形態を選択することには、メリットとデメリットどちらもあります。
ここでは、契約社員を雇う際のメリットとデメリットを詳しく解説します。
メリット | デメリット |
自社の社員として雇用・教育できる 短期的な人員確保として活用できる | 一定期間後は申出によって正社員登用が必要になる 雇用におけるコストがかさむ |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
メリット1|自社の社員として雇用・教育できる
契約社員は、フリーランスと比較して、自社の社員としての教育がしやすい点が魅力です。
なぜなら契約社員は企業の一員として働くため、入社した瞬間からチームに所属しながら、企業の慣習や人間関係を学びつつ、長期的な戦力として育てられるからです。
業務に慣れた契約社員は、正社員に登用することも可能です。
実際に新規事業の立ち上げ時に契約社員として採用し、業務に慣れた後に正社員登用する事例もあります。
長期的に自社で活躍する人材を今から育てたい企業にとって、契約社員はメリットといえるでしょう。
メリット2|短期的な人員確保として活用できる
契約社員は、必要なタイミングや期間で人材の確保ができる点が魅力です。
なぜなら契約社員を雇う際、企業側で契約期間を決めることができるからです。
たとえば年度末の決算業務やイベントの開催時期など、一時的に業務量が増えるタイミングに半年から1年程度の期間に絞って契約社員を採用すれば、必要な期間に十分な人材を確保できるでしょう。
新しいプロジェクトを立ち上げる際に、専門スキルを持つ契約社員を採用する方法も効果的です。
短期的な雇用を目的にしていますが、自社に必要な人材だと判断すれば、契約を更新することもできるため、調整のしやすさが魅力といえるでしょう。
デメリット1|一定期間後は申出によって正社員登用が必要になる
契約社員は、労働基準法により一定期間の雇用後は本人の希望によって正社員として登用しなければいけません。
労働基準法によると、有期雇用契約が通算5年を超えると、労働者が希望すれば無期雇用(正社員)に転換する権利を得る「無期転換ルール」があります。
”契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。”
引用:[無期転換申込権の発生・行使の要件等について|厚生労働省]
つまり同じ契約社員を5年以上継続して雇用した場合、その社員が無期雇用を希望すると、企業は正社員として採用する義務が発生するということ。
想定外の採用が増えれば、企業の雇用計画に影響を与える可能性があります。
契約社員の長期雇用は、将来的に正社員登用を検討しなければならない点を考慮する必要があるでしょう。
デメリット2|雇用におけるコストがかさむ
契約社員は企業と雇用関係があるため、企業側が契約社員に対して社会保険料や福利厚生の負担が発生します。
厚生労働省の調査によると、企業が1ヶ月の常用労働者1人あたりにかけている福利厚生の費用は以下のとおりです。
法定福利費:50,283円
法定外福利費:4,882円
引用:[令和3年就労条件総合調査の概況]
契約社員は一定の労働時間を超えると社会保険の適用対象となるため、企業は雇用保険や厚生年金などの費用を負担する必要も出てきます。
さらに福利厚生も適用される場合もあり、短期間の雇用であっても一定のコストが発生します。
フリーランスを雇うメリット・デメリット
ここからは、フリーランスを雇う際のメリット・デメリットについて詳しく解説します。
メリット | デメリット |
プロジェクトごとに即戦力を確保できる 社内リソースを使わず業務に従事できる | 自社のノウハウが蓄積されない 要件定義やマニュアルの設定が手間 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
メリット1|プロジェクトごとに即戦力を確保できる
フリーランスを採用する大きなメリットは、専門スキルを持ち即戦力になる人材を、必要なタイミングで確保できることです。
フリーランスは特定の分野に特化したスキルを持ち、さまざまな企業と業務委託契約を結んで仕事をします。
プロジェクトごとで仕事をすることが多いため、幅広い企業とどういった流れで仕事をするかなどの経験もノウハウも豊富です。
そのため、特定のプロジェクトでフリーランスを採用した場合は、一定の情報共有や意見のすり合わせをするだけで、研修の時間をかけずにすぐに業務を開始できる点が大きなメリットといえるでしょう。
社内にないスキルを持つ即戦力を確保したい場合におすすめです。
メリット2|社内リソースを使わず業務に従事できる
フリーランスを採用するメリットは、企業の人材リソースを消費せず、独立した形で業務を遂行できる点です。
通常、企業が正社員や契約社員を採用すると、入社手続きや研修、福利厚生などのコストが発生します。
しかし、フリーランスは業務委託契約であるため、契約の手続きに必要な手間はほとんどなく、業務の外注が可能。
たとえばECサイトのコンテンツ作成をフリーランスのライターに委託する場合、社内のマーケティングチームのリソースを使わずに記事を作成できます。
社内リソースを消費せずに業務を進められるため、人材不足で悩む企業に向いているでしょう。
デメリット1|自社のノウハウが蓄積されない
フリーランスに業務を依頼すると、自社のリソースを使わずに業務が進められるメリットがある一方で、ノウハウが社内に蓄積されにくくなるというデメリットも発生します。
なぜならフリーランスは業務ごとに契約が終了するため、社内での知識や経験値の共有が進みにくくなるからです。
特に長期的な運用が必要な業務であれば、フリーランスに頼りすぎるとマニュアル作成や引継ぎなどの業務ができず、社内の成長に悪影響を及ぼすリスクもあるでしょう。
フリーランスの活用は便利ですが、長期的なノウハウを蓄積したいのであれば、自社メンバーへの知識共有も忘れずに行うことが大切です。
デメリット2|要件定義やマニュアルの設定が手間
フリーランスはあくまでも外注先です。
業務を依頼する際は自社の環境や仕事のルールなどが分かっていない状態が前提なので、具体的な要件定義や業務フローの説明が必須です。
要件定義が曖昧だと期待通りの成果が得られなかったり、業務の途中でトラブルが発生するリスクもあります。
基本的なマニュアルを事前に作成しておく、もしくは細やかな打ち合わせを重ねつつ徐々にマニュアルを作成していく方法がおすすめです。
マニュアル作成が手間に感じる企業であれば、長期雇用を目的とした契約社員を雇う方が効率的かもしれません。
フリーランスか契約社員か|雇う際の判断基準
今すぐ人材を確保したい企業は、フリーランスと契約社員のどちらを雇うべきかと悩む人もいるのではないでしょうか?
どちらもメリット・デメリットはあるため、以下の基準で雇い先を見つけるとよいでしょう。
契約する目的
業務の難易度や期間
報酬と時間
特に大切なのは、契約する目的です。
なぜ必要なのか、何を依頼したいのかを明確にすることで、報酬や契約期間、業務内容なども決まってくるでしょう。
まとめ
今回は、契約社員とフリーランスについてそれぞれの違いやメリット・デメリット、採用時の比較ポイントを詳しく解説しました。
契約社員とフリーランスは契約の種類が異なることから、社会保険や福利厚生、働き方などで複数の違いがあります。
契約の特徴を踏まえて採用を進めなければ、雇用コストがかかったり、業務がスムーズに進まないなどのトラブルが発生するリスクもあるため注意が必要です。
人材が不足していて、フリーランスか契約社員を雇いたいと考える企業の担当者の方は、まず目的を明確にして、どちらが必要かを見極めることが大切です。
フリーランスや契約社員の採用に関して、契約方法やコミュニケーションに不安があるという企業には、Workshipがおすすめ。
必要な人材を検索するツールや、採用時にはサポートを受けながら必要な手続きを進められます。
まずはサービス内容や実績をご確認ください。
https://enterprise.goworkship.com/
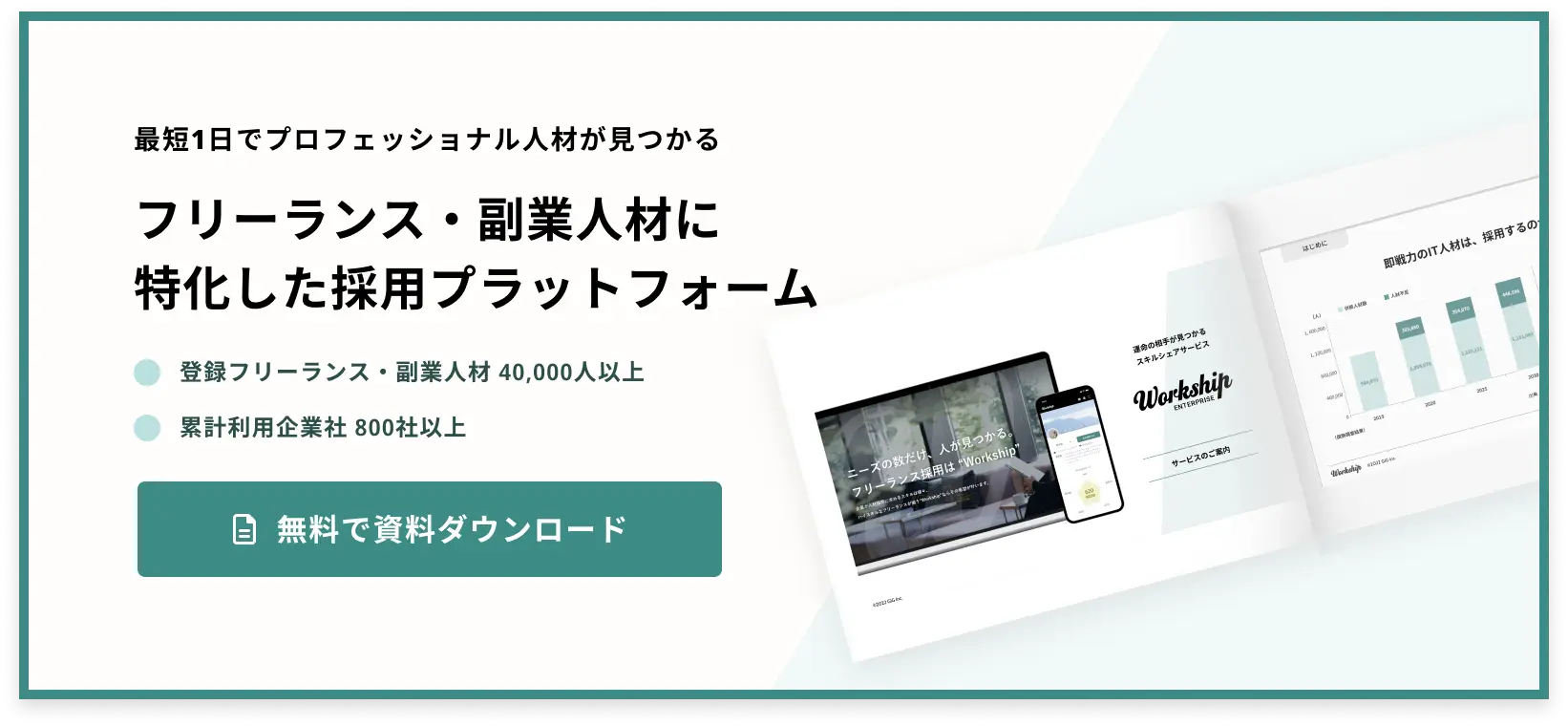 無料アカウント登録
無料アカウント登録